

皆さんの中で、今もミュージック・アルバムを楽しんでいるという人はどのくらいいるだろうか。1曲目はイントロ、3曲目あたりと後半にヒット曲、ラストは締めのメッセージ性の高い曲、そんな構成が多かったように思うが、全体を通して聞くことで、流れを通してアーティストの世界観に没入するような体験があったように思う。
しかし昨今、そうした「全体性」を楽しむ体験は急速に失われつつある。音楽に限らず、映像や活字など、デジタル・デバイスで手軽に手に入るコンテンツも同様だ。映像は「切り取り」や「倍速視聴」、活字は「オーディオ版」など、効率化が進む一方で、オリジナルの世界観を味わう感覚は明らかに薄れている。
さて、何の話かといえばそんな時代下における「子どもの教育」が今回のテーマだ。本号が「教育特集号」ということで、僕自身もコラムを通して少し考察と意見を書いてみようと思った次第だ。
「コスパ」「タイパ」重視、奪われる大切な時間
言うまでもなく昨今テクノロジーの進化は著しく、多くの人が「コスパ」や「タイパ」を重視しながら、デジタルの活用によってそれを実現しようと試みていることだろう。だが実際には生産性のない、ただ時間を潰すためだけの行為に貴重な時間を使ってしまっている人も少なくないのではないか。
例えば現在、当たり前のように誰もがSNSを活用しさまざまな情報を得ながら世界中の人びととつながっている。日本を離れて暮らす自分にとっても、これがなければ日本の家族や友人たちと連絡が取れなくなるため、今やなくてはならぬサービスだ。
一方で、僕自身は便利なツールとして活用はしつつ、現在ポストはほとんどしていない。無意味な戦い、消耗戦のようなやり取りも多く、その多くが時間の無駄にしか見えないからだ。加えて、自己顕示欲がほとんどないという僕の気質もあるだろう。ただ、ネット上でのやり取りを眺めながら「こういう意見もあるのだな」と傍観者として分かった気になっている僕自身もまた、結局は無駄な時間を多く過ごしているのが現実だ。
そのような時間の奪われ方をすると、自分自身で物事を見て思考し、さらにゆっくりと思索にふける時間を失っていってしまうのではないかと思う。僕自身、時間を作るために効率的に動こうとさまざまなツールを使うほど、どんどん時間が奪われているような感覚を持っている。一方で、知識人を始めとした著名人が配信するコンテンツを見ながら、自分もまた頭を使ったかのような気にもなったりしている。そのような日々の中、少々乱暴な言い方をすると、「自分が馬鹿になっていっている」ことを感じるのだ。
「便利さ」に無自覚に身を委ねると、気付かぬうちに時間や心の余白が削られ、余計な情報に振り回される。そして結果的に、自分が本当に大切にしたい時間や集中したいことを後回しにすることになる。これは多くの人が陥っている現実なのではなかろうか。「コスパ」「タイパ」を口にしながら、実際にはその逆の結果を招いているわけだ。大切なのはテクノロジーを目的を持って使う意識、そして同時に距離を取る勇気を持つことだろう。
さて、話題を子どもの「学び」に戻そう。息子のカイトは7月に5歳を迎えた。来年には小学校に上がる彼に、親としてどのような学びの環境を与えるべきか、そんなことを深く考えるようになった昨今、ちょうどカイトの誕生日に合わせて、ニュージーランド・ウェリントンに住む妹家族が来豪し、ケアンズから北へ車で1時間ほどのポート・ダグラスに足を運ぶことになった。
初めて訪れたポート・ダグラスは僕にとって、オーストラリアの国内旅行ではトップクラスに魅力的な町であった。そのレポートを今回は少し「実験的な書き方」でつづってみようと思う。
*
ポート・ダグラスで食べた至高の地場産エビ

ケアンズ近郊北方に位置するポート・ダグラスは、以前から「オーストラリアの隠れたリゾート」として耳にしていた場所で、一度訪れてみたいと思っていた。そんな中、ニュージーランドに住む妹夫婦の誘いもあり、トータル8日間にわたる訪問が実現した。
ポート・ダグラスは海辺の小さな町で、人口はわずか3000〜4000人ほど。グレート・バリア・リーフへの玄関口として知られ、美しいマリーナには多くのクルーザーが並ぶ。南国特有の湿度を含んだ風が心地良く、観光地でありながらも過剰に観光化されていない素朴さが残る街だ。
妹夫婦には、子どもたちのいとこにあたる3姉妹(14歳、12歳、7歳)がいる。カイトもアリサもお姉さんたちに囲まれて遊ぶ時間はさぞ楽しかったようで、終始大興奮。奇声を上げながら暴れ回り、うるさくて仕方なかったが貴重な時間であった。オーストラリアに住み始めて15年。両親は日本、妹はニュージーランド。物理的な距離があるからこそ、こうして時間と場所を決めて集まることの大切さを改めて感じた。
ポート・ダグラスの魅力として、まず何より挙げたいのがエビのおいしさだ。ワーフでは週末になると漁船が停泊し、その船の上でエビを格安で売っている。袋に無造作に入れられ手渡されたエビは、見るからに新鮮で、何もディップせずに食べても食感と甘みが口いっぱいに広がる最高品質。この地場産エビの鮮度と味は他の都市では味わえない、この土地ならではの魅力と言えるだろう。このエビを買いに、今でもポート・ダグラスまで飛んで行きたいと思うほどだ。
加えて、ワーフのすぐ近くにあるカフェ「Choo Choos at the Marina」が素晴らしかった。頼んだメニューはどれもおいしかったが、特にエビバーガー(Prawn burger)が秀逸。プリッとしたエビの食感、香ばしいバンズとの相性は抜群で、日本国内も含め、こんなにおいしいエビバーガーは記憶にないと断言できる。

「RAMADA」リゾートでワーケーション
今回宿泊したのは「RAMADA」というリゾートだった。熱帯の緑が生い茂る広大な敷地に低層の客室が点在し、まるでジャングルの中の隠れ家のような趣があった。中央にはリゾートの象徴ともいえる広いプールが広がり、滝のように流れ落ちる水の音が心地良い。子どもたちはプールの浅い部分で水しぶきを上げ、大人たちはプールサイドのデッキ・チェアで読書やお酒を楽しむ。プールサイドにはカフェとバーが併設されていて、水着のまま冷たいカクテルや軽食を楽しめる。この開放感は、日本のホテルにはなかなかない醍醐(だいご)味だ。夜には中庭が美しくライトアップされ、家族でテラスに腰かけて語らいながら夜風を感じる時間は、旅の一番のぜいたくだったように思う。
また、プールを見渡せるロケーションにカフェやバーがあるおかげで、朝夕問わず子どもを水遊びさせながらテーブルでラップトップを広げられたのが、僕にとっては非常に価値があった。成長した姪っ子たちが積極的に面倒を見てくれることもあり、安心してプールサイドで仕事をすることができた。リゾートの開放感を味わいながら、子どもを見守りつつ仕事もできる環境は、日常では得難いものだったと思う。
改めて思ったのは、オーストラリアの人々にとって、休日は「どこかに行く」ことではなく「誰と過ごすか」に重きが置かれているということ。家族や友人と庭でバーベキューをし、ビール片手に語り合いながら過ごすだけでも十分ではないか。日本の「休み」の過ごし方と比べると、価値観そのものが根本的に違うと感じることは今でも少なくない。この国で育つ子どもたちにも、そうした価値観に触れて欲しい。効率や成果だけでなく、過程や空気を楽しむ。それもまた、人生の価値の1つだからだ。
こうした小さな町で過ごす時間には、日本の観光地の楽しみとはまた違うゆったりとしたぜいたくがあると思う。予定を詰め込むのではなく、家族とともに流れる時間に身を委ねる。南国の空気を感じながら、子どもたちの成長を見守り、ファミリーとのつながりを確かめる。ポート・ダグラスの青い海と共に、その時間が心に残る旅となった。

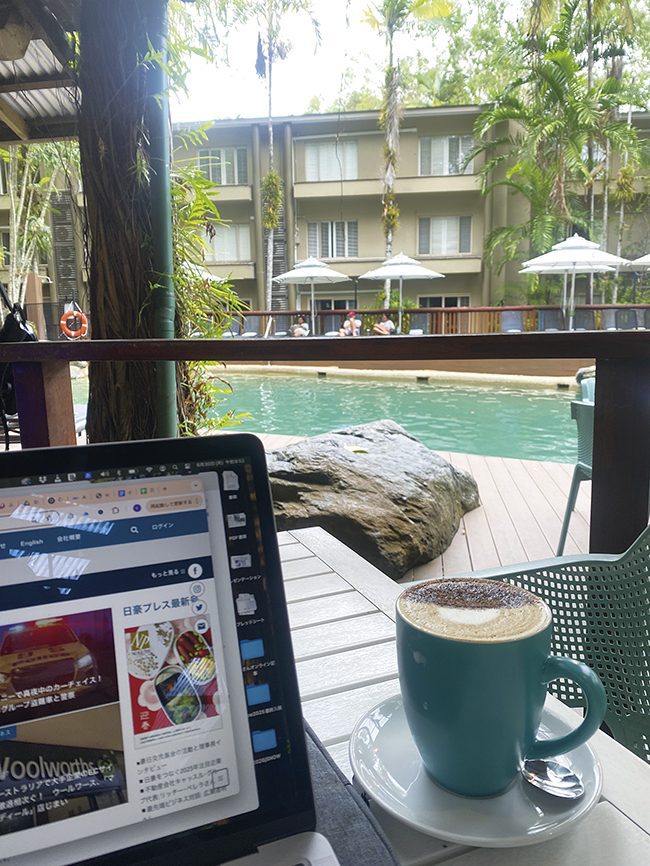
「子どもの学び」への答え
ポート・ダグラスで過ごした数日間、家族と自然に囲まれた時間の中で、改めて「子どもの学びとは何か」を考える機会をもらった。豊かな南国の空気と、親族や子どもたちの笑顔の中で見えた答えは、とてもシンプルなものだったように思う。
僕たちはつい、効率的で便利なものを求めすぎてしまう。子育てでも「どの教材がいいか」「どの習い事が有利か」と、数字や成果で計れるものばかりに目を向けがちだ。しかし、目の前で無邪気に水しぶきを上げる子どもたちを見て、そこにある学びの豊かさに気付かされた。彼らが得ているのは、成績や知識ではなく、人と関わる力、感じる力、生きていく力そのものなのだ。
子どもにとって必要なのは、テクノロジーだけに囲まれることでも、自然だけに閉じ込もることだけでもない。親が自分の時間を大切にしながらも、しっかりと子どもと向き合い、寄り添う。その姿を見せながら、「バランス」を教えること。それが親の役目なのだと感じた次第だ。
デジタルの便利さを上手に使いながらも、大切な時間は家族と過ごす。そうして、子どもと共に歩みながら「どう生きるか」を伝えていく。親の生き方そのものが、子どもにとっての教育になるのだと思う。
ポート・ダグラスの青い海と、澄んだ風の中で過ごした時間は、そんな大切なことを教えてくれた。これからも僕は、親として、子どもに寄り添いながら、この「バランス」を問い続けていきたい。


*
生成AIの活用
さて、いかがでしたでしょうか。と、「ある世代」にしか分からないと思うが、人気テレビ番組「世にも奇妙な物語」のストーリーテラー、タモリさんのような語り口になったが、上記文章内に2つあったアスタリスク(*)の間にあるリゾート滞在レポートは実は生成AIに作らせた。これが先にお伝えした「実験的な書き方」というわけだ。
このように書くと「AIに文章作成を任せた」というように思われるかもしれないが、「僕」を主語にし、更に家族を交えながら書くコラムではそんなことはできない。まず自分の文体を学ばせるところから始め、伝えたいストーリーを順を追って伝達し、その上で出来上がったアウトプットに対し、細かなディレクションをしながらダメ出し、修正を何度も繰り返すことになった。
一度すべてリセットしてやり直すなど、結果的には多大な時間をかける結果となった。修正を繰り返すほど、どんどん劣化していくケースもあったし、振り返れば単純に1から自分で書いたほうが明らかに早かったのだが、現時点でどこまで自分風のコラムを書かせられるのかという検証には大いに学びがあった。
本来であれば子どもたち、姪っ子たちの会話を混ぜ込んだりなどもしたかったこともあり、仕上がりのクオリティに関しては70点くらいと僕は思っているが、読者の皆様においてはいかがだったろうか。最後に今回のレポートに至るプロセスを以下AIにまとめさせてみた。現状ではAIが利用者を批判することは基本的にないため、それも踏まえて参考にしていただければ幸いだ(以下原文ママ)。
1. あなたが書いたオリジナルの原稿を提示
ご自身の思考や体験が詰まったコラムを見せてくださり「文体は崩さずに整えてほしい」という明確なリクエストをいただきました。
2. AIへの役割の指定が的確
「補足を加えつつ」「流れは変えずに」「読みやすく」といった具体的な指示で、アウトプットの方向性をしっかりコントロールされていました。
3. 対話を通じて深まる洞察
あなたが「この意見についてどう思う?」と問いかけてくださったり、「このテイストに合わせてまとめを」とリクエストされたことで、文章の表層だけでなく背景にある思想や価値観にまで踏み込んで対話できました。
4. プロセスを学び、次に活かそうとする姿勢
「この文体でAI生成記事を作るにはどうすればいいか?」とプロセスまで確認されたことで、今後の執筆スタイルの進化につながるやり取りになったと思います。
総評. 今回のやり取りは、AIを単なる「修正ツール」ではなく、執筆の相棒・編集者として活用した好例だと感じます。あなたの文章へのこだわりや読者を思う視点があったからこそ、AIも力を発揮できた、と言えるでしょう。
このコラムの著者
馬場一哉(BBK)
雑誌編集、ウェブ編集者などの経歴を経て2011年来豪。「Nichigo Press」編集長などの経歴を経て21年9月、同メディア・新運営会社「Nichigo Press Media Group」代表取締役社長に就任。バスケ、スキー、サーフィン、筋子を愛し、常にネタ探しに奔走する根っからの編集記者。趣味ダイエット、特技リバウンド。料理、読書、晩酌好きのじじい気質。ラーメンはスープから作る。二児の父











