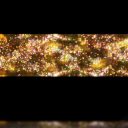第14回:夢の中へ
高校生のころ、海外留学を夢見てオーストラリア交換留学奨学プログラムの試験を受けた。3歳上の姉がAFS奨学生として、米国留学から日本に戻ってきた時期であった。父親は私の留学先は米国と信じていたので、それがオーストラリアと知った途端に、ものすごい剣幕になった。
当時、日本におけるオーストラリアに関する情報は限られていて、動物と大自然以外、生活文化についてはあまり知られていなかった。「留学するのなら先進国に行って学べ。オーストラリアは先進国とは言い難い。砂漠、毒クモ、蛇に水不足、一体そんな所で何を学べると言うのだ?」というのが父親の言い分だった。
私は、動物と大自然いっぱいのオーストラリアに子どものころから憧れていた。父親は昭和一桁生まれのガンコ親父の典型で、一度言ったらどうやっても聞いてくれない。インターネットのない時代のことである。私は図書館に行ってオーストラリアについてありったけの情報を集め、そんな父親に手紙を書いて説明することにした。
図書館で見つけたオーストラリアの本には、オペラ・ハウスのカラー写真が載っていた。「なんてきれいなんだろう」とオーストラリアへの募る思いでいっぱいの高校生の私は、父親への手紙を書き続けた。
奈良の興福寺に「一言観音」という人びとの願いをかなえてくれることで有名な観音様がある。そこにもお願いに行った。「どうかオーストラリアに行かせて下さい」オーストラリアに行きたい一心で、できることは、何でもやった。
合格通知が来て、東京で説明会が行われた。日本全国から15人の奨学生の中で、学生1人で参加したのは私だけだった。父親がまだ渋っていたから、保護者同伴は無理、私は1人新幹線に乗って東京に向かった。
しばらくして、何とかオーストラリアが英国連邦で教育制度がイギリスに似ていることや、世界的に見た生活水準、人びとの暮らしや考え方、将来性などを父親に理解してもらうことができ、その結果、私は遂に「自分で決めたのだから、泣き言は言うな」と父の承諾を得たのだった。
私はこうして17歳の春、他の14人の奨学生と共にオーストラリアに旅立った。成田空港からのカンタス便が離陸すると、みんな次から次へと泣き出した。私はそれを見て、「そんな心づもりなら行かなければいい」と留学仲間にきつい言葉を投げかけた。
私にとってのオーストラリアは一生の賭けだった。やっとの思いで勝ち得たこの機会、ホームシックで泣いている時間などなかった。私の胸中は興奮と期待でいっぱいだった。
到着した早朝のシドニーは、何ともすがすがしかった。留学プログラム協会の人たちが、空港から直接サーキュラーキーに連れて行ってくれた。そしてその時、目の前に現れたのは、あの写真で見たシドニー・オペラ・ハウスだった。
私は、この瞬間、夢がかなうとはこういうことなのだと実感した。心が解けていく、体は感動で震えていた。夢に見たシドニー・オペラ・ハウス。私は、遂に夢のオーストラリアにやって来た。

ミッチェル三枝子
高校時代に交換留学生として来豪。関西経済連合会、マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社に勤務。1992年よりシドニーに移住。KDDIオーストラリア及びJTBオーストラリアで社長秘書として15年間従事。2010年からオーストラリア連邦政府金融庁(APRA)で役員秘書として勤務し、現在に至る