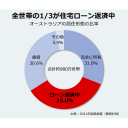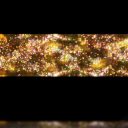生物や気象などの自然物が織り成す「その季節らしさ」は場所によって異なり、オーストラリアにはオーストラリアの春の形がある。初春となる9月、サウス・コースト地方の田舎町で新しい季節を彩るのは固有種の花々や生き物の姿だ。温暖化の影響と森林火災のシーズンの兆しも感じさせつつ、今年も色鮮やかな春が来た。(文・写真:七井マリ)
野生の花が咲く頃に

ジャスミンやツツジの開花が庭を明るくし、花から花へとミツバチや蜜を吸う鳥が飛ぶ。暦の上ではオーストラリアの春は9月からだが、その気配を感じるのは温かい日が顕著に増える8月下旬から。といってもそれは、ここサウス・コーストを含むNSW州など温帯エリアの話だ。日本の約20倍の国土に熱帯、亜熱帯、温帯、乾燥地域と幅広い気候帯が存在するオーストラリアでは、全土に同じ四季があるわけではない。動植物の分布も違い、春の風物詩にも地域ごとの個性がある。
NSW州を含むオーストラリア東岸では、ワラター(Waratah/和名:テロペア)や春咲きのボトルブラシ(bottlebrush/和名:ブラシノキ)などの固有種の花が春を彩る。私が暮らす地域の初春のイメージはボロニア(boronia)の花で、田舎に移り住んで野生の姿を初めて見た時の静かな喜びは忘れられない。乾いた森に映える無数のピンク色のつぼみが、小さな折り紙の風船のような形をして小枝に鈴なりに付き、かつてオーストラリアの絵本で見たボロニアと同じく微風の中で可憐に揺れていた。近隣地域の高齢者によると昔はもっと多くのボロニアが咲き乱れていたそうで、さぞ美しく詩的な光景だっただろうと想像する。
目に麗しい花の季節は、残念ながら花粉症の季節でもある。オーストラリア南東部の春の花粉症の主要因は、アカシア、ヒノキ、マツ、イラクサやイネ科の草など。国内の4人に1人が花粉症といわれ、私も田舎に引っ越してからくしゃみのせいで仕事や家事の手を止める日が増えた。
爬虫類と鳥たちの春

どこからともなく現れたトカゲやカナヘビは、冬の寒さで縮こまった体を緩めるように敷石の上で日光浴をしている。ヘビも頻繁に姿を見せ、変温動物の活発化が春の風物詩の1つであることは南半球の温帯でも同じだ。
日本との違いといえば、オーストラリアには数十センチから2メートル強にもおよぶ恐竜の子どものような大型のトカゲが何種類もいることだろう。全長60センチほどのイースタン・ブルータング・リザード(Eastern blue-tongue lizard/和名:ヒガシアオジタトカゲ)は、よく家からすぐの日当たりの良い倒木の前にいて時々目が合う。近付こうとすると逃げてしまうが、重量感があるので草むらを這う音も大きい。
温かい春は、鳥たちにとって子育てがしやすいタイミングでもある。オーストラリアン・ウッド・ダック(Australian wood duck/和名:タテガミガン)というカモの仲間が、カップルで可愛いヒナを7羽も連れて庭を歩き回っている。子育て中の親鳥は特に用心深いので、ストレスを与えないよう遠くから観察するのが良さそうだ。
けたたましい笑い声のような鳴き声で知られるラフィング・クッカバラ(laughing kookaburra/和名:ワライカワセミ)も、主として春に子育てをする。幼鳥はやがて親を真似て笑い声に似た声を出すようになるが、鳴き初めの頃は調子外れだったり途切れがちだったり。耳を傾けては、その子どもらしさに思わず頬が緩んでしまう。
有袋動物の子育て事情

この地域のカンガルーやワラビーの母親のお腹のポケットから、外の世界へと跳び出す子どもを見掛けるのも春が一番多い。親のすぐそばで不器用そうに草をかみちぎる幼子の姿が見えると、こうして命が続いていくのだと温かな気持ちになる。
初めての春を迎えたカンガルーやワラビーの子どもはちょっとした物音にも驚き、すぐに母親のポケットの中に潜り込んでしまう。ポケットはかなり伸縮性があるようで、一見入りそうにないサイズの子どもが手品のようにしっかりと収納される。そのまま跳ねて移動する母親の動きは明らかに重たげで、育児という仕事は生物種を問わず大変そうだ。
同じく有袋動物のポッサムも、この一帯では春が繁殖のピーク。夜行性の生き物なので間近で観察する機会はそう多くないが、お腹のポケットから出た時期の子を背中に乗せて歩く様子を見たことがある。四つ脚で移動するポッサムは、子を背負ったまま器用に木を登っていった。昼も夜も、生き物たちが子育てに勤しむ春だ。
乾燥、強風、高まる火災のリスク

花や動物に和むばかりではなく、春は火災のリスクに気が引き締まる季節でもある。サウス・コーストの初春は年間で最も雨が少ない時期。空気は乾燥し、気温は上がり始め、強風の日も多いので火事のリスクが高まり始める。その年にもよるが、NSW州の地方部では高温と低湿がセットになる10〜3月、つまり春から初秋が森林火災のハイリスク期間に指定されることが多い。その直前の初春の9月までに、森や庭に溜まった燃えやすい枝葉を処分しておくのが理想だ。
枝葉はグリーン・ウェイスト(green waste)としてゴミに出すのが一般的だが、田舎では量が多い場合は各戸の庭で焼却処分することもある。この辺りでは事前に行政機関や周辺住民に連絡したうえで、風のない日に剪定枝や枯れ枝を焚き火のように燃やしていく。火が大きくなりすぎないように少しずつ枝葉を足し、長い時は数時間にわたり火の番をする。初春でも火の周りにいると汗ばむほどだが、これを済ませておくと火災の季節の心配事が減るのだ。
気象局の発表によると、昨年のオーストラリアの春は例年より平均気温が2度も高かったそうだ。肌寒い日もある9月に30度を記録した日もあったほどで、気温上昇の傾向は数十年にわたり続いている。温暖化が止まらなければ、オーストラリアでは森林火災に注意が必要なシーズンは長くなる可能性が高い。気温上昇に伴ってもし花の開花期が変われば、蜜や花粉をえさとする鳥や虫の生態も、その捕食者の生態も変わっていくだろう。私たちが知っている四季はこの先も同じ姿を留めてはいないだろうという予感を前に、今年も巡ってきた春の光景をしっかり覚えておきたいと思う。
著者
七井マリ
フリーランスライター、エッセイスト。2013年よりオーストラリア在住