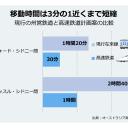“原発の是非を問う”こと──ルポ・原発問題①
新連載ルポ:シリーズ・原発問題を考える①

“原発の是非を問う”こと
──被災地支援活動家・小玉直也さん来豪
世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えつつ、自国内には原子力発電所を持たない国オーストラリア。被爆国であるにもかかわらず、狭い国土に世界第3位の原発数を誇る原発大国・日本。原発を巡る両国のねじれた構造を、オーストラリアに根を張る日系媒体が取り上げないのはそれこそいびつだ。新連載「原発問題を考える」では、原発を取り巻くさまざまな状況を記者の視点からまとめていく。
取材・文・写真=馬場一哉(編集部)
あの時の衝撃は今でも忘れることができない。2011年3月11日、記者は東京の自宅で原稿の執筆に追われていた。突如、大きな揺れが来た時にまず心配したのは家具が倒れて飼い猫をつぶしてしまわないかということだった。猫がベッドの下に隠れるのを見て、次に考えたのは本棚が倒れ、PCを直撃したら書きかけの原稿がおじゃんになってしまうということだった。必死で本棚を押さえ、揺れが収まるとともに落下した本の数々を一瞥。「すべて終わったら戻せばいい」と考え、再び原稿に向かう。震度5強。小学生のころ起震車に乗って以来、初めて体験する大きな揺れだったが、それでもなお、締め切りに追われた極限状態の身に驚いている余裕はなかった。
日本中が混乱するなか、それでも記者はテレビをつけながら原稿に向かい続けた。ある瞬間、あり得ない映像が目に飛び込んでくる。福島第1原発の建屋の爆発シーンだ。その前に津波があったはずだが、当時を振り返ってみると真っ先にこのシーンが思い返される。
さらに振り返ること20数年前。チェルノブイリの事故当時、記者はまだ小学生だったが、それでも当時の不穏な空気は肌で感じていた。雨が降ると「放射能が入っているかもしれないから絶対浴びるな」という母の教え通り、馬鹿の1つ覚えのように頭を隠した。放射能ほど恐ろしいものはない。子どもながらにそのことはしっかりと頭に刷り込まれていた。
その映像の持つ意味の理解を脳は一瞬こばんだ。そしてすぐにテレビで流され始めた「直ちに影響ない」という言葉を「そんなわけないだろう」という気持ちで聞いていた。
あの日を境に世界は変わった。だが、その脅威に対抗する術もなく、記者はその日、ただひたすらに原稿を書き続けた。翌日、会社に行くと社長からマスクを渡される。都内でも放射線量が上がっているとのことだった。マスクで防げるのか? 激しく疑問を抱きながらも、同時に、自分がメディアの人間としてできることは何だろうかと、思いを馳せ始めていた。
落ち葉のプレゼント
震災直後、記者も津波被害に遭った祖母の安否を伺いに青森県八戸市へと飛んだ。同地では海沿いに住宅がさほどなかったことから死亡者は3人と奇跡的に少なかったが、それでもビルほどの大きさの船が陸上に打ち上げられているのを見て絶句した。
11年11月1日、旅行でオーストラリア大陸をラウンドした20歳のころから夢見ていた豪移住を果たすべく、シドニー空港に降り立つ。震災直後の「超節電の夏」を乗り越えた直後の身に、当時、シドニーの電気の使い方はあまりに贅沢に映った。
それから生活を何とか再構築するための1年間を経て、生活が落ち着きを見せ始めると、不思議なものでそれまで忘れていたさまざまなことを思い出し始めた。そして、「今、自分がメディアの人間としてできることは何だろう」と再び考え始めた。
記者は早速、シドニーで反核運動などを行っている平野由紀子さんに連絡を取った。豪のウラン採掘に関するさまざまな問題、豪の反核運動の現状など、話をひと通り伺い、後日、改めて人を紹介していただくということになった。
そんな流れの中、11月中旬、被災地支援活動家の小玉直也さんと出会う。小玉さんは、被災地へのさまざまな支援活動を行っているNPO法人「アース・ウォーカーズ」の代表で、本業はカメラマンだ。彼は、地産地消せざるを得なくなっている福島県産の野菜を食べることに不安を抱えている人々に新鮮な宮崎県産の野菜を届ける「野菜プロジェクト」や、激しい精神的ストレスにさらされている福島の子どもたちを宮崎に招致する「保養キャンプ」などを開催している。今回はケアンズの日食を撮影し、その足で福島県の現状を伝える講演を行うべく、福島県出身の中学1年生J君とともにシドニーを訪れた。記者もまた彼自身から福島の現状に関して話を聞く機会を得た。彼は言う。
「保養キャンプに来た子どもたちが、帰り際、たくさんの落ち葉を大事そうにバッグに詰めるんです。僕は聞きました。『なぜ、そんなものを持って帰るの?』。子どもたちは答えます。『福島には放射能というばい菌が振っていて、木登りしちゃいけないし、花も虫も自然のものには触っちゃいけない。だから1年ぶりに落ち葉を触って、こんな感触だったなと思い出したの。学校に持って帰って、友達に1枚ずつプレゼントするんだ』。……僕はね、自然と乖離(かいり)した幼少期を過ごし、将来大人になった彼らが子どもたちに本物の自然について話すことができるのか心配です」
“原発の是非”を論じるエゴ

小玉さんは国内でも被災地支援活動家としてさまざまな新聞
に取り上げられている(写真は読売新聞)
オーストラリアという国は実に身勝手な国だ。国内に原子力発電所がない一方でウランの輸出量では世界第3位。核拡散防止条約(NPT)非加盟国のインドへのウラン禁輸措置を解除し、事実上インドの核保有を容認。これでは原子力産業を支えている国と言われても文句は言えまい。自国の安全はしっかりと確保し、そして経済の安定もまた確保するため世界に危険をばらまいている。しかし、自国の立場のみを考えるのであれば、最も合理的な道を選んでいるとも言える。
一方、日本は「核の平和利用」などという矛盾した言葉のもと国民を危険にさらし続けてきた。かつて、広島、長崎で痛い目に遭ったにもかかわらずだ。だが、今この場で是非を問うことはあまり意味がないと記者は考えている。自然を破壊し、人間を壊し、例え廃棄しても未来永劫、子孫にそのツケを払わせるようなものは、福島の例を見ても分かる通り、普通に考えればなくていいものであることは自明だ。だが、既にその多大な恩恵もまたこうむっているから話はややこしくなる。
いずれにせよ、私たちが話し合うべきことは、「どう付き合っていくか」、あるいは「どう付き合いをやめていくか」であり、是か非を論じることではない。
記者は試しに小玉さんに「原発に関してどういう立場でいらっしゃいますか?」と聞いてみる。
「100%、原発は将来なくなると信じています。こんなひどいものはないじゃないですか。人間が便利に生きるために、地球や人を傷つける。僕らは野蛮な生き物なんです。でも、長い歴史をひも解くとそれに気付くのは200年後です。200年後の教科書で『昔、原子力発電所があって、オーストラリアのウラニウムで被曝して死んでいった。そんな時代があったんだ、おかしいよね』と過去のものとして話される社会が必ず来ると思います。人間のモラルというものは歴史上いつでも前進しています。世の中には自分が、人間として到達できる一番高いレベルにいると思い込んでいる人が多すぎます。かつて、ジョン・レノンが『国境のない世界』について歌っていて当時はそんなものは想像することもできなかった。でも、ヨーロッパの国々を見ると国境のない世界はもう想像できます。トルコがEUに加盟するという話が出ていますが、もしそうなると、その隣はイラクです。1つになることはないと思いますか? 僕は国境がない、高いレベルの人間社会はやってくると信じています。そのための過程として、人間は今、戦争や原発、平和のテーマに取り組んでいるわけです。だけど、僕が『脱原発』と声を挙げるかというとそれはしません。その言葉はナイーブで、原発に依存している人があまりにも多い現状では、多数派になりにくいんです。『あの人、脱原発の人だよね』となると多数派の結集ができない。だから僕はそこに重きを置いてないんです」
反原発、脱原発、原発推進、消極的推進。立場を示す言葉にもいろいろあるが、いずれを明言したところで言葉は1人歩きを始め、できることは狭まっていく。声を挙げないという点では記者もまた小川さんと立場は同じだ。それを皆さんは無責任なことと思われるだろうか。
(次回に続く)