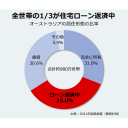ルポ:シリーズ・原発問題を考える⑱
「今なお、福島の電力に頼る現実」
──宮城県出身ジャーナリスト・村上和巳氏に聞く(2)
世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えつつ、自国内には原子力発電所を持たない国オーストラリア。被ばく国であるにもかかわらず、狭い国土に世界第3位の原発数を誇る原発大国・日本。原発を巡る両国のねじれた構造を、オーストラリアに根を張る日系媒体が取り上げないのはそれこそいびつだ。ルポ・シリーズ「原発問題を考える」では、原発を取り巻くさまざまな状況を記者の視点からまとめていく。 取材・文・写真=馬場一哉(編集部)
原発問題を取り巻く状況にもさまざまな立場からの観点がある。これまで被災者の視点、電力供給側の視点、当時東京在住だった記者の視点などさまざまな視点から原発問題を取り上げてきたが、前回から取材を行う取材者側の視点を紹介すべく、記者の知人ジャーナリストに登場を願っている。早速、前号からの続きに入っていこう。
戻りたい、戻れない
「私にとって原発災害取材の大きな転機となったのは2011年の秋、福島第1原発から南20キロ超に位置する福島県の広野町に行った時です。当時、福島第1原発から半径20キロは警戒区域に指定され、人の出入りが原則禁止されていましたが、広野町はその外側の半径20〜30キロ内で当時は緊急時避難指定区域とされ、かろうじて人の出入りは可能でした。この緊急時避難指定区域は当時解除目前だったのですが、やはり全く人気がなく気味が悪いくらいでした。
そんな中、60歳台くらいの老夫婦に会ったんですね。話しかけて来られて『ここから北には行けるのか』と聞かれた。しかし、そこから先は警戒区域ですから行けないのは当たり前で、何を言っているのだろうと私は思いました。一時帰宅の方や作業員、あるいはそうした人たちに何らかの形で随行するなど手段を得れば別ですが基本的には入れません。

男性にそのことを伝えると、『自分は今南相馬市の一部になっている小高区の出身だ』と言います。小高区は南相馬市の中で唯一警戒区域に組み込まれている地域です。聞くところによるとその方はだいぶ昔、若いころに家出をし、それ以来家には帰っていないそうなのですがボソッと『だけど帰りたいんだ』と言うんです。そして『どうにかして帰れねえかな〜、帰りてえ』って泣き始めた。
その時、ふと私も改めて思い出したことがあったんです。私は東京を出てから医療専門誌の記者を経て、フリーになったのですが、フリー時代は実家に帰る時に宮城県まで原付バイクで帰っていました。その帰路が今の福島第1原発の脇を通る国道6号線だったのですが、いわき市から今の南相馬市中心部の原ノ町までの約100キロはいわゆる田舎の原風景で取り立てて何もなかった。変化のない100キロは退屈で仕方なかったのですが、その時、目印にしていたのが東京電力・広野火力発電所、福島第2原発、第1原発でした。そのおじさんとの会話で急にその時のことを思い出し、妙に懐かしくなったんです。あの退屈さを感じられる日常が実はすごく幸せだったんだなと。
それまでは津波被災地ばかりを取材していましたが、それを機に原発被災地の取材を始めようと思い始めました。放射線に関しては、科学的に突き詰めても分かることと分からないことがあります。原発を巡る賛否が渦巻く中で、分からないものを分からない曖昧な状態で発信すれば、賛否双方の立場から非難されるでしょう。そのことはそれまでの周辺情勢を見て十分認識できていました。そしてその中で「分からないものは分からない」という姿勢を貫き続けることが正直、自分にできるかという怖さはありましたし、腰が引けていた面もありました。
しかし、取材者として原発被災地を避けていることで悔いの残ることがもう1つあったんですね。私はかつて地震関連の本を書いた時に、浜岡原発の問題を記事にしたことがありました。中部電力・浜岡原発というのは国がずっとこれまで警戒してきた想定東海地震の震源域の真上に位置することもあり、その時は『浜岡は大丈夫か』という視点で記事にしました。当時、取材に応じていただいたのは茨城大学理学部の名誉教授・藤井陽一郎先生でした。藤井先生は立場として反原発ではないとおっしゃっていましたが『浜岡に関してはいかにも悪い場所に置かれているので営業運転を停止して廃炉にすべき』との意見でした。当時インタビューが終わった際に藤井先生は問わず語りのように『原発そのものの老朽化を考えた時に災害に最も脆弱なのは茨城にある東海第2発電所と、福島の第1原発』とおっしゃっていたのです。当時の私は浜岡を記事にしなければならなかったこともあり、その話を聞き流してしまいました。自分はあの時の警告を無視してしまったということに忸怩(じくじ)たる思いがありました。そういった事情などもあって、11年の秋、いよいよ原発取材を始めるようになったんです」
激変した生活

水素爆発の痕跡を残す福島第1原発4号機。かたわらでは使用ずみ燃料棒取り出しのための建屋カバーが建設中だった(2013年3月)
「震災以前、私は国際情勢や医療問題などを中心に主に海外をフィールドに仕事をしていましたが、震災を機にそれが一気に国内に変わりました。北海道から千葉まですべての被災地を回ることを自分に課したのですがなぜそれをやったのかというとはっきりした答えはありません。お金のことを考えたらとっくに辞めています。フリーの活躍の場は、主に雑誌が中心になりますが、雑誌が3年間震災の情報を継続的に発信するかというとそうではなく、基本的には読者の志向に合わせることになります。3カ月も過ぎると読者は震災や原発の記事に辟易し、食傷気味になります。そしてそれ以降は、取材に経費はかかるけれども売れないという状況が続きます。フリーの立場としては赤字です。
被災地の取材を続けていると何かの時に声はかかりますがたまにしかないので取材費の足しにはならない。私の場合、国際情勢や医療の情報を伝えることでお金を稼ぎながら、被災地取材で使うという状況が3年間続いています。この状況を継続させている理由の1つは、私が東京に住んでいる被災地出身者ということでしょう。震災後、半年もすれば首都圏の在住者、特に東北に地縁血縁のない人の中では震災は過去のものとして消えていきますよね。私はそれを感じるほど意地になっていたような気がします。
例えば現在東京では普通の生活が営われていますが、そのための電力の一部は今でも突貫工事で復旧させた福島の東京電力・広野火力発電所が送っている。原発の犠牲を払ってなお福島が東京に電力を供給していることを知っている人はあまりいないでしょう。宮城県の津波被災地もまだ仮設住宅に人が住んでいます。しかし、そんなことはどこ吹く風という生活が東京で行われている。その落差が私の被災地取材のばねになっているような気がします。震災取材がフィールドワークになり私の生活も一変しました。職業がら1度関わるとその先をとことん知りたくなってしまうのですが、正直とんでもないものに関わってしまったなという気持ちもあります。
しかも、廃炉まで約40年と言われ、それを運営するのは経団連会長まで輩出した財界の雄・東京電力です。私ももう40過ぎですから人生の折り返し地点を越えていますし、残りの人生を考えるとえらいことになった、しかし、『蟷螂(とうろう)の斧』であっても、引くに引けない。そんな思いでいます。
被災地を回るようになって、新たな出会いもあり、現場ではさまざまな人情にも触れました。1年目に出会った方々に2年目、3年目と継続してお会いしていますが、私がふと顔を出すと、皆さんよく来たねと歓迎してくれます。彼らは寂しいんだと思います。かつてはメディアが東京から大挙して押し寄せてきたのに、それがぱったりと来なくなったことで、置き去りにされたような気がするんだと思います。私自身、これほど対象と密接にかかわりながら取材を続けるという経験はしたことがなかったので毎回新たな発見の連続です」
(次号に続く)

村上和巳───ジャーナリスト
宮城県亘理町出身。専門は国際紛争、安全保障、医学分野など。著書に『化学兵器の全貌』『大地震で壊れる町、壊れない町』、共著『戦友が死体となる瞬間─戦場ジャーナリストが見た紛争地』など。最近は東日本大震災に専念。震災関連の最新刊共著『震災以降』(三一書房)。