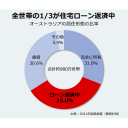ルポ:シリーズ・原発問題を考える⑳ 拡大版
「震災後」4年目の変化
──シドニーを訪れた福島の子どもたち
世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えつつ、自国内には原子力発電所を持たない国オーストラリア。被ばく国であるにもかかわらず、狭い国土に世界第3位の原発数を誇る原発大国・日本。原発を巡る両国のねじれた構造を、オーストラリアに根を張る日系媒体が取り上げないのはそれこそいびつだ。ルポ・シリーズ「原発問題を考える」では、原発を取り巻くさまざまな状況を記者の視点からまとめていく。 取材・文・写真=馬場一哉(編集部)
東日本大震災から3年半の歳月が経過した。その間、日本の原発を取り巻く状況はさまざまな様相を見せ、しかしながらメルトダウンを起こした福島第1原発自体の状況はほとんど変わっていない。同原発の先行きは根本的な解決法がいまだ示されぬまま、不透明というのが実情だ。そして現場の作業員がその多大なるリスクを背負わされている。汚染水の流出を食い止めるための凍土壁の造成も状況は芳しくない。コンクリートを流し込んで隙間を埋めるなどといった対症療法が施されるとも報じられているが、いずれにせよ、首相がかつて口にしたような「コントロールされている」状況とは残念ながら言えない。
そんな中、大きく変わったと言えるのは人々の意識ではなかろうか。多くの人々が3年半という歳月を経て「震災後」という状況に慣れてきたに違いない。記者も深く思うところあり2年弱ほど前に当連載を始めたわけだが(経緯は初期のバック・ナンバーを読み返してもらえると嬉しい)、毎月、原発および被災地の状況に思いを馳せ原稿を執筆しながら、それでもなお震災の記憶は少しずつ遠くに感じられるようになってきた。
そんな中、震災の記憶を呼び起こし、そして改めて風化させてはならないと自身に言い聞かせる機会が2度ある。1つは毎年訪れる3月11日、そしてもう1つがシドニーのボランティア団体が行っているホームステイ・プログラム「レインボー・ステイ・プロジェクト」だ。
津波や原発事故などで被害を被り、今なお苦しい生活を余儀なくされている福島県の被災地の子どもたちをシドニーに招待する同イベントは今年で4回目を迎えた。日本では、放射性物質の影響を危惧し土いじりなどを禁じられているような子どもたちに自然あふれるオーストラリア旅行をプレゼントし、約1週間を過ごしてもらうこの試みは確かに毎年子どもたちを癒し、そして将来の可能性を広げていると感じている。
昨年は代表の平野由紀子氏に話を伺うとともにフェアウェル・パーティーに参加させていただきプロジェクトの内容を記事にしたが、今年は記者自身、子どもたちがどのように滞在を過ごし何を日本に持ち帰ろうとしているのか、それを実際に目で確かめてみたいと考え、各イベントにできる限り顔を出させていただいた。4回目となるレインボー・ステイ・プロジェクトの様子を拡大版でお届けする。
ボンダイ・ビーチで融解する緊張の糸

7月28日早朝、日本から子どもたちを引率したレインボー・ステイ・プロジェクト日本事務局代表の木島正博さんとともに10人の子どもたちがシドニー空港へと降り立った。今回訪れた子どもたちは約40人の応募者の中から被災証明や作文の提出など、事前のプロセスを経て選ばれた10歳から16歳までの男子4人、女子6人。福島県から来たという共通項を除けば、仮設住宅で暮らしている子から児童養護施設で暮らしている子までさまざまなバックボーンを持った子どもたちが集まっている。
自主避難を行っている福島県会津若松市在住のM・Aさん(13歳)の母親は今回のプロジェクト参加に際し、このように語っていたそうだ。
「子どもたちの通っていた小学校は、最初に除染が必要と発表された5つの福島市内の学校の1つでした。私は地元を離れたくない思いも強かったのですが、夫が放射線の影響を非常に心配し『取り返しのつかないことになってからでは悔やんでも悔やみきれない』と主張し、震災後の5月に急きょ娘を転校させました。私も子どもたちも非常に苦しみましたし、今でも二重生活の経済的負担や、戻りたいという気持ちでつらい日々を送っています。子どもたちのパスポートは、もしまた原発が爆発したら国外しか逃げるところはないと考え、あらかじめ取っておいたものです」
さまざまな背景を抱えながら、成田空港で初めて顔を合わせた子どもたちは、例年、最初は緊張した面持ちで言葉も少なめだという。しかし、それが一気に融解するのが、シドニー空港到着後、毎年最初に訪れるボンダイ・ビーチを眺めた時なのだと平野氏は言う。
「それまでおとなしかった子どもたちが輝く海を前にパッと明るくなるんです。ビーチではしゃいだ後、すぐにみんな昔からの知り合いだったかのように仲良くなるのが今年もまた印象的でした。
毎年、さまざまな背景を持つ子どもたちが来ていますが、今年、レインボー・プロジェクトでは初めて児童養護施設から子どもを受け入れることができました。実はこれは想像していた以上に実現するのが大変なことでした。子どもの保護監督に関する規則は非常に厳しく、特に未成年者の場合、何かあった場合の責任問題、心のケアに関することなどさまざまな規則があります。しかし、今回、施設の園長先生は『ただでさえ社会体験が乏しい孤児の子どもたちに、こんな機会でもなければ絶対に行く機会がないであろう海外という世界をどうしても経験させてあげたかった』そうで尽力してくださいました。私たちのような小さな団体が、このように孤児の子どもを海外に1人で呼べたことは、ある意味大きな達成でした」
初日、ボンダイ・ビーチをはじめ市内観光を終えた子どもたちは各ホスト・ファミリーの家族と合流、それぞれ家路に着いた。
強く立ち直る力

アボリジニ文化の体験プログラムではウィロビーのゲイリー市長も訪れ、子どもたちにメッセージを送った(ワーナーズ・パークで)
滞在2日目の29日には、ウィロビー市のワーナーズ・パークでアボリジニの文化を体験するプログラムが行われた。少々肌寒い風の吹く中、子どもたちの前に最初に姿を現したのはウィロビー市長のゲイル・ジャイルズ・ギドニー氏。福島県から子どもたちが来ると聞き、歓迎の挨拶をしようと駆けつけた。
「ここではアボリジニのカルチャーについてのレクチャーや手軽なブッシュ・ウォーキングも楽しめます。ウィロビー市はシドニーの近辺でも非常に自然に恵まれた場所で、野性のワラビーや七面鳥などにも遭遇できます。今回、そういった楽しみを提供できることに本当に喜びを感じています。ぜひ、楽しんでいってください」
ゲイル氏の挨拶後、アボリジニ・アーティストのワラナーリ・カンタワッラ氏が登場し、子どもたちに先住民伝統儀式の紹介を行う。ワラナーリ氏は、国際的に活躍するアーティストであり、世界でも多数の賞を獲得、その作品はオーストラリア・ナショナル・ギャラリーにも展示されているという。氏はレインボー・ステイ・プロジェクトの趣旨に賛同し、初年度からサポートをしているそうだ。

アボリジニの伝統楽器「ディジュリドゥ」を演奏するワラナーリ氏(ワーナーズ・パークで)。氏は普段は国際的に活躍するアーティストとして知られている
少し照れながらも儀式に参加する子どもたち(ワーナーズ・パークで)
プログラムでは実際に伝統儀式を体験。音楽を奏でるチームと踊りを踊るチームの2班に分かれ、一方は音を鳴らし、一方はガイドの指示の下ポーズをとりながら踊る。エミューの格好を真似するダンスの格好のおかしさに、踊る側のチームは少し恥ずかしげに小さくなっており、一方で音楽を奏でるチームは「こっちで良かった〜」とはしゃいでいた。子どもたちの元気な声が森の木々の緑に静かに反射するのどかな時間だった。その後、子どもたちはブッシュ・ウォーキングに出かけ、野性のターキーを見つけては喜び、みんなでカメラを構えて写真を撮ったりなど自然の中でのアクティビティーを存分に楽しんだ。
翌日、子どもたちはノース・シドニー・ガールズ・ハイスクールを訪れた。記者は残念ながら同地を訪れることができなかったが、ここでちょっとしたトラブルが起きたのだと後に平野氏は語ってくれた。
「児童養護施設から来ているM・Kさん(16歳)が学校で両親のことを聞かれてしまったのです。その瞬間、おさえていた感情が一気にあふれ出て泣いてしまい、なかなか立ち直ることができませんでした。そんな中、生徒たちは皆、お昼ご飯も食べずにその子に寄り添って慰めていました。結果的に彼女は立ち直り、『みんなの気持ちが本当に暖かった』とポジティブな体験として受け止めてくれました。これまで4年間このプログラムを行ってきましたが、辛い思いをしている子ほど、強く立ち直る力を身に着けており、そして周囲への深い感謝の念を持っているような気がします」
CFMEUの協力

滞在4日目にはシティ内のオフィス・バルコニーで豪華な食事が振舞われ、全員でゆっくりと楽しい時間を過ごすことができた(CFMEUで)
6泊7日の滞在期間の後半3日間はゆったりとしたスケジュールが組まれており、基本的にはホスト・ファミリーとともに各々過ごす時間が大半だったが、そんな中4日目の31日には、全員分の航空券代を捻出してくれたオーストラリア最大の建築、森林、鉱山、エネルギーの複合労働組合「Construction Forestry Mining Energy Union(CFMEU)」の社屋内でバーべキューが開催された。シドニー・タワーなどシティのビル群に囲まれながらの屋外ランチはなかなか贅沢な経験だが、この日、子どもたちはすぐには会場に姿を現さなかった。
同プロジェクトは今年に入りさらに注目を集めているようで、日本のTBSやオーストラリアの公共放送局SBSからの取材を受けるなどしていた。この日、SBSのクルーにつかまり散々インタビューを受けた後、おなかを空かせて遅れて会場に現れた子どもたちには、バーベキュー以外にも、オイスターやエビをはじめとした豪勢な海の幸に加え、嬉しい手土産も配られた。その中には子ども向けの文房具などで人気の「smiggle」のギフト・カード50ドル分も含まれており、子どもたちは大いに喜んでいた。

CFMEU書記長のアンドリュー氏。暖かく子どもを見つめる表情が印象的だった(CFMEUで)

さまざまな支援を決断してくれたアンドリュー氏に感謝の意を英語で述べたK・S さん(10歳、CFMEUで)
「ようこそ10人の子どもたち!本当に大変な災害で大変な思いをしたことでしょう。今はこの時間を楽しんで、素晴らしい思い出を持ち帰ってください」
今回の寄付の発案者であるCFMEU書記長のアンドリュー・ヴィッカーズ氏は子どもたちに向けてこうメッセージを送った。
「私たちはウラン鉱山、原発に長い間反対してきました。そんな中、縁あって平野由紀子さんに出会い、レインボー・ステイ・プロジェクトへのサポートを依頼されました。私はその思いに胸を打たれ、子どもたちが巻き込まれている状況に対し、何かできることをしたいと思ったんです。子どもたちが直面した大変な出来事に対して私たちができるのはゆっくりとした休息の時間を送ることです。今回の滞在が良い思い出になることを願っています」
そう語る氏の表情は驚くほど柔和だった。子どもたちの姿を優しく見つめて微笑むその姿は記者の脳裏に強く、強く印象に残った。
「子どもがこんなことを思っていいのかな」
最終日前夜、シドニー・ノーザン・ビーチから少し内陸に入った緑深いオックスフォード・フォールズにある「オーストラリアン・テニス・アカデミー」でフェアウェル・パーティーが行われた。会場にはボランティアの人々、ホスト・ファミリーはじめ、協力者を中心に多くの人が集まり、滞在中のアクティビティー紹介やホスト・ファミリーへの感謝の言葉、ビンゴ大会、復興支援ソングの唱和などいろいろな行事が目白押しで楽しく時間を過ごしていたが、特に心に強く印象に残ったのは前出のM・Kさんがホスト・ファミリーの両親にお別れの言葉として語ったひと言だ。

M・Kさん(16歳)のホスト・ファミリー、ヒュー・ロスさん、柳生ひろみさんご夫妻(フェアウェル・パーティーで)
「絶対この1週間の経験を忘れることはないと思います」と話してくれたM・K君(16歳、写真真ん中、ホスト・ファミリーとフェアウェル・パーティーで)

ホスト・ファミリーの家の長男の火曜学校に体験入学したことが印象に残ったというK・K君(12歳、写真左、ホスト・ファミリーとフェアウェル・パーティーで)
「本当に素晴らしい時間をありがとうございました。そしてこんな家族がほしいなと心から思いました」
さらりとしたひと言だったが、彼女のホスト・ファミリーを務めたヒュー・ロスさん、柳生ひろみさんご夫妻は彼女の言葉に涙を抑えきれない様子であった。
「全部を支えてあげることは無理だけど何かの時に彼女の支えになってあげられたらと思っています。第2のふるさとと思って、困ったことがあったり、家族に会いたいと思ったりした時に、私たちを家族のように思って会いに来てくれたら嬉しいなと思います」
2人がそう語る中、パーティーの最後を締めくくる挨拶の言葉もまた最年長のM・Kさんが行うことになった。少し長くなるが彼女の言葉をそのままお伝えしよう。
「オーストラリアにいる人たちはすごく暖かくて、大自然はもちろんシティも楽しくて来てよかったなと思いました。英語はちょっと不安だったけど来てからは幸せ、幸せ、幸せでした。ガールズ・ハイスクールに行った時に泣いちゃったんですけどそれも含めて皆さまの温かみを感じることができていい思い出になりました。将来私は、保育士になりたいのですが、大きくなったらオーストラリア行ってみるといいよ、先生も経験したんだよと言いたいです。最後に、福島のことでオーストラリアにいる人に伝えたいことを話してくれとアンケート用紙に書かれているので話しますね(笑)。震災後の風評被害は3年経った今でもすごくあります。まだ帰れていない子もたくさんいて、みんな早く家に帰りたいのに国は何もしてくれないと私たちは感じています。子どもがこんなことを思っていいのかなと思うくらい何もしてくれません。福島は風評被害はあっても、本当にいいところなんです。私の住んでいるところは川に白鳥が遊びに来ます。綺麗なところなのでぜひ遊びに来てほしいなと思います」
「支援の輪」の連鎖
無事今年の開催を終えたレインボー・ステイ・プロジェクトだが、回数を重ねる中、これまでの課題をうまく生かしながらの運営を行うことができたと、自身、子どものころにシドニーに住んでいた経験を持つ日本事務局代表の木島正博氏は語ってくれた。
「選考基準の見直しやホスト・ファミリーとのマッチングを早めに行うなど、僕ら運営側も会を重ねることでより良い方法を実践できるようになりました。今回は渡豪前から子どもたちとホスト・ファミリーの間で交流を持ってもらえたことでスムーズな受け入れができたと思います。僕自身、子どものころにオーストラリアで過ごしたことでその後の人生が大きく変わりました。この滞在が子どもたちの将来にとって有益なものになることを強く望みたいですね」
平野氏は会を重ねる中で素直に感じていることをこう語る。
「1年目は震災が起きたばかりだから、子どもたちも何が起こっているのか分からないような様子だったことを思い出します。2〜3年目もどうなるか分からないけど政府が何とかしてくれると思っていたように感じます。ですが今年に入って福島の全く収束しない状況に対する見えない焦りを、子どもたちもまた感じているようでした」
また、子どもたちの将来の夢が段々と変わってきていることにも気付かされたという。「震災を経験し、いろいろな人に助けられたことで、自分もほかの人を助けたいと思うようになり、社会貢献できる職業を目指す子が増えています。自分たちのために動くたくさんの人々を見た経験が、自分もまたいつか支援する側にまわりたいという気持ちを芽生えさせているようです。震災の経験を前向きにに生かしたいという意思を持つ子どもが少なくないのです」
支援の輪の連鎖。平野氏はそう口にした。最後に、今後どのようにプロジェクトを展開していくつもりか聞いてみる。
「正直、規模は拡大できないと思っています。風化はさせたくありませんが、時間が経つにつれ協力も減っていくでしょう。だから、私は続けることが大事だと思っています。たとえ招待できる人数が少なくなっても続けていくことが重要だと思っています。彼らにとっては今より5年目、6年目、さらにそれ以降が大変なわけですから」
記者もまた、たとえ時に陳腐な内容になってしまったとしても、忘れぬために、風化させぬためにこの連載を続けていこうと思う。