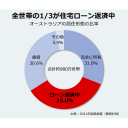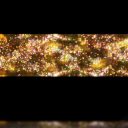約2年前にサウス・コースト地方で田舎暮らしを始めたころは、カンガルーとワラビーを見分けることができなかった。ここでは庭や森を跳び回る有袋動物は極めて身近な存在で、カンガルーとワラビーが同じ場所で草を食べていることもある。毎日眺めているうちに、似ているようで異なるカンガルーとワラビーの見分けが付くようになり、生態や雌雄の違いも少しずつ分かってきた。(文・写真:七井マリ)
隣人たちが見分けるカンガルーとワラビーの顔

オーストラリア国内には、カンガルーもワラビーも複数種が生息する。どちらも草食で、飛び跳ねて移動し、色や形も似た有袋動物だ。生物学の分類上も体のサイズだけがカンガルーとワラビーを隔てる要素であるという。一般的にカンガルーは体が大きくワラビーは小さいとはいっても、若いカンガルーも小柄なのでサイズだけで見分けるのは難しい。
田舎に移住してきたばかりのころは、なぜ隣人たちがカンガルーとワラビーを瞬時に見分けられるのか見当も付かなかった。そこで写真を撮り溜め、見分けるポイントを隣人に尋ねてみたら、顔が違うのだと言う。カンガルーはシカやウサギのような口元をしているのに対し、ワラビーはネズミやリスに近い顔立ち。そう思って目を向けているうちに、段々と違いが分かるようになってきた。この辺りによくいるイースタン・グレー・カンガルー(eastern grey kangaroo/和名:オオカンガルー)とレッドネックド・ワラビー(red-necked wallaby/和名:アカクビワラビー)という種を比べると、後者は鼻筋と耳の縁が黒っぽいのも見分けるヒントになる。
加えて、尾の形にも違いがあると聞いた。立ち上がっている時に尾の付け根から地面に付いているワラビーに対して、カンガルーは尾の途中から地面に付くような形状をしている。そうは言っても姿勢によって見え方が変わるので、これはなかなか難易度が高い気がする。
逃げるワラビーとあまり逃げないカンガルー

2年ほど田舎で暮らす間に分かったのは、ワラビーの方がカンガルーよりかなり臆病だということ。30メートル離れた所から歩いて来る人間を見つけただけで、ワラビーは弾かれたように逃げ出すので、近距離からの観察や撮影は運を要する。
対してカンガルーは、人間が10メートル以内にいても逃げずに庭で草を食べ、日光浴をしていることがある。必要な距離さえ保てば人間は危険ではないと認識し、慣れるようだ。とはいえ、草を咀嚼(そしゃく)しつつも警戒心を漂わせたり、少し移動してこちらの様子をうかがっていたりすることもある。
暑い日に大きな椿の木の下で何か気配がすると思ったら、カンガルーの母子が日陰に寝そべって涼んでいた。子カンガルーは母親の背後に回って私と距離を取ったが、眠たげな母親は頭を上げて私を一瞥(いちべつ)しただけだった。午睡を中断するにあたいしない人畜無害な相手だと思ったのかもしれない。ただしこれは庭に来る親子の話で、よそで見るカンガルーはワラビーほどではないがもう少し機敏に人間から離れようとする。
野生動物の食事中や休息中は邪魔をしないよう、姿を見たら静かにその場を離れるようにしている。警戒心が強いワラビーはそれでも驚いて逃げてしまうことがあり、なんだか申し訳ない気持ちだ。
母カンガルーが発した威嚇の音

カンガルーとワラビーは基本的に静かな生き物だという点も共通している。仲間同士で声によるコミュニケーションを頻繁に図ることはなく、他の動物に対しても同様だ。
庭に毎日来るなじみの母カンガルーが私に対してはっきりとした威嚇音を発したのは、この2年でたった一度だけ。降り出した雨の中、時々しか着ない赤い撥水ジャケットのフードを目深に被って足早に庭を横切ったら、離れた所で草を食べていた母カンガルーが立ち上がり、まっすぐ私に視線を向けながらうなるような低い音を発した。毎日顔を合わせても何も言わないのになぜ今日だけ、と不思議だったが、見慣れないジャケットのせいで恐ろしい生き物だと認識したのかもしれない。いつもやるように声を掛け、怖がらせないようにゆっくりとフードを外して顔を出してみた。なんだいつもの人間か、と思ったかは不明だが、母カンガルーがそれ以上うなり声を上げることはなかった。普段、うなりも逃げもしないのは私を認識しているからだとしたら光栄だが、カンガルーが個々の人間を識別しているかどうかは確かめる術がない。
ここまで書いて、ワラビーについては警戒や威嚇の声を聞いたことがないと気が付いた。それもそのはず、ワラビーは人間を威嚇などせず猛スピードで逃げ去ってしまうからだ。
筋肉質で見分けやすいオスのカンガルー

雌雄の見分け方でいえば、ワラビーもカンガルーもお腹の袋の存在が認められればメスだと分かる。ただしそれが分からない場合でも、カンガルーは体躯や人間への態度で雌雄を区別できることがある。
隣人の敷地内で立ち話をしていたら、開けた草地の50メートルほど向こうにひときわ大柄なカンガルーが1頭だけいるのが見えた。筋肉の発達した上体から一目でオスだと分かった。オスのカンガルーは私たちに気付くやいなや立ち上がり、荒々しいうなり声を上げながら反らした胸板を左右の前肢で掻きむしるような仕草を見せた。それを見て隣人は、目を合わせずに離れよう、と私を促した。
身の危険を感じたのはこの時だけだが、庭でもオスのカンガルーを時々見掛ける。成熟したオスの筋骨隆々とした体は遠目でも十分な迫力があり、雌雄の区別が付きやすい。だが、ワラビーの雌雄の違いを知るにはもっと観察が必要なようだ。田舎暮らしの中で体験しながら学んできたことがある一方で、まだ知らないことが山ほどあるという事実がこれからも観察力を鍛えてくれるに違いない。
著者
七井マリ
フリーランスライター、エッセイスト。2013年よりオーストラリア在住