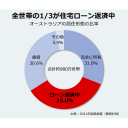ダリア、ユリ、ツユクサなど日本でなじみの花も咲くオーストラリアの夏だが、田舎の濃い緑の中では固有種の花の控えめなたたずまいも美しい。野原や樹上にひっそりと咲く野生の花々は、派手さはないがオーストラリアの自然の魅力の1つだ。南半球で近付く夏の終わりを前に、サウス・コースト地方で暑気の中に咲くオーストラリア固有種の花の思い出を振り返りたい。(文・写真:七井マリ)
ティー・ツリーの効能と花の可憐さ

この辺りでは晩春から夏にかけて、ティー・ツリー(tea tree)が白く可憐な花を咲かせる。花弁は薄く繊細で、満開の頃にそよ風で舞い散る様は束の間の雪のようだ。ティー・ツリーの花に集まる無数のハチの羽音に、高い枝を飛び回る小鳥のさえずりが混じる。木そのものは高く成長するが、花も葉もこぢんまりとしているので陽射しを完全に遮ってしまうことはなく、下を歩けば木漏れ日が明るい。
ティー・ツリーの葉は抗菌作用のある物質を含み、抽出した精油(エッセンシャル・オイル)は肌荒れのケアなどに役立つ。日本にいた頃にオーストラリア産のティー・ツリーの小瓶を持っていて、ふたを開けて漂う清涼感と青みのある香りが好きだった。その頃はどんな木か知らず、オーストラリアで実物を目にした時は顔を知らなかった文通相手に初めて会ったような心地がした。
ティー・ツリーはこの辺りを含めオーストラリアの森林ではよく見られる木の1つで、国内外に数十種類が存在する。オーストラリア先住民の間では傷や咳を癒すために使われてきた薬用ハーブだが、効能だけでなく花の美しさも知っていっそう印象深い木となった。
帽子の形のボンネット・オーキッド

ボンネットの形に似ているだろう、と言って隣人がボンネット・オーキッド(bonnet orchid)という固有種の蘭の一種を見せてくれた。ティー・スプーン以下のサイズの花だが、確かに近代以前の西洋社会で女性が日除けのためにかぶっていたボンネットのような形をしている。ジャン・フランソワ・ミレーの油彩画「落穂拾い」で3人の農村の女性が身に付けているあの帽子だ。
パートナーと共に隣人宅にお茶に招かれた日に、広い敷地内を案内してもらった。居家のほんの目と鼻の先に森があり、分け入って行くとユーカリの巨木や小川、豊かな植生が広がっている。木々が途切れずに茂る森の中は日陰が多く、夏でも日なたと比べてひんやりとする。
隣人がボンネット・オーキッドを指し示したのは、日陰の森の中を大量のヒルを避けながら歩いていた時。注意していなければ踏んでしまいそうなほど小さい花だが、一風変わった形と濃いワイン色が相まって凛とした存在感だった。私の記憶の中で、ボンネット・オーキッドの名称はあの時の森の景色と対になっている。植物を観察した記憶と共にその名を覚え、それを思い出すたび、言葉の後ろに広がる情景を繰り返し味わえるのがいい。
南半球の夏に咲くブルーベル

明るい緑色の茂みにぶら下がるように咲く、1センチほどの紫がかった青色の花の愛らしさに目を奪われた。オーストラリアン・ブルーベル(Australian bluebell)またはブルーベル・クリーパー(bluebell creeper/つる性のブルーベル)と呼ばれる植物だ。原産地は西オーストラリアだが、現在では反対側である東海岸沿いのこの辺りにも自生している。欧州に「ブルーベル」と呼ばれる別の植物があり、それと似た釣り鐘型の花を持つオーストラリア版の植物というわけだ。
「オーストラリアの」という言葉を冠した通称を持つ植物は無数にある。かつて入植者や移民が当地の固有種を初めて見て、故郷にある似た植物を偲んで名付けたのだろう。彼らに発見される以前から、6万年以上の歴史を持つ先住民が呼んでいた通称も存在する。そうした文化背景ゆえか、広い国土ゆえか、オーストラリアでは1つの植物が何通りもの通称を持つことが珍しくない。
逆に、複数の植物に対して同じ1つの通称が使われていることも往々にしてある。上の写真の花は世界共通の学名でいうと「Billardiera fusiformis Labill」というトベラ科の植物だが、通称である「Australian bluebell」を検索すると全く別の学名を持つキキョウ科の花も出てきて混乱する。英語の通称を覚えることで精一杯の私に、ラテン語の学名までは少々荷が重い。誤認防止のためにせめて、植物の細部まで写真に撮ってから図鑑やインターネットで名称を調べるようにしている。オーストラリアン・ブルーベルの花は軽く小さく微風にも揺れるので、ピントを合わせては何度も撮り直した。
乾いた地面にも咲くパステル・フラワー

今夏の前半、この辺りでは降雨が極めて少なく、露出した地面に土ぼこりが舞う日が続いた。春から続く乾燥によって庭の木陰や森の中の土も著しく乾き、積もった枯れ葉の下を10センチ近く掘ってもまだ水気がなかった。ユーカリの木々は水分の蒸散を防ぐために葉を大量に落とし、ひび割れた地面には半ば枯れた雑草がへばりついていた。干ばつの多いオーストラリアでは見慣れた光景だ。
そんな環境で生きる当地の植物は乾燥に強いものが多い。パステル・フラワー(pastel flower)と呼ばれる固有種は、熱帯雨林などに多く自生するが、乾いた森林にも適応している。家の近くの木陰で見つけたパステル・フラワーは、白に近い藤色の5枚の花弁の一部に紫色の斑点が散った小さな花。地面に溜まった枯れ葉の間で涼しげに咲き、極度の乾燥や熱波をものともしない。パステル・カラーの柔らかい花弁からは想像し得ないたくましさだ。
1月半ば、数週間ぶりに降ったまとまった雨が渇いた土や植物を優しくぬらした。パステル・フラワーの濃い緑色の葉に付いた水滴が、その色をいっそう鮮やかに見せた。
オーストラリアで田舎暮らしを始めたばかりの頃は、自然の細部にまで意識が及ばないまま季節を過ごしていた気がする。決して派手ではない野の花も見落としていたものの1つ。小さな花々の存在が目に留まるようになってきたのは、それだけここでの生活に慣れてきたということかもしれない。
著者
七井マリ
フリーランスライター、エッセイスト。2013年よりオーストラリア在住