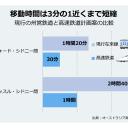外国人指揮者として
ローカル楽団をまとめること
指揮者
村松貞治
×
doq®代表
作野善教
日系のクロス・カルチャー·マーケティング会社doq®の創業者として数々のビジネス・シーンで活躍、現在は日豪プレスのチェア・パーソンも務める作野善教が、コミュニティーのキー・パーソンとビジネス対談を行う本企画。今回ご登場頂くのは、ヨーロッパ、オーストラリアで研鑽を積み、現在はシドニーをベースに指揮者として活躍する村松貞治氏。オーケストラを統率する指揮者の立場から見えるチームのまとめ方など多岐にわたるお話を伺った。
(監修・撮影:馬場一哉)
PROFILE

むらまつさだはる
ストラスフィールド交響楽団芸術監督。シンフォニア・ジュビラーテ芸術監督。シドニー・ユース・オーケストラ指揮者。エクセルシア・カレッジ講師・指揮者。スズキ・チェロ・アンサンブル指揮者。才能ある若者に贈られるモーティマー・ファーバー指揮者賞受賞、エメリッヒ・カールマン国際指揮者コンクール・ファイナリストなど数々の功績を誇る。19年には日本国外務大臣表彰も受賞。
Web:sadaharu.net
PROFILE

さくのよしのり
doq®創業者・グループ·マネージング・ディレクター。数々の日系ブランドのマーケティングを手掛け、ビジネスを成長させてきた経験を持つ。2016年より3年連 続NSW州エキスポート・アワード・ファイナリスト、19年シドニー・デザイン・アワード・シルバー賞、Mumbrellaトラベル・マーケティング・アワード・ファイナリスト、移民創業者を称える「エスニック・ビジネスアワード」史上2人目の日本人ファイナリスト。

作野:村松さんに初めてお会いしてからもう10年が経ちますね。お互いにまだまだ駆け出しの頃で結果を出そうと切磋琢磨していた記憶があります。これまでの経歴などを含め、本日はお聞きしたいことがたくさんありますが、まずは何がきっかけで日本を出られたのか教えて頂けますか?
村松:18歳で日本を出てイギリスの音楽大学に留学しました。日本では、国内の音楽大学を卒業後に海外の音楽大学に留学するのが一般的ですが、僕は音楽大学に行こうと決断を下したのが他の人よりも遅かったのです。だから日本で音楽の英才教育を受けた人たちと、同じ土俵で勝負するのは到底勝ち目がない。ならば一般的なルートとは逆になるけれど、「クラシック音楽の本場、ヨーロッパで勉強してみよう」と決意しました。ただ僕はイタリア語もドイツ語もできないので、消去法でいくと、これまで学校で勉強してきた英語が使えるイギリスが選択肢に残ったわけです。
作野:18歳で日本を出ることを決心したのは、相当な強い意志がないとなかなか実行できないことだと思います。
村松:強い意志を持って海外に出られる人は多いと思いますが、僕の場合、愚直というか若気の至りのようなものでした。大人になり家庭を持った今ならなかなかできない選択でしたが、あの頃はただまっすぐにしか進めなかったんです。また当時はビートルズが好きで、イギリス独自のポップ・カルチャーに憧れていたこともイギリス行きを決めたきっかけの1つになりました。
作野:海外に行かれたのはそれが初めてですか?
村松:実はイギリスに行く数カ月前に、先輩を訪ねにアメリカのロサンゼルスに1週間旅行に行きました。しかし空港に到着した瞬間、車で強盗に襲われ荷物を全部奪われたんです。着いてすぐの出来事でしたから、すっかりアメリカ恐怖症になってしまい、アメリカ留学という選択肢は自分の中から消えました。
作野:それで留学先がイギリスに固まったわけですね。イギリスに初めて到着した時の心境は覚えていますか?
村松:アメリカで強盗に襲われたことがトラウマになっていたので、イギリスに着いた時もまずはホテルまで無事たどり着けるよう自分の身を守ることに必死でしたね(笑)。
作野:イギリスに着いて、早速指揮の勉強を始められたのですか?
村松:まずは語学学校に入りました。実はイギリスやオーストラリアの音楽大学は日本と違って大学に指揮科が存在せず、大学院に行かないと指揮を専門的に勉強できないんですよ。日本で指揮者を目指す人たちは、高校卒業後に音楽大学の指揮科に進まれる人も多いですが、イギリスなどでは大学で楽器や作曲の勉強をした後、大学院でやっと指揮を学ぶことができるのです。結局、僕は語学学校で勉強後、大学に入りホルンを専攻しました。
作野:ホルンの演奏はこれまでに経験があったんですか?
村松:中学、高校時代にずっとホルンをやっていたので、大学では自ずとホルンを選択しました。ただ僕はホルン奏者になるつもりは全くなく、あくまで指揮者になるために留学したわけですから、大学院への足掛かりとして大学生活を頑張ろうと乗り切りました。
作野:そもそもなぜ指揮者を目指そうと思ったのですか?
村松:僕は中学、高校で吹奏楽部の部長をやっており、先生が不在時には指揮を振っていたので、ある程度の経験は積んでいました。ただ当時、僕は指揮よりも作曲のほうに興味があり、いざ進路を決める段階になって後輩たちに将来のことを聞かれた時、「作曲家になろうかな」と話したら、「先輩は指揮者でしょう」と言われまして。今まで指揮はやっていたけれど、それが職業になると考えたことはなかった。でも、第三者から素質があると指摘され、「じゃあ指揮者を目指してみようかな」と、将来の方向性を作曲家から指揮者にシフトしたんです。

作野:大学院では具体的にどんな指揮の勉強をされたのですか?
村松:ピアノやオーケストラに合わせた実践的な授業が多かったです。例えば、事前に「次の授業ではベートーベンの交響曲〇番をやります」と通知され、後日授業では2台のピアノ演奏に合わせて指揮を振り、先生から技術的な指導を受けました。そしてその日の夕方になると、今度は実際のオーケストラの演奏に合わせてまた指揮をし、先生から再度指導を受けるといった繰り返しでしたね。
作野:技術と言えば、僕もずっとサッカーをやっていて技術面についてはよく考えます。サッカーに関して言えば、技術のみならず運動量、サッカーへの理解度、チームメイトからの信頼度、自分のフィジカルの強さなどの要素がどれも高い人が優れたプレーヤーであると僕は考えていますが、優れた指揮者に必要な要素とは一体何なのでしょうか?
村松:耳の良さはとにかく大事です。それに加え、自分の頭の中でリハーサル前に設計図がどれだけ構築されているか、そして限られた時間内での適格なリハーサル能力も求められます。また、作曲家や楽器に対する知識も必要ですね。僕はホルンを専攻しながら、並行して弦楽器についても勉強しました。その他、オペラなら語学力も大事です。複数の語学を話すことができれば、いろいろな国に行ってもすぐに対応することができますから。
コンプレックスの克服に10年
作野:イギリスでの学生生活ではどのようなご経験をなされましたか?
村松:僕は海外経験も知識もほとんどない状態でイギリスに行ったので、初めは外国人がバイオリンを持っているだけでプロに見えました(笑)。とにかく彼らは楽器を持っているだけで様になる。クラスでアジア人は僕1人でしたし、コンプレックスを払拭するのに10年ぐらいは掛かりました。
作野:そのコンプレックスはどうやって克服されたのですか?
村松:時間が解決してくれた面も少なからずありますが、場数を踏んで経験を重ねていくことで耳が鍛えられ、彼らの中にも上手な人、決してそうでない人がいることが見えてきたんです。それで、自分自身をいかに上手な人のレベルに引き上げていくか、また上手く見せるかということを常に考え研究しました。
作野:それはビジネスの世界でも同じことが言えますね。例えば僕の場合、ビジネスで初めてアメリカに行った時、アメリカ人のプレゼンテーションのレベルに圧倒されました。プレゼンテーターは自信に満ち溢れ、資料も完璧で説明もユーモアに富んでいる。でも実際に何年か仕事をして月日が経つにつれ、相手の実力が垣間見えた時に「それぐらい自分だってできる」と思える場面が何回もありました。外国人と比べると日本人は、プレゼンテーションでの見せ方といった点は不得手なのかもしれないですね。
村松:そうかもしれませんね。大学院時代の話から時期は少しずれますが、プレゼンテーションのスキルは指揮者にも求められます。指揮者は60~70人の演奏者を目の前に曲への思いを語るわけですから、僕はその思いを伝えようと自分の中で必死に練習を重ねていました。指揮科の授業では、先生が僕のリハーサルを後ろで見ているのですが、ある日先生から「サダ、つたない英語で色々語るな。皆、楽器を弾きたくてここに来ているんだ。君の話を聞きたくてここにいるわけじゃない」と言われ、ハッとさせられました。
作野:なかなか厳しいですね。
村松:実は音楽の世界では、どの国の言語でもたった8個の単語で9割リハーサルができると言われているんです。その単語というのは「速い、遅い、大きい、小さい、強い、弱い」などですね。先生からは、「君は9割の仕事をしないで、残りの1割のプレゼンテーションの部分をいかに上手くこなそうかということばかり考えているだろう。簡単な英語でいいから、まずは9割の仕事をきっちりやる。プレゼンテーションに力を入れるのはその後だ」と指摘されました。
作野:それは大学院でイギリス人の先生に言われたのですか?
村松:いえ、これはシドニーでハンガリー人の先生に言われた言葉です。彼もハンガリー出身で英語が母国語ではないので、僕の立場をよく理解していたのでしょうね。
作野:結局、仕事で中長期的に継続して結果を出そうと思ったら、9割の部分で勝負をして誰よりも長けていることが大事ですね。
指揮者として学んだコミュニケーションの大切さ
作野:大学院を卒業した後、日本で指揮者として活動を始められたんですか?
村松:指揮科を卒業して日本に帰国後、履歴書を100通ぐらい送ったのですが、どこからも返事がなかったんです。僕はまだ24歳で経験もなく、海外の有名大学の指揮科を出たぐらいでは誰も見向きもしてくれない。「あ、これが現実なんだ」と思い知らされましたね。今後、どうしようかと悩みましたが、若さを逆手に取ってあらゆるコンクールに出場し、研鑽を積んでいきました。また東京で音楽関係の仕事も1年ほどしていたのですが、ある日、文化庁の新進芸術家海外研修制度を知り、ちょうどイギリス時代の友人から「シドニーに良い先生がいるよ」と教えてもらったこともあり、2009年にシドニーに来ました。
作野:それで現在、芸術監督を務めていらっしゃるストラスフィールド交響楽団の指揮者になられたのですね。オーストラリアに来てから、日本のオーケストラとの違いを感じたことはありますか?
村松:基本的に音楽を作る上で、日本と海外の違いを意識したことはほとんどないですね。ただ、「バイオリンならバイオリン、チェロならチェロ」と、楽器ごとに演奏者の性格が国を超えて共通しているのは面白いと感じました。
作野:村松さんは今、指揮者として楽団を率いていく立場にあるわけですが、これまでに心掛けてきたことはありますか?
村松:楽団員の立場に立ってコミュニケーションを行うことは常に心掛けています。僕自身の体験ではないのですが、コミュニケーションの大切さを実感した出来事がありまして。以前、マスタークラスの指揮者の先生が大学でオペラのリハーサルをしていたので、僕はそれを見ていました。先生はリハーサルの全容をつぶさに把握しており、「さすが素晴らしい指揮者だな」と感心していたのですが、いざ先生が投げかけた言葉を、聞き手であるソプラノやテノールの歌手たちが理解していたかというと、これが全く理解していない。その時、どれだけ指揮者の頭の中に素晴らしい設計図が出来上がっていても、「相手の立場に立って話さないと理解してもらえない」ということに気付いたんです。
作野:たとえ指揮者として優れた実力の持ち主でも、相手が理解できる形でコミュニケーションをとらなければ、プレーヤーの良さを引き出せないのですね。
村松:そうですね。あと僕が所属しているストラスフィールド交響楽団は、コミュニティー・オーケストラですから、上手な人とそうでない人の差が歴然としています。例えば、リハーサルの時に僕が大事なキーワードを投げかけても、全員の演奏が瞬時に上手くなるわけではありません。言葉の意味が分かった人、分からなかった人が混在していることを理解する。リハーサルにおいては個々の演奏者のレベルを瞬時に把握し、演奏者1人ひとりに合わせた一歩上のレベルの課題を与えていくことが大事だと思っています。
作野:相手に合わせるというのは、サッカーでも同じですね。プロの選手とサッカーをしていた時に気付いたのですが、プロは相手に合わせたパスを出すんです。強さ、速さ、角度を含め、アマチュアが受け止められるだけのパスしか出さないんですよ。
村松:僕も相手のレベルによってコミュニケーション方法は変えています。上手な人に対して多くは語らない一方、そうでない人に対してはしっかり言葉で伝えます。ただ、できないからと言って手取り足取り指導すると、相手が委縮してしまうので、そのさじ加減は難しいところです。
作野:指揮者と演奏者間のコミュニケーションは非常に大事ですが、仮に指揮者がいなくなった場合、オーケストラは音楽を再現できるのでしょうか?
村松:プロならできます。プロのオーケストラは職人集団ですから、基本的に彼らは指揮者が嫌いなんですよ(笑)。オーケストラを料理に例えるなら指揮者は料理人で、プロの演奏者は1人ひとりが良質な食材です。そのまま食べてもおいしいけれど、指揮者として呼ばれたからには、それらの食材がさらに美味しくなるよう料理することが求められるわけです。
作野:指揮者のリーダーシップについてお話頂けますか?ビジネスの世界ではトップダウン型の「支配型リーダーシップ」のほか、部下を支え、チームに奉仕する「サーバント・リーダーシップ」など、リーダーシップにもさまざまな種類があります。
村松:基本的に指揮者はトップダウンですね。どれだけ柔らかい言葉を使って指示しても、結局何かを決める時に僕は誰にも相談していませんから。ただトップダウンでもどれだけその権力を使うかは、指揮者によって分かれるところです。
作野:なるほど。指揮者は一般人にとってなかなかなじみのない職業なので、いろいろな疑問がわいてきますが、小澤征爾さんなど世界的に活躍されている日本人は多いですよね。
村松:小澤さんももちろん素晴らしいですが、オーストラリアにはかつてメルボルン交響楽団で長きにわたり指揮者として活躍された故・岩城宏之さんがいらっしゃいました。今、日本人の僕がオーストラリアで指揮を振ることができるのも、岩城さんをはじめとする先駆者たちが過去に偉大な功績を残してくれたからだと思っています。
地元に根差すことが成功への鍵
作野:日系社会の先駆者たちが道を切り開いてくれたからこそ、今の僕たちがあるんですね。最後になりますが、読者の中には今後キャリアを変えたいと思っている人たちもたくさんいると思いますが、そういった方たちへのアドバイスはありますか?
村松:ひと言で言えば、「いかに地元に早く根を張るか」でしょうか。かつて自分は留学生でしたが、現在は留学生を教える立場になりました。多くの日本人留学生を見てきましたが、居心地の良い日本人同士で固まって、オーストラリア人と盛んに交流しない人もたくさんいましたね。隣に素晴らしい音楽家がいるのにつながろうとしない。それを見ていて本当にもどかしかった。だから自分がオーストラリアに来て何がしたいのかを見極め、どんな形でもいいから地元の人たちとコミュニケーションを取ることが大切だと思います。
作野:確かにそうですね。オーストラリアの全人口は約2,500万人。そのうち、日本人の数は短期滞在者も含めて約9万8000人程度と言われています。成功の可能性を数値で見ても、日系社会の枠を超えて地元に根差すことは大事ですね。本日はお忙しい中貴重なお話をありがとうございました。
(2月24日、日豪プレス・オフィスで)