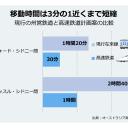シドニーを拠点に世界へ
飛躍する日本人建築家
doq®代表 作野善教 × 建築家 髙田浩一
日系のクロス・カルチャー·マーケティング会社doq®の創業者として数々のビジネス・シーンで活躍、現在は日豪プレスのチェア・パーソンも務める作野善教が、コミュニティーのキー・パーソンとビジネスをテーマに対談を行う本企画。今回は、シドニーを拠点に世界を舞台に活躍する日本人建築家、髙田浩一さんにご登場頂いた。
(監修:馬場一哉、撮影:クラークさと子)
PROFILE

たかだこういち
建築賞「Best Tall Building」で世界一の評価を得たシドニー中心部の「セントラル・パーク」を始め、近代的な様式と自然を融合させた革新的な設計スタイルで注目を集める「Koichi Takada Architects」創業者。ニューヨーク、ロンドンで建築を学んだ後シドニーに移住。2021年2月にはニューヨークの「Architizer A+Firm Awards」でミディアム・ファーム部門でベスト・オブ・ザ・イヤーに輝いた
PROFILE

さくのよしのり
doq®創業者・グループ·マネージング・ディレクター。数々の日系ブランドのマーケティングを手掛け、ビジネスを成長させてきた経験を持つ。2016年より3年連続NSW州エキスポート・アワード・ファイナリスト、19年シドニー・デザイン・アワード・シルバー賞、Mumbrellaトラベル・マーケティング・アワード・ファイナリスト、移民創業者を称える「エスニック・ビジネスアワード」史上2人目の日本人ファイナリスト。

作野:オーストラリアを拠点に世界的に活躍されていますが、まずはご経歴からお聞かせください。
髙田:僕は小さい頃から自分の考えや感情を表現することが大好きでした。東京都日野市出身なのですが、東京とは思えないほどの自然豊かな土地で、近所の川でザリガニやナマズを釣ったり、山でクワガタやカブトムシを捕ったりして、自然と共に成長しました。そんな少年時代を経た後、高校卒業時に日本を出ることにしました。 当時、「自分を表現する」という意味で、西洋アートの「爆発するような表現の仕方」に憧れを持っていました。自分自身を表現する場を模索していたのですが、日本社会の中では「感情を表現できる場」というのが非常に限られているように感じていたんです。 自然の世界では、川で溺れたら自力で這い上がらないといけないですし、山奥に入って道に迷っても自力で道を探さなくてはならないですし、「自分自身を信じないと生きていけない」という、緊張感が常にあります。 自分と向き合って自分を信じ、それによって自分が成長していくという環境を求めて、僕は当時憧れていたニューヨークに行くことを決意しました。ただ、父親からは芸術家として「食べていけるのか?」と反対されたこともあり、アートとエンジニアリングが融合した建築家になることを目指して18歳で渡米しました。
作野:建築のキャリアはアメリカでスタートされたのですか?
髙田:大学在学中から教授の下で働くと同時に、ソーホーにある事務所でも働きました。学校とは違い、実践なので緊張感がありました。
作野:世界中の人が集まるニューヨークという大都市で仕事をする中で、どういったことを学ばれましたか?
髙田:小さな事務所でしたが、建築という職業においてコミュニケーションをどのように確立していくかという面では、非常に多くのことを学びました。日々試行錯誤する中で、感覚的に「こうしたゾーンにはまっていけば自分を表現できる」といった感覚を養えたので、楽しかったです。
作野:僕もシカゴで働いていた時に経験しましたが、アメリカ人のコミュニケーションやプレゼンテーション能力は本当に高く、日本人としては学ぶものが多いですよね。
髙田:最初は「皆、なぜこんなに自己表現が上手なんだろう」と思っていました。英語というツールを通じていかに自分の意思を伝えていくか、といったことを学ぶのは非常に勉強になりました。英語での表現は日本語と比べるとかなり直接的ですから、他の人のプレゼンテーションを見ては、「こんなにストレートに表現していいのか!」と驚きながらも、自分の壁をどんどん破って可能性を広げていくという毎日を過ごしました。
作野:日本は島国ですし、暗黙の了解や見えないルールなど「空気を読む」ことや「話さない文化」があるんですよね。日本人は少し話しただけで、相手の意図が感覚的に分かる人が多いし、言わなくても分かってもらえるという期待値もある。同一民族の割合が全人口の約95%以上占めることが起因しているように思いますが、そのような国家は世界でも珍しいらしく、日本、韓国、北朝鮮、アイスランド、ポーランド、南太平洋諸島のポリネシア系の島国など数カ国しかないそうです。世界にはオーストラリアやアメリカなどをはじめとする多民族国家が多く、「ここまで言っていいのか?」というぐらいストレートに物事を表現しないと、バックグラウンドが違う人達とは分かり合えないですよね。その頂点のような存在が、人種のるつぼであるニューヨークだと思うのですが、髙田さんにとってニューヨークはどんな街だったのでしょうか?
髙田:世界中から自信がある人、優秀な人が集まっていますから、成績が良くても1回プロジェクトがうまくいかなくなると、落胆する度合いが非常に大きい場所でした。落ちては這い上がるということをコンスタントにやっていくという難しさといった意味では、浮き沈みがすごく激しい街だったなと思います。ニューヨークにはプレッシャーを常に背負って、自分を追い込んで試している人が多かったですね。
作野:ニューヨークにはどれくらい滞在されたんですか?
髙田:3年滞在しました。大学1、2年ではほとんど一般教養の授業しか受けられず、実際に建築の勉強ができたのは最後の1年だけなんです。教授たちには「早く建築の勉強をさせてくれ」としょっちゅう懇願していたので、しまいには「ミスター・アーキテクチャー」というあだ名で呼ばれるほどでした(笑)。それぐらい当時は「情熱の塊」でしたね。 ただ、留学前に憧れていた高層ビル群に段々と息苦しさを覚えるようになったんです。そんなある時、セントラル・パークで野球をしていた時に自然の中で成長した少年時代に戻ったような気がして、ふと「僕はなぜニューヨークで建築を勉強しているんだろう」と思ったんです。ビルが好きで来たのに、ビルが近すぎて嫌になってしまったんですよね。
憧れの摩天楼を離れロンドンへ
作野:ニューヨークの後はロンドンへ行かれたのですね?
髙田:ロンドンで3年間暮らしました。当時ロンドンには超高層ビルがほとんどなく、スケール的にも親近感が沸きました。フランスやドイツ、デンマークなど欧州のさまざまな文化背景を持つ人たちが集まっていたため、数カ国語を話せる人も多く、感覚的にも良い刺激をたくさん受けました。
作野:ロンドンでも建築を勉強されながら、お仕事もされたんですか?
髙田:勉強しながら実務もやりました。今振り返ると実務をやっていて吸収するものは多かったと思います。ただ、実務をやりすぎることを僕はお薦めしないです。現実を見すぎてしまうと、その分失望も大きいですからね。学校にいる間は、夢は見られるだけ見た方がいい。そのバランスを上手に取ることが大事ですね。
作野:ロンドンでの学生生活は、ニューヨーク時代とはまた違ったものだったんでしょうか?
髙田:習っていた内容もがらりと変わり、よりコンセプチュアルになりました。世界的に有名な建築家が海外からわざわざレクチャーに来てくれることもあり、建築を学ぶという意味で、僕はロンドンの方が刺激的でしたね。
作野:ヨーロッパでは建築の歴史が長く伝統もある一方で、これから新しく生まれる建築物もありますよね。歴史的建造物の多いヨーロッパにおいて新旧の建築物が融合することから生じる軋轢(あつれき)というのはあるのでしょうか?
髙田:ロンドンはまだ新しい建築物が入っていける土壌がありますけど、ヨーロッパには歴史的に重要な崩すことのできない建築物がたくさんありますから、新しく何かを建てるというのは非常に難しいんです。仮に新規の建築プロジェクトが計画されても、大抵は大御所の建築家がプロジェクトを手掛けますから、若手にチャンスは回ってこない。こうしたこともあって、僕は最終的にオーストラリアに来ました。オーストラリアは、アメリカ的な自由な表現の仕方ができるだけでなく、ロンドンのように古い町並みに新しいものを上手に取り入れ新旧うまくバランスを取っていて、ちょうどアメリカとイギリスの中間にあると感じたんです。
シドニーに詰まっていた自身の原点
作野:チャンスを求めてオーストラリアに来たのですね。
髙田:ロンドンを離れた後、いったん日本に戻って建築家として修行をしており、1998年にコンペで初めて来たのですが、空港に着いて空気を吸った時に、「すばらしい国だな」と感じたのを覚えています。コンペが終わった後日本に戻りましたが、現地の事務所から招待を受けました。自然と都市のバランスがうまく取れているところに魅力を感じていたので「やってみよう」と決意して、オーストラリアで働くことにしました。
作野:オーストラリアには、髙田さんの原点である自然との共存、伝統と新しいものの融合、チャンスといったものが全てあったのですね。
髙田:オーストラリアには、表現できる機会もたくさんありました。当時、「爆発的に表現する建築物」はオペラ・ハウスぐらいで、わりと大人しい建物が多かったんです。国のイメージにまでなってしまうオペラ・ハウスは造形的にも機能的にもすばらしいデザインだと思うのですが、そういった建築物がなぜそれ以降生まれなかったんだろうと思うと共にチャンスも多くあると感じました。 自分が一番大事にしている少年時代の「感覚」、自然と表現という自分の原点を失いたくない──。その思いと共に、自然をテーマにしたものや、自然を都市に戻していくコンセプトなどを追求し、それを求めて世界中を旅しながら、行きついた先がシドニーでした。
金融危機をチャンスと捉え独立を決意
作野:しばらく現地の大手事務所で働き、その後独立されたそうですね。
髙田:2008年に起きたリーマン・ショック(世界金融危機)を機に独立しました。多くの人が退職を与儀なくされる厳しい状況の中、これを最悪の時と捉えるのか、最善の時と捉えるのかで見方が変わってくると思うのですが、僕の中では「最善の時が来た」という感覚がありました。「自分を表現する」ことを考えた時に、事務所で働いていた10年間で学んだものは、「社会でうまくやっていくためのルール」だったんだということに気付いたからです。その時に「枠から外れて自分の限界を試すチャンスが来たんだ」と、独立を決心しました。
作野:「一建築家から、一経営者になった」わけですが、経営者として大事にしていること、努力していることはありますか?
髙田:会社のルールやシステムの構築が非常に大事で、それを社会の動きに合わせて常に改善、進化させていくことが必要ですが、僕が貢献できるのはこうしたルールやシステムの枠を超え、1人ひとりの感性や才能といった感覚的な部分を引き出すことだと思っています。僕は歴史やこれまで成功した人から学んだりして、自分の中にある壁をどんどん突き破っていくことを大事にしています。 また、今後は社会に貢献したいと考えています。サステナビリティ(持続可能性)が重要視される時代ですから、我々も自然からインスピレーションを受け、環境に優しいデザインやライフスタイルを提供していくということに主軸を置いています。

コロナ後は利益重視から環境重視へ
作野:コロナ禍は髙田さんにどういった影響を与えましたか?
髙田:コロナは金銭で解決できない問題なので、リーマン・ショックとはまた違った状況ですよね。建築面で言うと、「ウェルネス(健康)」の分野をより意識するようになった気がします。経済や利益を重視した建物作りだったのが、コロナ後は「3P(プロフィット=利益、ピープル=人、プラネット=地球環境)」を調和させ、健康や環境といった面を重視した建物を作ることがますます重要になると感じています。
作野:利益重視から環境重視へと、建築における優先順位が変わってきたと。
髙田:当社では2030年までにカーボン・ニュートラル(CO2排出実質ゼロの状態)を達成し、2050年にはカーボン・ポジティブ(CO2の吸収・削減量が排出量を上回る状態)でありたいと考えています。例えば電力は太陽光などを利用し、建物内で賄うといった取り組みですね。
作野:コロナ禍を経て職場環境や人間の行動が変化していくと思いますが、そうした変化を建築はどのように支えていくと思いますか?
髙田:在宅勤務がノーマルになりつつある現在、これまでの住宅スペースでは狭すぎて精神的にかなり厳しいと思うんですよ。ですから我々は高層マンションの設計をする時に、大きなバルコニーを設けるなど内側から外につながるデザインを意識しています。意識的に「ブリージング(一息つける)・スペース」を作らないと、健康にも良くないと思っています。自宅でも仕事ができることが証明された今、大きなオフィスは必要なくなってきています。今後はワーキング(職場)よりリビング(住居)中心で、リビングの中にワーキングを取り入れる。そのバランスが重要になってきますね。
作野:未来を見据えて設計をするわけですね。
髙田:建築家というのは、常に何十年先という未来を想像しながら設計をしています。今後はA I(人工知能)がどんどん発達してきますから、数十年後はロボットが普通に働いている時代が来るかもしれません。これからは「アーバン・ファーミング(都市空間の隙間を利用した農業)」も盛んになり、AIを活用することで太陽光に頼らなくてもおいしいトマトができるようになるでしょう。そういった人工的な部分に頼らないとカーボン・ニュートラルの達成も難しいと思います。
作野:AIの台頭は建築家にも影響を与えると思いますか?
髙田:AIが台頭する中で、ますます人間らしさが求められると感じています。組織として大きくなればなるほど、実際に人と対面する、目と目を見て感覚的にコミュニケーションを取るといった原点に立ち戻ることが大切ですね。幸い感覚、感情、表現の仕方などといった部分は、AIにはまだできません。AIが進化し、グローバリゼーションも加速する中で、我々建築家は、各都市にあるその土地固有の文化的な建物を守り、アイデンティティーとして後世に残していかないといけません。我々の世代はリーマン・ショックやコロナなど数々の危機を乗り越えてきましたが、危機が起きても自分自身を見失わず、次世代のために「人間的な部分を残していく」ことが使命であると痛感しています。
海外在住の日本人だからこそできる表現
作野:日本人であることを仕事で意識することはありますか?
髙田:普段、意識することは少ないですが、自然や四季の移り変わりなどといった感性の部分や表現方法におけるプロセスといった部分は日本的であると思いますね。日本人であるということは自分のアイデンティティーそのものですから、その原点を忘れずにいることが自分の強みにもなっていると信じています。
作野:日本でも髙田さんの建築プロジェクトが始まっていると伺いました。
髙田:日本政府は2050年までにカーボン・ニュートラルの実現を目指すと宣言していますが、僕はこれまで培ったノウハウを生かし、10 年以内にカーボン・ニュートラルを達成する勢いでプロジェクトを進めたいと思っています。技術的に日本はそれを達成できる国です。あとは概念的な部分ですね。これまでオーストラリアで都市と自然が共生しあう建物を作ってきましたが、今度は日本でも環境に優しく、ウェルネスを重視したコンセプトのデザインをどんどん提供していきたいです。
作野:オーストラリアで培ったものを日本に逆輸入する、日本人として海外に住んでいるからこそできる貢献ですね。
髙田:海外にいるからこそ生まれるものというのはあります。側にいると近すぎて、新しい発想が生まれにくいですから。日本のプロジェクトも同じで、国内からではなく海外から日本を見るからこそ表現できるものがあると思うので、僕はそこに注力していきたいですね。
作野:最後に新たな挑戦を行っている人も多い読者の方に向けて何かメッセージを頂けますか?
髙田:チャレンジ精神と好奇心があれば何でも乗り越えられるはずです。好奇心というのは情熱のことで困難にぶち当たっても継続できる燃料です。それがないことには始まりません。あとは、夢を見ることだけは忘れないで欲しいです。チャレンジ精神を持って自分を見失わずにやっていけば、夢は必ず叶います。