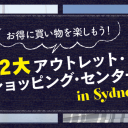オーストラリア各地で話題の日本映画を一挙上映!
第23回日本映画祭
ジャパン・ファウンデーションが主催する毎年恒例の「日本映画祭(The Japanese Film Festival 2019)」が、キャンベラ、ブリスベン、パースでの開催を終え、11月14日から24日にかけてシドニーで開催される。本特集では、お薦め作品の紹介、及び注目作『ブルーアワーにぶっ飛ばす』の箱田優子監督と、『岬の兄妹』の片山慎三監督のインタビューをお届けする。人気の日本映画を英語の字幕付きで観に出掛けよう。
特別インタビュー
箱田優子監督、片山慎三監督
日本映画祭で上映される話題作『ブルーアワーにぶっ飛ばす』の箱田優子監督と、『岬の兄妹』の片山慎三監督が、スペシャル・ゲストとして来豪するに当たり、話を伺った。箱田監督は11月16日、片山監督は17日にシドニーでの映画上映後にQ&Aセッションを行う。
※『ブルーアワーにぶっ飛ばす』、『岬の兄妹』の作品紹介はこちらから。


箱田優子
CM界で活躍。新進気鋭の若手映像作家を生み出すプロジェクト「TSUTAYA CREATORS’ PROGRAM」において2016年審査員特別賞に輝いたことで、同プロジェクトに企画として提出していた本作の映画化が決定。本作は、第22回上海国際映画祭アジア新人部門で最優秀監督賞&優秀作品賞に輝くなど国内外で高い評価を得ている。
――本作の主人公はCMディレクターで、箱田監督もCM界で活躍されてきました。監督ご自身の経験がこの主人公を描く上で大きく影響しているのではないでしょうか。
自伝のような書き方をしていますが、話の根本は「どうしようもなく過ぎ行く時間でどう生きるか」というところにあります。肌触りとして、現実と地続きの生々しさを感じて欲しかったのもあり、1つの方法として己で取材、体験したことをさらした上で、主演の夏帆さんには自己解放してもらいました。フィクションとドキュメンタリーが入り混じる構造にエンターテインメントを感じて頂けたらと、各所に気を配りました。
――主演の夏帆さんは今回の役にかなり強い思い入れがあるとおっしゃっていて、箱田監督と密になって撮影に取り組んでいた様子が伺えました。
役者とこんなに距離を詰めて作ったのは初めてです。夏帆さんは繊細さと不器用さがとても魅力で、現場でも細かいニュアンスの温度調整をお互い取り合いながらも、演技を超えた何かを期待していたので、随所に追い込むネタを仕込んでいました。理性と本音の間で揺れ動きながら、どうしようもない感情を吐露する部分が垣間見えた時、彼女の役者としての決意を感じられて、うれしかったです。
――本作は第22回上海国際映画祭を始め海外でも好評を得ています。このような反応をどのように受け止めていますか?
国は違えど、感動するポイントは同じところにあるように感じています。日本の東京から茨城と小さな範囲での1日半の話ですが、時間の話と捉えた時に、こんな広がり方をするのかとうれしく思っています。日本人はシャイなので劇場でもリアクションが見えにくいところがあるのですが、海外のお客さんは反応がダイレクトなので、笑うところは声を出して笑うなど、感情表現が豊かで気持ちが良いです。疑問、質問、違和感を含め、皆さんきちんと言葉にしてくれるので、会話をするのがとても楽しいです。本作において、ジェンダーの話が多く上がる日本と違い、海外ではその点に関して一切聞かれないのが驚きでした。反応から見える社会のありさまは勉強になりますね。
――そんな本作が今回、オーストラリアで上映されますね。
オーストラリアはプライベートを含めて初めて行く場所なので、どんな国なのか、どんなお客さんに会えるのか楽しみです。香港国際映画祭のお客さんの中に、オーストラリアから旅行で来ていた女の子2人組がいて、「(主人公たちは)私たちみたいだった!」とビッグ・スマイルで言ってくれたことがとても心に残っているので、彼女たちの育った国に行けることがとてもうれしいです。もちろん、映画の感想もたくさん聞きたいです。あとは、オーストラリア名物を食べて帰りたいので、教えて頂きたいです!
――今後、映画監督として挑戦したいことはありますか。
本作で映画がもっと好きになりました。観客としての自分を忘れず、自分が観たいと思える映画を今後も作っていきたいと思っています。
――箱田監督の作品を心待ちにしているファンにメッセージをお願いします。
国は違えど、ブルー・アワーの時間はどこにでも訪れるものです。過ぎ行く時間の中、あの青い時間に、皆さんが今何を思うのか、ぜひ聞いてみたいです。


片山慎三
カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した韓国のポン・ジュノ監督や、『苦役列車』などの山下敦弘監督の下で、助監督として映画製作の経験を積む。長編映画監督デビューを果たした本作は、若手映像クリエイターの発掘を目的にしたSKIPシティ国際Dシネマ映画祭で優秀作品賞ならびに観客賞を受賞し、全国公開に漕ぎ付けた。映画業界内外からの支持を得て、自主製作映画としては異例のヒットを記録した。
――長編映画を初めて手掛けてみて、大変だったことは何でしょうか。特に今回、監督のみならず、脚本、編集も担当なさいましたね。
初めての長編映画で、できるだけ制約なく撮影したかったので自主制作という形を選びました。脚本や編集、車の運転まで、普段やらない仕事をしてみると、いろいろな発見があって勉強になりました。撮影中は体力的には大変でしたが、楽しかったのであまり苦労は感じなかったです。そんな中一番大変だったのはやっぱりお金ですかね。予算も自分で出したので貯金の減り具合が尋常じゃなかったですね。
――ポン・ジュノ監督、山下敦弘監督というアジア映画界をけん引する監督方とお仕事をされてきた経験が、本作の製作で生かされていると感じたことはありましたか。
ポン監督と山下監督は2人ともとてもすばらしい監督ですが、スタイルが全然違います。ポン監督は絵コンテまで書いて、全て計算したものを現場でそのコンテ通りに撮影していきます。山下監督は絵コンテを決めず、俳優の芝居に合わせて現場で撮影方法を決めていくので、よりライブ感がある演出方法を取ります。今回、自分が監督するに当たり、全てのシーンで絵コンテがあったわけではないので、どちらかというと山下監督の演出方法に近かった気がします。そんな中でも数カットはあらかじめどう取るか決めて撮影したシーンもあるので、そのシーンに関してはポン監督の影響があると思います。3人の男が1カットで入れ替わったりするようなカットだったり、ステディカムで人物に合わせて動いていくような砂浜のカットがそれに当たります。どのように演出するか答えがないので、模索しながら進んでいく形でした。
――本作のストーリーは、リストラされた兄が妹に売春をあっせんして生計を立てていくという衝撃的なものですが、どのように思い付いたのでしょうか。
自分の親戚に障害を持つ方がいて、「親がいなくなったらどうなってしまうんだろう?」という疑問を起点に発想しました。
――人間や地方都市の暗部に切り込んだ作品でありながら、喜劇的な要素もありました。この絶妙なバランスはどのように模索していったのですか?
キャストの持つ明るさが全面的に出ていると思います。特に妹の真理子役の和田光沙さんはコメディーのセンスがあり、彼女とのオーディションの時に作品の方向性が決まったと思ってます。笑っちゃいけないのに笑ってしまうような。そんなシーンを狙って演出しました。
――本作は業界内外から絶賛され、実際に日本での公開館数が増えるなど大きな反響がありました。
撮影時にはこの作品が広く受け止められるとは想定していなかったので、すごく喜ばしく思います。ありがたいです。同時に、架空の出来事を描いた作品がリアリティーを持って受け止められている今の時代性についても考えさせられます。つまり、この映画の内容が絵空事ではなく現実味を帯びているという意味で考えさせられました。
――オーストラリアの日本映画祭で本作が上映されることについて、どのようなお気持ちですか?
オーストラリアの方がどのような反応をされるのか、非常に楽しみです。この映画は1年間四季を通じてゆっくりと撮影しました。予算は少ないですが、ぜいたくに時間を掛けたので皆さんの心の奥深くまで届くことを願っています。あとは、初めてのオーストラリアなので、時間があれば日本にはないような雄大な自然に触れられたらと思っています。