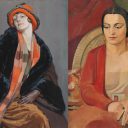年間約1万人近くが来豪すると言われている、日本人のワーキング・ホリデー(以下、WH)・メーカー。では、日本人WHメーカーの最新の実態はどのようなものなのか。セカンド・ビザを含めたビザ発給数の状況、男女別の年齢ごとの割合、来豪前の職業、出身都道府県の項目に、総合情報センター「Travel & Travel」(トラトラ)スタッフの現場の声を交え、気になるその実態をさまざまな角度から調査した。(調査データ提供=日本ワーキング・ホリデー協会、構成=山内亮治)
WHビザ発給状況
出典:『Working Holiday Maker visa program report (31 December 2017)』
(オーストラリア政府移民省)
※データ集計対象期間:2017年7月1日~12月31日
ファースト及びセカンド・ビザ発給数の推移(過去5年同時期比較)

日本人のファーストWHビザは2015/16年度を境に4,000人台で推移。2016/17年度に一時的に落ち込んだが、昨年度(注:以下を含め6カ月分)は回復傾向を見せている。セカンド・ビザは1,000人前後で推移しているが、昨年度は過去4年に比べ855人と大きく落ち込んだ。
ちなみに、昨年度の日本のファーストWHビザ発給数4,233件は、協定20の国・地域で7番目。最多はイギリスの1万5,949件で、ドイツ(1万3,505件)、フランス(1万1,514件)、韓国(8,940件)、台湾(7,163件)、イタリア(4,701件)と続く。
最新動向調査
※データ集計対象期間:2017年1月1日~12月31日
年齢別男女申請者の割合

一般的に大学在学中に当たる22歳までは男性の割合が女性と同率または上回っているのに対し、多くの人が社会人1年目になる年齢(23歳)以降は女性の割合が逆転。日本の職場環境において男性が離職しづらい状況、女性が将来的なキャリア形成に積極的であることや語学習得に意欲的であることが読み取れる。
出身都道府県・地域別割合

WHビザ申請者の出身都道府県は、五大都市圏(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)のうち1都1府2県(東京都・愛知県・大阪府・福岡県)に集中している。地域別割合では、関東・中部・近畿で全体の4分の3以上を占めた。大都市圏の人口集中と申請者の割合の高さが密接な関係にあることが分かる。
みんなの「ワーホリ・ダイアリー」
出演者の出身都道府県ランキング・トップ5

2018年8月号時点で55回となる本紙連載「みんなの『ワーホリ・ダイアリー』」での出演者の出身都道府県を調査。結果は上記の通りとなった。
来豪前の職業(上位5職種)

「会社員」の回答が全体の4分の1以上を占めていることから、WHが新たなキャリア形成の場として捉えられている可能性が高い。次いで多い学生は語学学習や職業選択前の重要な機会として同制度を利用していることが考えられる。また、看護師、美容師といった専門職も全体の上位に入った。
インタビュー
トラトラで聞いたWHメーカーの動向
調査結果の数値とは別に、実際に日本人WHメーカーに接しサービスを提供している立場の人は、現在の状況についてどのようなことを感じ取っているのか。その疑問に答えるべく、シドニーの総合情報センター「トラトラ」のスタッフ・藤澤大智さんにインタビュー。来豪者数の変化、滞在目的のトレンド、セカンド・ビザ取得に関する状況など話を伺った。

――日本人WHメーカー数の変化をどのように実感していますか。
現在は、1~2年前に比べると数が回復してきていると感じていますが、もう少し長いスパンだと減っている印象です。というのも、毎週土曜日に空港で来豪者の出迎えをするのですが、トラトラで勤務を開始した4年前は多い時だと1日で20~30人、しかし、現在は10人もいれば多いくらいだからです。
シドニー以外の他都市に行く人の割合が増えた可能性もありますが、それでも少ないと感じています。
――減っている要因をどのように分析されていますか。
海外志向の若い人そのものが減ってしまったのかもしれません。一方で、旅行者の数が落ちているという実感はありません。オーストラリアは旅行先として高い人気を誇っていますが、いざ住むということになると話は別のようです。
――若い人の中でマインドの変化があるのですね。
ただ、少し話は変わるようですが、WHで来豪した人の中には1年ですぐ帰国するのではなく長く滞在しようとする傾向が高いように思います。滞在を延長する明確な理由は分かりませんが、WH後に学生ビザに切り替えて滞在を延長する人は多くなっています。
――来豪者の男女比については、何か特徴を感じますか。
圧倒的ではないですが、女性が多いと感じます。例えば日本の外国語大学などで、女性が多いのと同じ状況かと思います。
――来豪目的には何かトレンドが見られますか。
WHで来豪する目的として英語力の向上を挙げる人がやはり多いのですが、その中でも多くの人がIELTSやTOEICなどの英語力の証明、J-SHINEといった資格の取得を重視しています。
より長期の滞在を希望する人は、現地で職業経験を積むことを見据え調理師学校やビジネス・スクールなどに進学、学生ビザへの切り替えを行っています。実際に調理師などの学校に進学したかまでは状況をつかめていませんが、学校に関する問い合わせは多くあります。
また、農業系の大学出身で、オーストラリアの農業について勉強するという目的で来豪した人もいました。WHメーカーの中には、この国ならではの背景や特徴をよく考慮して来豪する人もいます。
――セカンド・ビザを取得する人の割合の変化はどのように感じていますか。
来豪者数の状況と同じく、セカンド・ビザを取得する人の割合も以前に比べ減ってきているように思います。ビザ申請の基準が厳しくなったことや審査期間が長くなっていることが要因として挙げられます。こうしたビザ取得における状況が厳しくなっていることがWHメーカーの間で共有され、セカンド・ビザの申請が敬遠されているのかもしれません。
また、こうした状況の変化だけでなく、ファームの良し悪しなどのリスクを考え、滞在を伸ばしたいという人は求人の多いシドニーを中心に働き資金を貯め、学生ビザに切り替えています。学生ビザに切り替えを行う人の増加は、こうしたセカンド・ビザを取り巻く状況とも関連しています。
――WHでの来豪者の状況に対し、貴社のサービスは細分化など変化を求められていますか。
サービスの大きな枠組みは変わりませんが、少しずつ来豪者のニーズに応じて提供するサービス内容を細かくアレンジしています。
以前は、ビザの取得から学校選び、ホームステイまで日本で事前準備をしっかりして来豪する人がほとんどでした。現在は、学校を実際に見学して決めたい、学校に通うつもりだったが早く働きたいなど個人のニーズが多様化してきていますから、空港での出迎えとホームステイの調整といった来豪直後の最低限のサポートをした上で、来豪後にカウンセリングを行い柔軟性の高い対応ができるよう努めています。本来WHは交換留学などと異なり、個人が融通を利かせて滞在できる制度なので、それに合ったサービスを今後更に用意していきたいと考えています。
藤澤大智(ふじさわだいち)
2013年1月にWH制度を利用し来豪。WHではセカンド・ビザを取得し2年間滞在。その後、2年間の学生ビザでの滞在を経て、永住権取得。14年に総合情報センター「Travel & Travel」(トラトラ)入社。同社では主にオーストラリア国内を中心とした旅行の手配や航空券、ホテル手配を担当。また、現地WHメーカーや留学生の生活サポートも行っている