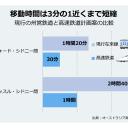ルポ:シリーズ・原発問題を考える④
被災者と、“非”被災者の境界
世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えつつ、自国内には原子力発電所を持たない国オーストラリア。被ばく国であるにもかかわらず、狭い国土に世界第3位の原発数を誇る原発大国・日本。原発を巡る両国のねじれた構造を、オーストラリアに根を張る日系媒体が取り上げないのはそれこそいびつだ。新連載「原発問題を考える」では、原発を取り巻くさまざまな状況を記者の視点からまとめていく。取材・文・写真=馬場一哉(編集部)
福島大学の前に置かれた放射線量をはかるモニタリング・ポスト。この数値をどの程度信頼していいかということもまた議論の的になっている(提供:平野由紀子)
東日本大震災から今月で丸2年が経とうとしている。2年前のその日、当時作っていた雑誌の校了日が間近に迫っていたことから、記者はオフィスへの往復2時間の移動時間を惜しみ、徹夜作業から継続する形で東京の自宅で原稿を書いていた。東京の死者数は7人と、震災の被害としては軽微だったと言えるが、そんなことは当時知る由もない。大きな揺れに「ついに東海沖地震が来たか」と覚悟の心を決め、「生きているうちに必ず起きると言われた大地震を生き延びることができれば将来の地震におびえる日々が終わる。生き残るために、今はまず落ち着くことが大事だ」と不思議なほど冷静に考えながら大きく前後に揺れている本棚を押さえた。
自宅周辺の揺れは震度5強と、恐れていたほどの大きさではなかったが、それでも味わったことのない大きな揺れに家族の安否が気になり、連絡を取ろうと試みるも電話は混雑のため不通。スカイプを立ち上げ、両親と妹、妻に安否確認のメッセージを送り、オフィスに無事作業を継続できている旨をメールする。状況は全く分からず、それ以外にできることは何もなかった。
その後、テレビで被害の状況を確認しながら原稿を書き続けた。テレビでは都内千代田区九段下にある九段会館の天井が崩落し、何名かが下敷きになったことが報じられていた。
九段会館は、友人が結婚式を挙げた会場であり、記者もそこで彼らの門出を祝ったことを思い出すと同時に、実家、妹夫婦、妻の実家、どの家からも近いエリアでの事故に「まさか巻き込まれてはいないだろうな」とぞっとする想像をし、全身が粟立った。その後、家族とはインターネット経由で連絡が取れ無事を確認したものの、友人が一生の思い出を得た場所は一瞬にして、記憶から消し去ることのできない負の場所となってしまった。
九段会館では女性2人が天井の下敷きになり死亡した。先ほど記者も書いたが、被害者の人数が少ないと「軽微」という表現になる。しかし、亡くなった本人、その周りの人々にとっては、1つしかない大事な命を失うという堪え難い悲しみを伴うものであり、これほど重いものは世の中にはない。揺れにおののき、その後落ちてくる天井に押しつぶされ、どれほど苦しかっただろうか。例え、直接知らない人であっても、本人の苦しみ、そして残された家族がそれを想像した時の苦悩を考えると胸が苦しくなる。
巡り合わせが悪ければ、被害に遭うのは自分にとっての大切な人であったり、あるいは自分だったりもするのだ。大きな災害や事故で大勢の人々が亡くなっている中、今生きている自分たちはたまたま運がいいだけに過ぎない。それを実感として感じることはいざという時のための心備えとして有要だ。
また、他人の苦しみや辛さを自分のもののように想像できる心を持っていることも大事だろう。いざという時に大事な人々を助ける行動ができるか否か、それは普段からのそうした心の持ちように寄るところも大きいにちがいない。
震災直後、周囲の動きはさまざまだった。知り合いのジャーナリストやカメラマンの多くは線量計を手に被災地に飛び、取材・報道活動を重ねた。編集者たちは「災害時のSNS活用術」「来る東海沖地震に備える」「放射能汚染とは」など、さまざまなタイトルをひねり出していた。そんな中、当時の記者は金融や不動産、医療などの雑誌やムックを企画・製作する職務に就いており、メディアの一員でありながら報道とは一線を画した現場にいた。未曾有の大事態が起きたにもかかわらず、誰をも助ける立場を取ることができぬまま1年8カ月が過ぎ、やっと取ることができたアクションは当連載を始めるということだった。 震災から2年の節目を迎えている今、忘れやすい気質の日本人にとって、震災はどれくらい過去の出来事として脳内処理されてしまっているのだろうか。2年経った今でも、依然、行方不明者は膨大で、被災者たちは失ったものの大きさに苦しめられている。
ある人から聞いた話にこのようなものがあった。その人は震災後しばらくしてから、趣味の釣りを福島県相馬市の沖合で開始した。ひとしきり釣果も上がり、採れた魚をさばいたところ、魚の中から人間の爪や入れ歯、指輪などが出てきたのだという。津波で流された人間のものであろう。津波による被害は3.11後もあらゆる場面で人々を苦しめ続けている。
そして、3.11の中でも最も負の遺産となった原発事故の被害が目に見える形となって無視できない大きさになるのはこれからだ。風化どころか、誰もが本気で向き合わねばならぬ日が間違いなくこれから来る。私たちはそれを覚悟しておかなければならない。節目に際し、そのことを自身にも言い聞かせつつ強調しておきたい。
被災者と、その周囲の軋轢
さて、話を前回の続きに戻そう。年末年始に日本に帰国し、まず祖母の住む青森県八戸市を訪れた記者は、帰京時、東北自動車道を途中で降り、福島県伊達市にある健康ランドで仮眠を取った。狭い日本とはいえ、青森から東京への道のりは長い。ましてや、大寒波が来ている猛吹雪の中でのドライブである。八戸を出発したのが夕方ということもあり、途中で1度しっかり休む必要があると判断したわけだ。
到着したのは午前1時過ぎだった。翌朝は遅くとも6時前にはそこを出なければならなかったが、もともと3時間も寝られれば十分と考えていた記者は温泉が湧き出る大浴場にゆったりと浸かった。ここは高濃度の放射線が検出され、非難を余儀なくされた福島県飯舘村から約30キロの位置だ。漠然と、「今、自分が浸かっているこの温泉の放射線量はどうなのか」などと考え、「ああ、これが傍観者の自然な反応なのだろうな」と1人苦笑した。そうしていると、1人の中年男性が記者に声をかけてきた。
「仕事かい?」
その男性は福島県相馬市で建設会社を営んでいる社長さん(Tさん)であった。「プライベートだ」と答えつつ会話の流れ上、編集記者であることを伝えると「そうだと思った」と言う。不思議に思っているとTさんは言う。
「深夜にここで風呂入って仮眠を取るなんて、最近ではマスコミか警察くらいしかいないからね」 たま
たまではあったが、せっかくの機会なので話を伺ってみることにした。「政府もマスコミも悪いものはすべて福島県に押し付けていて卑怯だよ。放射性物質は日本全国かなりのエリアに飛散しているけど、『大したことではない』ように扱い、すべてを福島の県境内で納めようとしている。私は相馬市の出身だけど被害はあまりなかったし原発からも離れていて非難区域にも指定されていない。沿岸の市街地が壊滅した隣の南相馬市も数年前に3つの区が合併した大きな市だから被害に遭ってない人はもちろんたくさんいる。けれど、すべてがひとくくりにされてしまっているんだ。マスコミがお涙頂戴のストーリーを流し、同情されるほど、私のような福島県の“非”被災者は風評被害で動きづらくなってしまうんだ」
Tさんは続ける。
「家が倒壊し、非難生活をしている人や仕事を失った農家の人々には政府や東電から補助金が出ていて、聞くところによると家族1人あたり10万円ほどだという。家族5人だったら50万円。そのほかにもいろいろな名目で義援金が入金されるなどということもあり、結構羽振りのいい人が少なくないんだ。また、被害の度合いの違いでお金をもらっている家ともらっていない家が隣り合っていたりすることもあって、そこで生じている軋轢も尋常じゃない」
湯につかりながら長時間話していたこともあり「茹でダコになってはかなわん」と言いながらTさんは浴槽の淵に腰掛け、話を続ける。
「働かずにお金が入ってくる状態が続くと勤労意欲は減衰する。一部の人は今後、長きに渡って、追加の保障を政府に要求する“たかり”のようになるかもしれない。このような状態が続くと、遅かれ早かれ福島の産業は自然消滅してしまうのではないかと思っているよ、福島人の手によってね」
ひとしきり話し終えるとTさんは「こういう出会いが風呂のいいところだね。話を聞いてくれてありがとう」と言って笑顔で立ち去った。その背中には福島県の“非”被災者としての苦悩が刻まれていた。
(第5回に続く)