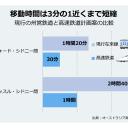ルポ:シリーズ・原発問題を考える⑦
原発ゼロの国オーストラリアが支える原発産業
世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えつつ、自国内には原子力発電所を持たない国オーストラリア。被ばく国であるにもかかわらず、狭い国土に世界第3位の原発数を誇る原発大国・日本。原発を巡る両国のねじれた構造を、オーストラリアに根を張る日系媒体が取り上げないのはそれこそいびつだ。シリーズ「原発問題を考える」では、原発を取り巻くさまざまな状況を記者の視点からまとめていく。
取材・文=馬場一哉(編集部)

福島第1原発で使われていたウラン燃料の一部が採掘されたと言われるオリンピック・ダム鉱山
この原稿を書き始めた5月28日、同24日に発覚した茨城県東海村の加速器実験施設「J-PARC」の放射能漏れ事故、そして福井県敦賀市の高速増殖炉「もんじゅ」の点検漏れなど不祥事が相次いだ日本原子力研究開発機構について、抜本的な組織改革の検討が報じられた。「J-PARC」における事故では実験施設内の6人が被曝(最大55人の被曝の可能性)、さらに施設内に備え付けられた換気扇によって放射性物質は外部にも飛散した。福島第1原発の事故から2年2カ月。組織改革の長として指揮を取ることになった下村博文文科相は「安全意識の低さや管理体制の不備が招いた」としているが、福島第1原発事故を経た上での原子力関連事故の発生に「安全管理への意識の低さ」が救いようのないレベルなのではないかと驚きを禁じえない。福島第1原発の事故が教訓とならず、想定外中の想定外として意識の枠の外にくくられており、意識水準は相変わらず事故前のままなのではないかと勘ぐってしまう。
この事故への驚きと同時に、実は「被曝」という文字が目に飛び込んでくることに慣れている自分にもまた驚いた。放射性物質の飛散や被曝は、今や日常の中で「情報」としては容易に受け入れてしまい得るものになった。このようなことに気付き、大げさではなく世界は変わったのだと嘆息せざるを得ない。
変わった世界の中で、私たちは飛散してしまっている放射性物質とどう付き合うかという問題を突きつけられている。原発連載を書き進めるにあたってこれまでさまざまなことを調べてきた。しかし、今さらながら記者には分からないことが多すぎる。リサーチが足りないのかもしれない。あるいは問題を複雑に考えすぎているのかもしれない。だが、敢えて言うと例えばこのような一番大事なことが分からない。
福島第1原発のメルトダウンに端を発した放射性物質の飛散状況は今現在どうなっているのか。さまざまな専門化が予測した飛散予想図などを見ても、実際、現状がどうなのかは分かりようがない。それら予想図が示していたのは空気中に飛散しながら密度は薄まるものの、気流にのって放射性物質は世界中をめぐるというものであり、遅かれ早かれ、それはここオーストラリア沿岸にも到達することが予想されていた。しかし、それがいつなのかは分からないし、結局のところ、地道に線量を計測するしか手段はない。これを機に記者もまた計測器を持ってシドニー市内を回ってみることを始めてみようかと考えている。
もちろん、予測には希望的観測、あるいは逆に悲観的観測などのバイアスがかかるため、何をどう信じればよいかは見る人それぞれによって異なってくる。しかし、実際問題、起きている現実はただ1つである。日本という国はあまりに小さく、そして極めて重大な事故の「現場」から世界規模で見るとあまりに近い。そんな中、例えば「被災地で農業が再開された」などのニュースを目にすると、現地の人々の喜ぶ姿を嬉しく眺めると同時に心の片隅で「大丈夫なのか」と考えてしまう自分もいる。これがいわゆる風評被害を生み出す元となるものなのだと思いながら。
もちろん、だからこそ各自治体はモニタリング・ポストを設置し、線量の定点観測を行っているわけだが、一部でその数値は信用できないという声もまた上がっている。調べれば調べるほど、安全の基準や根拠は曖昧で分からなくなってくる。安全と言われる被曝線量基準値に関しても、その基準が果たして妥当なものなのか。判断は専門家の意見に委ねるしかなく、それも人によって言うことがまちまちだ。
現在、非難生活を余儀なくされている人々の中には、いつかふるさとに戻ることを信じて生活している人がたくさんいることだろう。そのためには、例えば「除染」を推し進めていくことなどが前提にあるわけだが、そもそも「除染」が根本的解決になるのかと考えてしまうこともある。危険な物質を別の場所に移動させているだけに過ぎない「除染」は記者にとって、あまりに原始的に思えてならない。人類にとって、講じられる手段がこの原始的な手段しかないのであれば、それはやはり手に余るものとして扱うべきものではなかったのだと、今さらながら思ってしまうのだ。
こういった状況を受け、国や自治体を信用できないという声もよく聞くが、少なくとも記者は事態を穏便にすませるための曖昧さこそ散見されるものの(それはまた日本人のパーソナリティーのようなものでもある)、彼らが敢えて国民をだますなどといったことは、さすがにないのではないかと思う。仮にそれがまかり通るのであれば、日本という国は根っこから腐っていることになる。
プロの書き手として、紙面で論じるには少々乱暴に過ぎることを書いていることは重々承知だ。記者の書いていることが現状を知らないばかげた意見なのであれば、ぜひ指摘していただきたいと思っている。間違った認識はいつ、どんな時でも可及的速やかに改めねばならない。今感じているこの漠然とした不安が解消された上で、国が主導している収束への道筋を安心して信じ、それを情報として提供できる時が来ることを願っている。
国内外に犠牲を強いる豪のウラン採掘
以下、前号に引き続き豪国内のウラン鉱山の問題に関して切り込んでいく。
2011年10月、福島第1原発5基以上(全6基)の原子炉でオーストラリア産ウランが使われていた事実を、オーストラリア連邦政府の外務省の役人が認めた。世界一のウラン埋蔵量を誇り、生産国として世界第3位を誇るオーストラリアは、原発を保有する世界各国にウランを輸出しており、その中にはアメリカやフランスなど核兵器保有国も含まれている。原発ゼロ、核兵器保有に対して反対の立場を取っている一見クリーンな国、オーストラリアはその実、世界の原発産業を陰で支える原子力産業の中核を担う国でもまたあるのだ。そんな中、今大きな議論の的となっているのがインドへのウラン輸出解禁である。インドは核拡散防止条約に加盟しておらず、核の利用に関して、民生用、軍事用のボーダー・ラインが極めて曖昧だ。輸出したウランが核兵器に利用されれば、それは世界の安全を確実に脅かすことになる。オーストラリアの経済繁栄の一端には、なぜかあまり表立って目に触れる機会の少ないこのようなグレー・ゾーンがあるのだ。
国は今後、さらにウランの輸出拡大、採掘拡大の動きを加速させようとしているという。極めて重大な事故が起こり、世界中の人々の監視の目が強まる中、長い目で見ると原発産業はおそらく衰退していかざるを得ないと思う。だが、原発産業は多くの国でそれぞれの国の経済にとって重要なファクターとして組み込まれてしまっており、経済的な面だけから見てもその構造を見直すにはどうしても時間がかかる。世界の原発産業自体が衰退する前に、儲けられるだけ儲けよう、国はそう考えているのではないかと邪推してしまう。
国内のウラン産業が拡大すればするほど、鉱山があるエリアに住む先住民アボリジニは、放射能に汚染された汚染水などによる被曝に苦しめられることになる。オーストラリアのウラン採掘は、国内外に多大な犠牲を強いながら、なお推進されようとしているのである。
※ちょうど筆を置こうとした瞬間、とんでもないニュースが飛び込んできた。29日朝の産経新聞によると、北朝鮮の朝鮮人民軍が対韓国開戦直前、日本全国にある原子力発電所施設に特殊工作員計約600人を送り込み、米軍施設と同時に自爆テロを起こす計画を策定していた。「甚大な損害を与えられ、核兵器を使う必要がなくなる」との思惑からだという。原発の安全管理のあり方がますます問われていると言えるだろう。