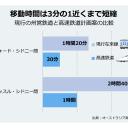ルポ:シリーズ・原発問題を考える⑧
見えない戦争
──原発事故後の世界を描いた問題作『希望の国』より考察
世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えつつ、自国内には原子力発電所を持たない国オーストラリア。被ばく国であるにもかかわらず、狭い国土に世界第3位の原発数を誇る原発大国・日本。原発を巡る両国のねじれた構造を、オーストラリアに根を張る日系媒体が取り上げないのはそれこそいびつだ。ルポ・シリーズ「原発問題を考える」では、原発を取り巻くさまざまな状況を記者の視点からまとめていく。
取材・文・写真=馬場一哉(編集部)
原発事故後、記者の周囲にいたジャーナリストらの多くはすぐさま被災地へと飛んだ。そして津波の被害や被災者を取り巻く状況、各地の放射線量など、さまざまな情報を貪欲に取材しては執筆していた。さまざまなところで彼らの名を目にし、被災地の悲惨な現状を憂いつつ、一方で彼らの活躍を嬉しくも思っていた。しかし、それらの動きも震災から半年〜1年を過ぎたころには沈静化し、彼らの活動が書籍という形に結実した段階で一応の終わりを迎えたように記者には見えた。もちろん今でも被災地に赴き、取材を重ねたり、東電の記者会見などに足しげく通っている。だが、メディア側がそれらの情報を多く求めなくなっている以上、露出の機会は減らざるを得ない。
ニュース・メディアでは、独自の情報をいかに得て、それをいかに早く出せるかが最重視される。ウェブであればライバル会社より1秒でも早く情報を出すことが肝要。日刊の新聞であれば出るタイミングは変わらないがゆえ、他社との差別化を図る形で速報を出せることが望ましい。週刊誌になれば、ある程度まとまった情報を出すことになるため、切り口の独自性、意外性が求められる。月刊誌ともなれば、よりいっそう俯ふかん瞰的な切り口の企画を練る必要性が生じるだろう。その過程が一定期間繰り返されながら、写真集や書籍の発刊に至れば報道のサイクルはひとまず1周したと考えて差し支えない。次に、関連する大きな事件や事実の発覚など新展開があるようなら第2、第3のサイクルが始まる。だが何もなければ、1年、2年などの節目に際し、紋切り型の「あれから○年」などの特集を行うにとどまるだろう。
被災地の方たちが最近「私たちを忘れないでください」という言葉を口にしていると聞く。このような報道のサイクルの中、被災者たちの情報は早い段階で消費され尽くした。読者や視聴者は被災者の置かれた状況に同情し、時には涙を流しただろう。だが報道の沈静化とともに徐々に彼らを忘れていったに違いない。人は自分の身に起こったことでなければ、その辛さを深く理解し、それを胸にとどめておくことはできない。だが、だからといって人々の間で無意識に「終わったこと」になり、メディアで「あれから○年」と過去のことのように回顧されるのはあまりにも不憫だ。今でも多くの人が何も変わらぬまま避難生活を送っている。せめて今も苦しんでいる人がいるということを忘れない努力はできるのではないか。その意味で、今回は被災者の身に起きたさまざまな出来事を再確認するためにも、ある1本の映画を紹介したいと思う。
考えさせられるセリフの数々

『希望の国』(Tha Land of Hope、園子温監督)で妊娠した女性が防護服を来て買い物をする印象的なシーン
6月5〜16日に行われた『シドニー国際映画祭』では東日本大震災や原発事故にまつわる2作品が2日間にわたって上映され、記者も鑑賞に赴いた。どちらも非常に意義深い作品ではあったが、ここでは特に原発事故に真正面から向き合った『希望の国』(園子温監督)をメインに、取り上げたい。
いわゆる映画レビューを書くつもりはないが、作品の概要は紹介する必要があるだろう。まず最初に言っておくと、同作の設定はすべて架空だ。舞台は、おそらく長崎、広島と福島から取った造語「長島県」の「大葉町(これも福島第1原発にほど近い大熊町、双葉町、楢葉町などの名前から作ったのではないか)」。東日本大震災の数年後という設定で、同様に大地震、津波、メルトダウンが起こる。作中、「福島の時のことを思い出せ」などといったセリフも登場するなど架空の設定に沿って話は進むが、そこで起こるさまざまな出来事は、すべて福島第1原発事故の際に起きた出来事をモチーフにしており、さながら被災者が直面したであろうさまざまな問題を詰め込んだ総集編のような印象だ。
だからといって、ストーリーが散漫になっているわけではなく、どの出来事も深く胸に突き刺さる。ストーリーは2家族、3カップルをメインに進む。① 老夫婦:小野泰彦( 夏八木勲)・智恵子( 大谷直子)、②その息子夫婦:小野洋一(村上淳)・いずみ(神楽坂恵)、③若い恋人同士:鈴木ミツル(清水優)・ヨーコ(梶原ひかり)という構成だ。
①の老夫婦は酪農家夫婦で原発からぎりぎり20キロ圏外ということで強制退去を免れるが、その後計画的避難区域に指定される。しかし、妻が病気であることに加え、慣れ親しんだその土地を動くという気はなく避難を断固拒否。そんな中、手塩をかけて育ててきた牛を殺処分しなければならなくなる(当連載第5回で行った原発座談会に登場いただいた「原発にふるさとを奪われて」(宝島社)の著者、飯舘村の酪農家・長谷川健一氏がモチーフではなかろうか。作品中に「原発に手足もがれたような気持ちだ」というセリフが出てくるがこれは長谷川氏の友人の酪農家が自殺した際に残した言葉だ)。
②の息子夫婦は福島第1原発の時の政府の対応からそこにいるべきではないと父親から自主避難を命じられた若夫婦。避難後、妻が身ごもるがそこに放射能の問題が大きく浮上してくる。生まれてくる赤ん坊のために、放射能を過剰に気にするようになった妻は、寝る時はビニールのテントの中、外出時は防護服を来て日常生活を送るようになる。
③は、20キロ圏内ということで強制避難をさせられた隣の家の放蕩息子とその彼女。彼女の方は津波以降、家族と連絡が取れなくなっているという設定だ。警戒区域の住民は避難所暮らしを強いられており、津波で流された肉親の捜索のために彼女は被災地に入ろうとするが入れない。いつまでも両親の安否が分からぬまま過ごす不安な日々を描いている。
以下、作品内の印象的なセリフをピックアップしながら被災者が直面した状況を切り取っていきたい(セリフは必ずしも正確ではないかもしれないがあしからず)。
「あなたの家は、20キロ圏外」
バリケードが2つの家を分かちさせた際に「うちは避難しなくていいのか」という小野家に対し、警察が放った言葉。バリケードの外と中にどんな明確な違いがあるのだろう。
「これは見えない戦争なの。弾もミサイルも見えないけどそこらじゅうを飛び交っているの」「この子のためなら何だってするもん」
洋一に防護服を着ることを非難され、いずみが放ったセリフ。見えないものに対する恐怖は尋常ではないが、一方でその存在を忘れてしまいかねない恐ろしさもある。
「たった1カ月で忘れたのかよ!」
防護服を着て暮らす妻に驚きを隠せずにいるが、それを同僚に馬鹿にされた際の洋一のセリフ。彼らは、ほんの1カ月前まで、放射能を気にし、洗濯物を部屋に干し、外出時はマスクをしていたが1カ月経ち、何事もなかったかのように過ごすようになっている。
「やっぱ敏感だねえ」
放射能対策をしっかり行っている洋一らに対する同僚のセリフ。
「テレビが嘘をついてるんじゃない。医者が嘘をついているんです」
放射性物質の飛散などについて本当のことを知りたがる洋一に医者が放ったセリフ。福島県立医大の山下俊一教授を揶揄した言葉か。
「国の言うことなんてあてになるか」「日本人が日本歩いてどうして怒られるんだ」「逃げるとは強さだ」「放射能と楽しく暮らせってことですか」
そのほか気になったセリフ。今の日本の状況にそのまま当てはまるのではないか。
子どもを守ろうとするのは当たり前のことで、だが、そのエスカレートする行動が周りから失笑される。実際、震災後東京にいた記者の周りでも「大丈夫だ」という情報を信じ込み、過剰反応する人を「騒ぎ過ぎ」と切り捨てる空気は確かにあった。そして記者もどちらかといえば、そちらの側だった。ネットで拡散した「安心」という情報を収集し、「気にしていても仕方ない」と構えていた。しかし今思えば根拠もなく右にならえでマスクを外し、日常生活を送っていたあの時の自分は、何1つ自分で判断していなかった。周りの空気に従ったに過ぎない。
原発事故の対応などで浮き彫りになった日本人の国民性など、いろいろなことを深く考えさせられた『希望の国』。ぜひ1度観ることをお薦めしたい。