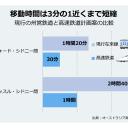ルポ:シリーズ・原発問題を考える⑰
「原発問題とは距離を置きたかった」
──宮城県出身ジャーナリスト・村上和巳氏に聞く
世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えつつ、自国内には原子力発電所を持たない国オーストラリア。被ばく国であるにもかかわらず、狭い国土に世界第3位の原発数を誇る原発大国・日本。原発を巡る両国のねじれた構造を、オーストラリアに根を張る日系媒体が取り上げないのはそれこそいびつだ。ルポ・シリーズ「原発問題を考える」では、原発を取り巻くさまざまな状況を記者の視点からまとめていく。 取材・文・写真=馬場一哉(編集部)
いよいよ4年目を迎えている「震災後」という状況だが、福島第1原発の状況には大きな変化は見られず、避難生活もいつ終わるとも知れぬ長期戦の様相を呈している。そのような状況下、被災地や政府、東電などに対し取材を続ける取材者の側もまた長い戦いを強いられている。当連載では複数回にわたり、私たちが目にし、耳にする情報の裏側で現場を飛び回るジャーナリストのストーリーを紹介していこうと思う。また違った目線から問題をとらえるきっかけとなれば幸いだ。
今回、話を聞いたのはかつて、東京で編集記者をしていたころに出会ったジャーナリスト・村上和巳氏だ。ジャーナリストの多くは自身の強みとなる特定の分野の情報に精通しており、村上氏もまた医療系の分野に特に強みを持っている。最近では4月22日発行の「週刊エコノミスト(毎日新聞社刊)」で「60億ドル賠償命令『武田薬品ショック』」の記事を執筆するなど活躍しているが、一方で戦場ジャーナリストとして紛争地を駆け回っていたこともある。また記者がかつて手がけた金融系のムックで、ウェブのポイント・サイトの攻略法や、クレジットカード活用術などを執筆するなど、かなりマルチに取材・執筆ができる頼れる人物でもある。そんな彼が東日本大震災を機に被災地の取材に飛び回ることになった経緯はどのようなものだったのだろうか。そのあたりのことから話を聞いていった。
被災地に向かった理由
「東日本大震災が起きた時、なぜそれを取材しようと思ったのか。やはり、こういう職業なので歴史に残る大事件を取材したいという気持ちは素直にありました。職業病とも言えるし、職業柄の野次馬根性とも言えるかもしれません。またもう1つ、私のアイデンティティーに関わることで取材者として有利な部分がありました。私の実家は宮城県南部の亘理(わたり)町のというところにあります。沿岸部の町で福島県の県境まで車で30分。南は福島第1原発まで、北は岩手県の陸前高田まで日帰りで行ける位置です。そういったところに取材者として有利な面を感じていたのは確かです。
震災の日、私はその日の午前中に仕上げなければならない原稿をほぼ徹夜で書いていて、地震がきた時はちょうど仮眠を取っていたところでした。ゆらゆらと揺れたなという感じがして目が覚めました。徹夜明けであれば普段はよほどのことがなければ目を覚まさないですが、あの時は眼が覚めました。それで、地震だなと。揺れはどんどん強くなってくるし、とにかく長い。しばらく天井を眺めていたのですが、これは尋常じゃないと思い、起き上がってベッドに腰かけた瞬間、ドスンという音が聞こえました。隣の部屋の机の上に置いていたスキャナー兼プリンターが床に落ちていたんです。で、その間も揺れている。これは尋常じゃないと思い、テレビをつけた。宮城県沖で地震とあり、東京は震度5と出ていた。私は宮城県の実家のことを考えるより先に、子どものことを真っ先に思い浮かべました。当時学校が終わった後、娘を学童保育に預かってもらっていたのですが、ちょうど学校から下校して学童保育に向かう途中か、着いたくらいの時間でした。電話がつながらなかったので、施設まで自転車で向かいました。
途中、幹線道路に出た時に余震が続いていることもあり、道路沿いの家から人が逃げ出して、家のドアも開けっ放しになっていました。揺れに合わせてそのドアがばたんばたんと鳴っているのが印象的でした。娘は学童保育に着いていたので安心して仕事場に戻りました。そして無情にもその時になって、気付いたんです。そういえば実家はどうなんだろうと。実家は4キロほど海から離れているのでまさか大丈夫だろうと思っていましたが何度かけても電話がつながりません。心配で、夜近くに住んでいる姉の家に向かったのですが、普段全く人気がない道が人で溢れていた。帰宅難民です。これはちょっと大変なことになっているなとその時、強く思ったことを覚えています。姉の家で両親と連絡を取ることができ、停電で困ってはいましたがひとまず無事だったので安心しました」
傍観者から当事者に
「翌日、私は事務所でテレビを見て、福島第1原発が水素爆発を起こしたことを知りました。その瞬間、ああもう駄目だな、どうしようと途方もない気持ちになったことを覚えています。これじゃあ東京も駄目かもしれないと思い、その瞬間に再び考えたのが実家のことです。うちの実家は福島第1原発から80キロ近くしか離れていない。急に心配になり両親に何とか連絡を取り、『車で日本海側に出てそこから東京に来い』と伝えました。しかし、母親が『ガソリンももったいないし、出て行く気はない。残る』と言うんです。いくら70歳を越えているからって親に何か起こることを見過ごすことはできません。とにかく逃げろと伝えましたが、結局そのまま残ることになりました。取材も含めて実家周辺には取材に行きたいと思っていましたがどうしても抜けられない仕事で結局現地を訪れたのは震災から約2週間後でした。
そのころの私は被災地出身とはいえ、傍観者の立場の気持ちでいました。深夜バスで向かったのですが、仙台で1度バスを降りて違うバスに乗り換えたんですね。町は早朝だからなどというレベルではないほど、不気味に静まり返っていました。そんな中、市街地を抜け仙台駅を歩いている時に、目に入ったアーケードに『私たちは負けない』と書かれた横断幕を見つけたんです。その時です。本当に突然気持ちが高ぶり、声を上げて泣いてしまったんです。
既に宮城県で暮らした時間よりも東京での生活の方が長くなっていたくらいでしたし、その半年前に7年ぶりに宮城に戻った程度。そもそも私は仙台も含め、地方の退屈さに辟易しており、まさに逃げ出すように地方をかなぐり捨てたのですが、その横断幕を見て泣いてしまった時に、自分は東北人なんだなと思ったんです。その瞬間、傍観的な気持ちで宮城県出身者として有利に取材をするなどというずるい考えは吹き飛びました」
ダリの『記憶の残像』
「実家に着くと母が出迎えてくれました。両親からリクエストのあったベーコンとソーセージをクーラー・バッグから出したら、母がはらはらと泣き出した。そのころは電気も水道も回復していたのですが。本当に辛かったのだろうなと思いました。父に会うと真っ先に言われたのが『取材しにきたんだろう。どこへ行きたいんだ』というひと言でした。父は『いずれあいつも取材で帰ってくる。だから、その時のためにガソリンを取っておく』と言い、私のために車を使わずにガソリンを取っておいてくれたんです。私たちは車に乗って海側の被災地に向かいました。

がれきの山の中に時を止めた時計がある。村上氏が震災取材で最初にシャッターを切った1枚だという
向かう途中、陸地にも関わらず、小舟があったりなど見たことのない光景が広がっていました。自分の見慣れた光景すべてが、がれきの山になっている。父親と一緒に「何だよこれ」と言い続けました。港で車を降りてがれきの山を歩き始めたのですが、混乱して何をしていいか分からない。カメラを持っているのに撮れないんですよ。見慣れた光景が見るも無惨に無秩序に破壊されている。僕は戦場の取材もよくやっているのですが、見慣れた風景が壊れていることの衝撃はそれ以上でした。がれきの山の中に時計があって、それにはっとしてシャッターと切ったのが最初の1枚でした。とっさにその時思い出したのは時計が木の枝にぶら下がっているダリの『記憶の残像』という絵でした。
今回の東日本大震災は大きく分けると、津波、原発、震災の被害に分かれます。私は最初は津波被災地ばかり回っていました。それくらい衝撃的だったからです。原発被災地の取材は4月18日に初めて行い、その後しばらくしませんでした。いわゆる反原発、また、反原発に対するアレルギーを持つ人たちの間の論争などがあって、そこに巻き込まれたくなかった。そういう意味で原発問題からは距離を置きたかったというのが素直な気持ちでしたね」
(次号に続く)

村上和巳───ジャーナリスト
宮城県亘理町出身。専門は国際紛争、安全保障、医学分野など。著書に「化学兵器の全貌」、「大地震で壊れる町、壊れない町」、共著「戦友が死体となる瞬間─戦場ジャーナリストが見た紛争地」など。最近は東日本大震災に専念。震災関連の最新刊共著「震災以降」(三一書房)。