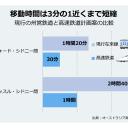ルポ:シリーズ・原発問題を考える㉕
「原発の安全神話」
歌人・三原由起子さんインタビュー①
世界有数のウラン輸出国として原発産業を支えつつ、自国内には原子力発電所を持たない国オーストラリア。被ばく国であるにもかかわらず、狭い国土に世界第3位の原発数を誇る原発大国・日本。原発を巡る両国のねじれた構造を、オーストラリアに根を張る日系媒体が取り上げないのはそれこそいびつだ。ルポ・シリーズ「原発問題を考える」では、原発を取り巻くさまざまな状況を記者の視点からまとめていく。 取材・文=馬場一哉(編集部)

三原由起子さん近影
4年前の6月、震災から3カ月という状況の中記者は自身の結婚式を控え忙しい日々を送っていた。震災直後、東京では「自粛」という言葉が飛び交っていた。人々や組織の多くは予定していた花見を自粛し各地の桜の名所は閑散とした状況となった。陽気なイベントや祝い事なども不謹慎だという理由で軒並みキャンセル、結婚式を取りやめた人もいた。
東京は1週間ほどで落ち着きを取り戻したが、震災の爪痕はさまざまな形となって我々の生活の中でその姿を現した。記者の父の会社では東北にある工場が津波被害を受けしばらく操業できない状況となり、続いて子会社が倒産。父もその責任を負わされるなど憔悴しきりで胸が痛んだ。それでも日常は徐々に取り戻されていったが、一方で自粛ムードはむしろ高まりを見せていったような記憶がある。
被災地のことを考えれば騒ぐ気にならない、自粛しようという思いも当然出てくるだろうが、入学式などに加え、さらには夏の花火大会まで、その自粛は少々行き過ぎたきらいがあったように記者は記憶している。いくら自粛をしたところでそこから何かが生まれるわけではない。“被災地の方たち、福島原発で復旧作業に携わる作業員の方々、風評被害で苦しむ人々…。今、たいへんな思いをしている人々に思いを馳せつつも、東京にいる自分がすべきことはまず経済活動、そして心ばかりの募金と節電だ”“ある程度割り切って動かないと日本全体がもっと深刻な事態に陥るのは目に見えている”
その当時、記者は上記の書き込みをインターネット上に投稿した。何かを偉そうに語れるような立場ではなかったが、書かずにいられない心境だったことを思い出す。結婚式を直後に控えていたこともあり「自粛したほうがいい」という世間の声に多少翻弄されてもいたが、本来動くはずだったお金を手元に置いておくことが経済的な意味合いも含めて良い効果につながるとはとうてい思えずキャンセルすることはしなかった。一方、別の視点では取り返しのつかない大きな問題に対し自分にできることは何かと深く自身に問いかけてもいた。

記者がそんなことに頭を悩ませていた当時、現在、一部帰還困難区域となっている福島県浪江町出身の歌人・三原由起子さんはこのような短歌を詠んでいる。“「十年後も生きる」と誓いし同窓会その二ヶ月後にふるさとは無し”
三原さんは新進気鋭の歌人としてメディアでも取り上げられるなど将来を嘱望されており、ふるさとへの思いを「短歌」「音楽」を切り口に伝える多彩な活動を展開している。2013年出版の彼女の第一歌集『ふるさとは赤』(本阿弥書店)では彼女が高校生だったころから17年間にわたる歌が時系列で収録され、生活や精神面での変化などが赤裸々に描かれている。中でも3.11を境に歌の質が変容していく様はリアルで、無念な気持ちとそれでも前向きに進んでいく様子に心を打たれた。
当連載では今回から2回にわたり、三原さんへのインタビューをお送りする。彼女とは連載23回目で紹介した「日本を紹介する100人」として各メディアでも取り上げられている浪江町出身の松永武士さんや本紙編集部員Oなどいくつかの幸運な縁が絡み合う形でつながることができた。偶然の出会いに感謝したい。
地元で感じた不条理
──もともと短歌を詠み始めたきっかけは何だったのでしょうか。
「中学生の時に登校拒否をしていた時期がありました。その時に当時国語の先生だった佐々木史恵先生が『詩を書いて自分の気持ちを外に出してみたらどうだ』と言ってくださり、自分で物を書くということをするようになりました。その後福島県文学賞の詩部門で青少年奨励賞という賞を受賞し、それがきっかけで登校拒否から立ち直ることができたんです。中学校を卒業してからも、佐々木先生とはずっと見守ってくださっていて、高校生になった時、先生に勧められて短歌を始めました」
──高校生のころからの作品集ということもあり『ふるさとは赤』でも序盤は恋愛模様を歌ったものが多いですね。歌1つ1つは独立していますが、順に読んでいくと三原さんの歴史が綴られていてストーリーを感じることができ、興味深く読み進められました。
「短歌は自分のことを詠う形式だと思うんです。最近の短歌は自分を出さずに分かりにくくしたり、レトリックに頼る方法が多くなっていますが、私の場合はストレートな性格が短歌に出てしまいます」
──それがゆえにまわりを取り巻く環境の変化などによって、歌が変容していく様子がリアルにうかがえます。
「そうですね。まず結婚してからは恋愛の歌よりも生活の歌にシフトしていきました。そのころ作った『ミラーボール』という一連では、東京から浪江町に帰省して町おこしに関わる中で、諦めることや仕方がないという現実と向き合って歌にしています」
──そうした背景から「仕方ない」から始まる歌(上記)を詠むに至ったのですね。
「浪江町には原発がなかったので、隣の双葉町と大熊町の原発立地地域に比べて町の財政が厳しかったんです。『浪江は原発がないから仕方ないんだ』と言いつつ、『雇用がないから原発で働くしかない』というような声をよく耳にしました。しかし、何でも『仕方ない』ですませていたら、結果的に日常がなくなってしまった。そんな思いで作りました」
──原発事故が起きる以前から地元で不条理と感じることも少なくなかったようですね。
「例えばイベントの運営に関する会議で『当日に雨が降ったらどうするんですか?』と質問した時には『雨は降らないから大丈夫』の一点張りでした。原発も『安全だから大丈夫』とリスクを見なかったのではないかと。今が良ければそれでいい。そういう風潮だったと思います。ふるさとだけではなく、原発事故後の現在の日本全体もそういう感じがして残念に思うことが多々あります」
──現在東京に住まれていますが、地方と東京の違いを強く感じていますか。
「東京の会社で働き始めた時にはそれを強く感じました。会議で意見を言うことは当たり前のことですが、田舎では意見はともすれば悪口と捉えられて『生意気だ』と言われてしまうことも少なくなかったのです。女性は黙って男性を支えていればいいという雰囲気もあって、違和感を覚えました」
──そんな中、震災が起きました。
「はい。これから地元のことも詠んでいきたいなと思っていた矢先に3.11が訪れました。それから私の作品はがらっと変わりました。以前から原発の危険性は認識していましたが、まさか原発事故で故郷を失い、一生向き合っていかなければならなくなるとは思いもよりませんでした…」(次号に続く)