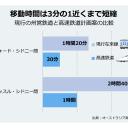【第16回】最先端ビジネス対談 (前編)

日系のクロス・カルチャー·マーケティング会社doq®の創業者として数々のビジネス・シーンで活躍、現在は日豪プレスのチェア・パーソンも務める作野善教が、日豪関係のキー・パーソンとビジネスをテーマに対談を行う本連載。今回は、「リゾート再生の請負人」との異名を持つ、星野リゾート代表・星野佳路氏にご登場願った。
(監修・撮影:馬場一哉)
PROFILE

星野佳路(ほしのよしはる)
慶應義塾大学卒業後、米国コーネル大学ホテル経営大学院へ。1991年星野温泉(現・星野リゾート)社長に就任。運営特化戦略を取り入れ、山梨県のリゾナーレ、福島県のアルツ磐梯、北海道のトマム・リゾートを再建、2005年「星のや軽井沢」開業。以後、「星のや」「界」、「リゾナーレ」、「OMO」、「BEB」のブランドを中心に、59のホテル運営を行う。「リゾート再生の請負人」としてメディアにも多数出演
PROFILE

作野善教(さくのよしのり)
doq®創業者・グループ·マネージング・ディレクター。米国広告代理店レオバーネットでAPAC及び欧米市場での経験を経て、2009年にdoq®を設立。NSW大学AGSMでMBA、Hyper Island SingaporeでDigital Media Managementの修士号を取得。移民創業者を称える「エスニック·ビジネスアワード」ファイナリスト、2021年NSW州エキスポート・アワード・クリエティブ産業部門最優秀企業賞を獲得
作野:大学卒業後、ホテル経営を学びにアメリカに留学されたと伺っています。
星野:私は小学校ではスピードスケート、中学から大学まではアイスホッケーとずっと体育会の世界に身を置いていしました。その間はとにかく試合に勝つことを目標に設定していたので、勉強はほとんどしていませんでした。その後、事業を継ぐためにはホテル経営の勉強が必要だと考えたのです。90年代当時、日本にホテル・スクールはなく、せっかくなら海外のスクールに行ってきちんと勉強したいというのが海外留学を決意した動機です。
作野:米国コーネル大学ホテル経営大学院で、2年間ホテル経営を学ばれた中でインパクトを与えられた出来事はありましたか。
星野:私はずっと日本で育ちましたから、日本に対する海外からの期待はどのようなもので、海外の人が日本をどう見ているかなど、外からの視点を私自身で考えたことはありませんでした。ですから留学中はその視点が欠けていると感じる場面がいくつもあったのです。特にショックを受けたのが、旅行業界から有名なゲスト・スピーカーが来たイベントに参加した時のことです。当時、一緒に学んでいた学生が50人程度いて、グループ・プロジェクトなどを通じてみんなと仲良くなるんです。その仲間たちと参加したそのイベントはフォーマルなものと聞いていたので、私はスーツにネクタイという恰好で向かったところ、浮いてしまったのです。普段はTシャツにジーンズのようなラフな格好で学校に通っていた仲間が、その日は皆、それぞれの国の衣装を身に着けていました。インドからの学生はインドの衣装、中東から来ている学生は中東の衣装、つまりそのイベントは世界中の人たちが自国の文化を表現する場だったのです。ところが、先ほどの通り私はスーツを着ていたので、同級生たちに「なぜ日本には古い歴史を持つ文化があるにも関わらず、お前はイギリス人の真似をしているんだ」と笑われました。それがすごいショックでした。その時からスーツを着ている自分が恥ずかしくなったのですが、今思うと特別な経験でした。ビジネスの世界で、そこまでストレートに言ってくれる人はなかなかいないと思うんです。

作野:結果的にはそれらの体験が今に結び付いてきているわけですね。
星野:はい、2003年に星野温泉旅館を建て壊して、新たに「星のや軽井沢」を作るプロジェクトを立ち上げたのですが、私の中での、唯一にして最大の目標は大学院時代の同級生たちから「お前はなぜ西洋リゾートの真似をしているんだ」と言われないものにするということでした。軽井沢は元々西洋の文化を感じさせる観光地ですし、西洋風にアレンジするのが軽井沢らしさでもありました。しかし、私は「さすが日本」と言われるようなものを作りたかったのです。そこで「谷の集落」というコンセプトのもと、日本の屋根が連なっているようなデザインにしたり、海外のリゾートよりもはるかに進んだエネルギー自給の仕組みを「星のや軽井沢」で時間を掛けて実現しました。このことは今でも私にとって大きな誇りです。
作野:同級生を見返したいという思いが原動力となっているのですね。
星野: 1980年代のバブル経済真っ只中、トヨタやソニー、パナソニックなどが米国を圧倒し、更に日本企業がロックフェラー・センターを買収するなど、すごい時代でした。そんな中、ホテル業界でも、日航ホテルがエセックス・ハウスを買収し、ホテル・オークラや帝国ホテルが海外進出を果たしました。そうなると、同級生から「お前の国は何がそんなにすごいんだ」と問われます。しかし、私自身はそのすごさの理由を当時はまったく答えられなかった。そんな中、バブル経済が崩壊し、日系のホテル企業も90年代に米国から撤退するまでを私は目の当たりにしたのですが、当時の日系ホテルの苦戦ぶりは私にとって大きなコンプレックスとなりました。日本人は丁寧で、優しく親切で、ホスピタリティーに向いている文化を持っているにもかかわらず、ホテル運営はうまくできない。ホテル・スクールでもそのことを指摘され、そのことは私の心の中にわだかまりとして残りました。留学を終え軽井沢に戻った時、私たちはまだまだ世界に出ていけるような状況ではなかったのですが、少しずつ市場でのプレゼンスが大きくなるにつれ、もしかすると日本のホテル会社を代表して海外でのリベンジを果たすことができるかもしれないという感覚をこの10年間で得られるようになってきました。ようやく海外への挑戦権を得た、やっとオリンピックに出られる、そんな気持ちです。そして、日本のホテル会社が海外で挑戦するならば、やはり日本の文化を体現できる「日本旅館」で勝負をしなければならないと考えています。これが80年代、90年代の米国で私が経験し、学んだことなのです。
作野:皆さんの期待値がおそらくそこにあるだろうというわけですね。
星野:はい、その通りです。日本旅館でアプローチしない限り、世界の人たちは、私たちが世界に出て行く理由を認めてくれないという確信があります。

リスクを取った北海道トマムの再建
作野:オリンピックへの出場権利を得られた感覚、と先ほどおっしゃいましたが、「星野温泉旅館」からスタートし、現時点で59軒のホテルを運営されています。さまざまな挑戦がおありだったと思いますが、最も心に残っていることは何でしょう。
星野:1つには絞りきれないですが、最初に思い出すのは北海道トマム・リゾートの再建です。トマムは巨大なリゾートで、発電所の経営、水道事業までを担っています。2000の客室に加え、パブリック・エリアまでを含めると1つの町を運営しているようなもので、その赤字の度合も当時はかなりのものでした。とても私たちだけで抱え込めるようなリスクではなく、再生を担う話が持ち上がった時、私は反対しました。しかしその後も担い手は現れず、最終的には私たちが運営を引き継ぐことになりましたが、既に大出血している状態ですから、まず止血をしなければなりません。その上で業績を好転させるためには売上も立てる必要があるなど、特に最初の3年間はたくさんの苦労がありました。
作野:引き継がれた際、持たれていたビジョンは実現できましたか。
星野:ファイナンシャルの面でいうと、十分な収益を出すことができました。そういった意味では成功したという評価を頂きましたが、まだ道半ばであると考えており、まだまだやらなければならない仕事が残っています。というのも、私は全てのリゾートにおいて、明確なコンセプトと理想を持っています。ただ一方で現実もあります。理想を思い描きつつ、現実的なアプローチを取るために、ちょっとずつ妥協しているというのが本当のところで、妥協していない施設は1つもありません。そしてその妥協したポイントというのは実は私だけが知っています。実際に、施設に行くとそのポイントが光って見えてしまうので、理想と現実のギャップの間で落ち着かない気持ちになります。しかしそれでもお客様に十分な価値を提供し、きちんと収益を出しながら、そういった妥協を1つずつ改善していくチャンスを残しながら、運営をしています。リゾート作りというのは、かなりロングタームなプロジェクトなのです。
作野:施設ごとにビジョンを持たれているということですが、ビジネスのインスピレーションはどこから得られるのですか。
星野:かつての私の同級生が来た時に、バカにされないようにすることです。
作野:そこに戻られるのですね(笑)。
星野:はい(笑)。例えば、私たちが運営する青森県の「青森屋」という施設は、元は古牧温泉という巨大な団体温泉旅館でした。私は同級生が来た時に、日本人の団体客が星野リゾートのホテルで酔っ払って騒いでいる姿を見せたくないですし、社員にもそのような状況でサービスをさせたくないという強い思いもあります。そのため、「青森屋」は青森文化のテーマパークというのをコンセプトにしました。ねぶた祭り、津軽三味線、ヨッテマレ酒場など青森の魅力を随所に盛り込み、スタッフは津軽弁で接客をします。「青森屋」は成功したプロジェクトの1つですが、そのインスピレーションの源泉は私のかつての同級生に「日本はすごい」と必ず言わせるということ。その点においては日本人も海外の人も、地方の観光地に求めるものは一緒だと思っています。ローカルの文化の豊かさやすばらしさが観光の最大の売りですし、観光というのは基本的にはご当地自慢なのです。地元の人たちが地元に対してプライドを持って、それを堂々と表現し、そのすばらしさを来た人に知ってもらう。全員を満足させることは難しいかもしれませんが、喜んでくれる旅行者は世界中に大勢いるはずです。
作野:今後の残された人生で叶えられたい夢、ビジョンはありますか。
星野:世界に対して日本旅館で勝負する、その一歩を踏み出すのが私に残された時間の中での重要な役割だと思っています。最初の一歩を踏み出し、成功するプロジェクトとしての姿を世界に示したいと考えています。ホテル業界というのは不思議なもので、世界中の国が新しいホテルのコンセプトを必死に探しています。温泉旅館は、ニューカテゴリーとして、その後世界に広がっていく可能性を秘めたプロダクトだと私は思います。日本食を食べて、温泉に入り、日本らしい建築や空間を世界の人びとが楽しむ。温泉旅館は私たちが発明したものでも何でもなく、日本に何百年も前からある、言わばテーマパークなのです。その魅力を世界に知って頂くこと、それが私の叶えたいことですね。
作野:叶えられそうですか。
星野:既にチームを作って場所を探しています。温泉は世界中にあちこちありますし、南半球だとニュージーランドのロトルアなどでは、ものすごい量の温泉が湧き出ていていますが、あまり使われずに川に流れている。日本では考えられないような、もったいない状況です。私はそういったところにチャンスはあると思っています。
年間60日のスキー滑走
作野:3年ぶりの来豪となりましたが、コロナ禍以前は毎年南半球にお越しになられていました。
星野:はい、南半球にはスキーを目的に12年連続で来ていました。星野家の人間は、遺伝子に組み込まれているのではないかというくらい、80歳で人生を終えています。そこで私も50歳になった時に残りの人生を30年と仮定してみたのですが、30年後に後悔があるとすれば「もっとスキーをしておけばよかった」ということではなかろうかという結論に至りました。その30年を前後半に分けた時に、体のことを考えると、後半の15年間よりも明らかに前半の方がスキーには向いています。そこで、自分の人生最後の日に後悔しないよう、あらかじめ年間の滑走日数を60日と定め、最初にスケジュールだけ決めて、仕事は残りの日にすると割り切りました。ただ、日本を始め、北半球の冬だけで60日を達成するのはなかなか大変なので、季節が逆のオーストラリアやニュージーランドに通って20日くらい日数を稼ぐことを決めたのです。ただ、コロナ禍の期間は日本の冬だけで何とか60日を達成しました。

作野:星野リゾートの海外でのプロモーションも星野さんのスキーの日程に合わせてやっておられると伺っています。ビジネス(Business)とレジャー(Leisure)を両立するブレジャー(Bleisure)を実践されていますね。
星野:そうですね。現地を訪れる回数を重ねれば重ねるほど、市場への理解も深まりますし、オーストラリア人が日本のスキー場を訪れてくれる理由もよく分かりました。オーストラリアのスキー場も魅力的ですが、雪だけを見ると圧倒的に日本が勝ります。雪の質、量、それはもう全然違うレベルで、日本のように腰の高さまであるようなパウダー・スノーにはオーストラリアではなかなか出合えません。だからこそ、この土地でスキー、スノーボードを練習して好きになった人たちは、将来必ず日本に行きたいと思うようになるのです。そこに確信を持つことができたというのが大きかったですね。
(以下、後編に続く)