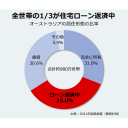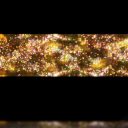アリサの洗礼
アリサが新たなスキル「メガネ壊し」を習得した。メガネのフレームを左右に広げて破壊するという攻撃技で、このスキルが発動されるともれなくメガネが使えなくなる。RPG的に言えば視界を奪う間接攻撃的な位置付けになるのかもしれないが、何せ、しばらくメガネが使えなくなるためその効用時間は地味に長い(妻の実家では家人のメガネがもれなく破壊、後日、皆が修理に走った)。
幸い僕はこれまで難を免れていたが、ついにアリサの洗礼を浴びることに。夜中の読書に使っている「Reading Glasses」(横文字だと一見いい感じに見えるが老眼鏡)のヒンジ部分が完全破壊され、無残にも180度開脚状態で机に置かれていたのである。
奇しくもその晩、シドニーは大雨に見舞われ、その影響で我が家は深夜に停電。ちょうど原稿執筆を再開しようとしていたタイミングで全ての電気が落ち、気勢を削がれる形に。仕方なく電池式の読書灯を点け、気分転換に読みかけの『街とその不確かな壁(村上春樹著、新潮社)』を開いたタイミングで僕は、その亡骸を発見したのだ。
話を脱線させるが大雨のたびに停電するというこの生活インフラの脆弱性は本当に困りものだ。停電は翌朝解消したが、その後我が家は3日以上お湯が出なかった。ビルの管理人からどこか別の所でシャワーを浴びてくれとのお達しがあったが、どこかってどこですか? 公共浴場があるわけでもないこの国でいくら何でもそれは無茶振りだ。
更に脱線。昔ファミコンでよくやっていた戦国シミュレーション・ゲーム『信長の野望』では、政治のターンで「治水」という項目があり、当時小学生だった僕は国力を強くするために「治水」を行っていたがその本質を理解していなかった。今になって思えば最強コマンドだ。ボタン1つで国の治水力が高まるのだから。
さて、戻そう。発見したメガネはつるの部分が完全に割れ普通に考えれば買い替えレベル。だが、実際には家の中だけで使用するだけの物なので、応急処置でも良いのではないかということで思いついたのが「Blu Tack」だった。日本だとあまりなじみがないかもしれないが、オーストラリアでは広く使われているガムのような粘着剤で、壁に物を貼る、物を簡易的に固定する、細かい部分のほこりを取るなど、アイデア次第で用途は数多くあり、僕は日常的に使用している。これをヒンジ部分にパテのように使うことで最低限の機能を取り戻すことに成功。
「Blu Tack」はしっかりと固定するには頼りない粘着力なのだが、簡単に剥がせるため軽い物を壁に手軽に貼るには非常に便利。使ったことがない人はぜひスーパーでチェックしてみては。
なぜか「Blu Tack」の宣伝になってしまったが、今回のメインネタは久々に訪れた「シドニー・ロイヤル・イースター・ショー」だ。
11年前の僕にとっての「イースター・ショー」

4月上旬、「シドニー・ロイヤル・イースター・ショー」を訪れた。僕ら夫婦にとっては約10年ぶり。園内の至る所にいるたくさんの動物、屋外でのピクニック、遊園地のアトラクション、それらを子どもたちが笑顔で楽しむ姿を見ていただけで、よくよく考えれば自分自身は特に何をしたわけでもない。だがなお心が満たされる極上の時間を過ごすことができた。それは、きっとこのショーが、多分に家族連れ、子どもに向けて作られている側面が大きいからかもしれない。
さて、ここまで書いておいて肩透かしかもしれないが、以降、筆を11年前の「自分」に譲る。40台半ばになった今の僕が「お父さん」の目線で語るより、2013年に書いた記事の方がよほどショーの本質を突いていた気がするからだ。若かったな、とももちろん思うが、こんな思いや時間を経て今の自分があるのだなと改めて感じた次第。この拙文が皆様にとっても、この地で今を過ごしているご自身、そこに至るまでの時間を振り返るきっかけになるとうれしく思う。
シドニー五輪が行われる前年、僕はなけなしの金を手にオーストラリアを訪れた。長距離バス・チケットを購入し、シドニーからメルボルン、アデレード、アリス・スプリングス、エアーズロック・リゾート、テナント・クリーク、そしてタウンズビル、ケアンズというルートを陸路で回った。この時の旅で得た体験はどれも貴重で忘れがたく、僕はオーストラリアという国の持つ懐の深さに取りつかれた。
2011年再来豪を果たす。語学学校でひと回り以上も若い子たちに混じり、英語の歌を歌ったり、ゲームをする毎日。貯金は驚くほどの勢いで減り続けた。時に日本に帰りたがる妻を「そんなことでどうする。先が見えるまでは絶対に後ろを振り返ってはダメだ」と自分の夢であったにもかかわらず身勝手にしかった。そのころ僕らにはけんかが絶えなかった。
そんな折、僕らは「シドニー・ロイヤル・イースター・ショー」を訪れたのだ。農業・酪農産業に携わる人びとが、毎年手塩に掛けて育てた牛・豚・鶏・羊の品評会から始まった同イベントは、190年(編注:13年当時)という長い歴史を誇る農業・酪農大国オーストラリアの文化を深く満喫できる祭りとして知られ、1万5,000品目を超える農作物や食品の展示、ロデオや丸太切り競争、ドッグ・ショー、豚のレースなどさまざまなイベントやアトラクションが一堂に会す巨大テーマ・パークさながらのショーだ。
疲れ切っていた僕の目に、馬、羊、ヤギ、豚をはじめとしたさまざまな動物たち、そしてそれを輝く目で見つめる子どもたちの姿が映った。フレッシュ・フード・ドームでは色とりどりの鮮やかな野菜や穀物を眺めながら、ラム・ステーキやチーズを試食。そしてワインを試飲しながらオーストラリア産のオイスターに舌鼓を打つ。「なんだこれは?」と思わず笑ってしまった丸太切り、動物たちのレース。僕はいつしか心の底からショーを楽しみリラックスしている自分に気付いた。この国の「豊かさ」の源流、僕がずっとこの国に惹かれてきた理由がこの時初めて形となって目に飛び込んできたような気がした。そして改めて思ったのだ。「ここでがんばっていこう」と。
だから僕は今年もまた自分がこの地にいることの喜びをかみ締めるためにショーを訪れたのだ。もし、まだ訪れたことがなければ来年こそぜひ足を運んでみていただきたいと思う(「編集部BBKの突撃レポート第7回」(日豪プレス2013年5月号)より一部抜粋、一部編集)。

このコラムの著者
馬場一哉(BBK)
雑誌編集、ウェブ編集者などの経歴を経て2011年来豪。「Nichigo Press」編集長などの経歴を経て21年9月、同メディア・新運営会社「Nichigo Press Media Group」代表取締役社長に就任。バスケ、スキー、サーフィン、筋子を愛し、常にネタ探しに奔走する根っからの編集記者。趣味ダイエット、特技リバウンド。料理、読書、晩酌好きのじじい気質。ラーメンはスープから作る。二児の父