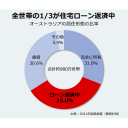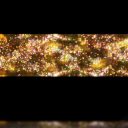宝石大陸見聞録と銘打っての新シリーズ初回は、今回の旅の重要な目的地であるブロークン・ヒルへの道中に寄り道したホワイト・クリフズでのオパール探しまで書いた。2回目となる今回は、ブロークン・ヒルでの滞在とその先のお話。まぁ、能書きはここまでで、さぁ、さっそく出発進行!
一路、ブロークン・ヒルを目指しバリヤー・ハイウェイ(国道A32)を西へ西へと走っていく。現在も地下で採掘のために稼働中の3つの巨大鉱山の間を走り抜けると、ようやく視界に現れてくるのがオーストラリア最大の鉱業の町ブロークン・ヒルだ。人口1万7000人のこの町は、歴史的建造物が多く残され、この町がたどってきた歴史を感じさせるのに十分な趣がある。
1883年、現在の町の中心エリアから25キロほど離れた場所で、銀と鉛が見つかったのを皮切りに、85年以降、本格的に鉱業が盛んとなった。最盛時の1905年には、3万人を超える人口を数えた。140年もの鉱業の歴史を有する町は、往時よりは人口が減りはしたものの、長さ7.5キロ、深さ1.6キロの規模を誇るオーストラリア最大の鉱山が稼働する同国有数の“マイニング・タウン“なのだ。

町の案内所で石関連の情報を聞いてはみたが、やはり本格的な鉱山の町だけあって立入禁止区域が多く、石探しには向かないので、観光を優先させることにする。町の中央にある鉱山の見晴台から町の景色を一望して写真を撮りながら下山する。その途中、案内所で「あの辺りなら石とか持って行っても大丈夫だよ」と言われた場所に差し掛かった時、道端がキラリと光った。
すぐに、膝をつき、きらめいた石を手に取りじっくり観察する。漆黒の表面はツルリとした面とボコボコの粗い面があり、光にかざすと虹色に反射する。一瞬ドキッとはしたが、鉱物を熱処理し、鉛や亜鉛などを取り除いた後のガラス状になった石の塊で、スラッグ(Slag)呼ばれる物に間違いない。要は産業廃棄物だが、持って行っても問題ないとのことだったのでブロークン・ヒルの記念品としてポケットに忍び込ませた。

ブロークン・ヒルは、2015年公開のオーストラリア映画の名作『Last Cab To Darwin』の舞台となった。劇中で主人公の家として使われた場所で記念撮影してから、町の外れでピクニックがてらランチをすませる。それからゆっくりと町の北にある今晩のベースとなるリビング・デザート・スクラプチャー(Living Desert Sculpture)のキャンプ場に向かう。
緩やかな山道を進み、山頂に着くと、そこにはオーストラリアの彫刻家によるサンド・ストーンの彫刻がズラリと並んでいた。大自然と奇抜な彫刻との取り合わせ、時間や天候の移ろいで変わるサンド・ストーンの色合いを楽しみながらの味わい深い時間と共に、日は静かに暮れていった。

翌朝、晴天。キャンプ場を後にして更に西へ進む。やがて、NSW州とお別れして、越境したのが南オーストラリア(SA)州。道端にはSA州の州花、真っ赤で中心に黒い球状の種があるスタート・デザート・ピー(Sturt Desert Pea)が咲き乱れ、美しく鮮やかな花のお出迎えにテンションが上がる。そんなSA州入境後、最初に訪れた町はピーターボロ(Peterborough)。VIC州、NSW州、WA州、NT準州の4州をつなぐ駅があったころは活気のある町だったが、現在の人口は1400人ほど。今も、メイン・ストリートの脇にはかつて走っていた列車が何両も置かれていて、往時の賑わいと歴史を感じさせる。


以前、町の唯一の娯楽の場だった劇場を改装したカフェでコーヒーとピロシキを食べてから、のんびりと町の周りを散策する。町外れに石が無造作に積んである場所があった。泥が固まった泥岩ばかりかと思いきや、よくよく見るとなかなかおしゃれな模様が混じっている。紫、茶、黒色の混ざった塊は、オーストラリア北部で採れるゼブラ・ストーンに近い感じの印象を受けた。
その後、案内所で今後の訪れる場所の情報収集をしてから、この町の列車の歴史を学ぶツアーに参加。町外れでキャンプをして、SA州の初日が暮れていった。

翌朝、朝食を軽くすませてから、進路を北西に取る。次なる目的地は、案内所で聞いたマグネティック・ヒル(Magnetic Hill)。その名の通りに強力な磁力を帯びた丘とのこと。未舗装路を走ること30分、丘のふもとに看板があり「車のエンジンを切り、ギアをニュートラルに」とある。
半信半疑で言われるままにしてから、車内で大人しく待つ。すると、どうだ、勝手に車が坂道を登り始めるではないか。磁力が起こす初めての感覚に童心に帰ったかのように大はしゃぎのトレジャー・ハンター、4○歳(笑)。
その後、更に北へ進み、フリンダース・レンジ(Flinders Range)を通過。南のフォーカー(Fawker)と北のパラチルナ(Parachilna)へと連なるこの山脈は鉱山でも有名で、特に北東部のブリンマン(Blinman)は銅の採掘が盛んだった場所。他にも化石が採れることでも有名だが、国立公園に指定されていて石探しは御法度なので、美しい山道のドライブを楽しむ。
道中は大自然にポツンとたたずむ寂しげな廃墟で写真を撮ったり、壮観な岩肌のエミリー山でピクニックをしたりしながら、夕方までにブリンマンに到着。歩けないくらいの強風で散策は諦め、町で唯一のパブにピットイン。ビールを流し込んで、長い運転の疲れを癒す。

“何か情報が欲しければパブに行け”が基本のオーストラリア。このパブで鉱山の歴史をいろいろと教えてもらったところによれば、1850年に羊飼いのブリンマン氏が銅を発見して以降、62年から1907年まで銅採掘が行われた町のピーク時の人口は1500人。現在はわずか18人となってしまった町に残された数々の廃墟が、往時の賑いをかすかな名残として伝えている。

翌朝、銅山跡地を見学。ここにも虹色に光る黒い産業廃棄物がゴロゴロとしている。更には、取り残した緑色の銅を含むマラカイト(孔雀石)も所どころに落ちているのを見つけた。
とまぁ、今回はこれと言って目を見張るようや石との出合いはなかったが、オーストラリアの鉱山とそれに関する歴史を学び、マグネティック・ヒルなど幾つかの得難い経験をできたのは予想外の大収穫だった。
今回書いた移動距離だけでも1000キロを超え、運転時間だけでも12時間近くかかる旅程をさほど苦労なくこなせたのは、やはり訪れた先々でいろいろなことに触れ、さまざまなことを学ぶことができたからだろう。
来月以降も、もう少し、トレジャー・ハンターの宝石大陸見聞録にお付き合い頂ければ幸いだ。
(この稿、続く)
(写真はすべて筆者撮影)
このコラムの著者

文・写真 田口富雄
在豪25年。豪州各地を掘り歩く、石、旅をこよなく愛するトレジャー・ハンター。そのアクティブな活動の様子は、宝探し、宝石加工好きは必見の以下のSNSで発信中(https://www.youtube.com/@gdaytomio, https://instagram.com/leisure_hunter_tomio, https://www.tiktok.com/@gdaytomio)。ゴールドコースト宝石細工クラブ前理事長。23年全豪石磨き大会3位(エメラルド&プリンセス・カット部門)