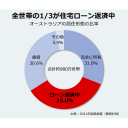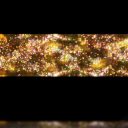オーストラリアでは「drought(干ばつ)」という言葉を毎年のように聞く。私が暮らすサウス・コーストは干ばつが頻発するエリアではないものの、冬の終わりから春に掛けては少雨と乾燥が極端で、湿度の低さで肌が異様に乾く。本格的な干ばつに至らずとも、飲用水の不足、植物の枯死、火災のリスクなどを真剣に意識しておかなくてはならない。(文・写真:七井マリ)
乾いてひび割れた地面

粘土質の土は乾ききってひび割れ、周りの雑草は枯れて鮮やかさを失っていく。風が吹けば土埃(つちぼこり)が舞い上がる。そんな光景はオーストラリア内陸部の乾燥地帯だけでなく、温帯や亜熱帯のエリアでも決して珍しくない。温帯に属するサウス・コーストの田舎に移り住んだ年の春、庭の地面に明らかな亀裂をいくつも見つけた時は、これがオーストラリアの気候かと妙な感慨を抱いた。
乾燥が続く時期に町を車で走れば、家々の庭木や芝生が強い陽射しの下で生気を失いかけているのが目に入る。芝生の青さを保つために毎日のように水をまいても、ある程度の高温と低湿のセットが続けば葉は少しずつ褐色になっていく。蛇口をひねって出る水が上水道からであれ雨水タンクからであれ、水も限りがあるので好き放題にまき続けるわけにもいかない。
対して、オーストラリア固有種の植物は違った様相だ。乾いた土の上で咲く固有種の花の姿に、当地の気候に適応してきた植物の生命力を感じる。ユーカリは常緑樹だが、葉からの水分の蒸散を減らすために、乾燥を察知して驚くほど大量の葉を落として地面に積もらせる。強風の日にとめどなくユーカリの葉が降る様子からは枯死を連想するが、実際は生存のためのルーティーンのような毎年恒例の眺めだ。
雨の少なさが生活に及ぼす影響

「干ばつ」とは、日照りや少雨で長期的な水不足が続く状態を指す。その年の気候によって、特にオーストラリアの乾燥した内陸部では人間の飲用水だけでなく家畜のための水や牧草も不足する。水や飼料代が尽きる前に、肥育農家が予定外に早く牛や羊を売るのもよくある話。特に干ばつがひどかった年には、雨を待つ間に資金が尽きて廃業する農家や、緑が枯れ果てた土地でやせ細って死んだ多数の家畜を埋葬する農家のニュースも見た。
サウス・コーストはそこまでの少雨や乾燥に見舞われることは珍しいが、それでも干ばつはすぐそこにある現実だ。このエリアでは9月から始まる春が年間で最も雨が少ない。私の住むエリアは上下水道がなく、飲用から庭の水やり用まで全てを各家庭の大型タンクに溜めた雨水から調達するので、雨が少なければ水は溜まらず干ばつは生活にダイレクトに影響する。春だというのに家の周りに溜まり続ける枯れ葉を掃きながら、ひたすら祈るように雨を待つ。
この季節の降水量がゼロというわけではない。とはいえ、連日の強い陽射しと極度の乾燥の後では少量の雨は土の表面をぬらすにとどまり、人間にも動植物にも不十分だ。近年の気候の変化によって、春の時点で夏のような熱風の吹く日が増えていることも乾燥に拍車を掛ける。
下がる水位、生き物たちの渇き

雨が少ない時期は、水の残量を常に意識しながら蛇口をひねる。雨量の不足はタンクが空に近づくことを意味し、本当に不足したら給水業者から多量の水を買うこともある。
オーストラリアの田舎では、個人所有の土地に溜め池があることも多い。ポンプでくみ上げて庭の水まきや家畜の飲用水などに使うだけでなく、カンガルーや鳥の水飲み場として、カエルや水棲のカメなどの生息地として溜め池は重要な存在だ。ただし、溜め池の水源も雨。暑さによる蒸発と少雨が続けば水位はみるみる下がってしまう。
家庭菜園には、我が家では飲用とは別に庭に設置した雨水タンクから給水している。露地栽培でなくガーデンベッド栽培を選んだのは、地面がひび割れるほどの乾燥ぶりも踏まえてのことで、下に水が溜まる構造なので1滴も無駄にせずに済む。シャワーを浴びる時に大きなたらいやバケツにお湯が溜まるようにしておけば、冷めてから地植えの果樹の水やりに使える。とはいえ、どれほど節水してもまとまった量の雨が降らなければ雨水タンク内の残量は減る一方だ。
野生動物が飲むようにと水を張ったバケツを庭に置いてすぐに、普段は警戒心が強い野鳥が舞い降りた。こちらの存在を気にしつつバケツの水で喉を潤す姿に、その渇きの切実さを感じた。
森林火災に備える貯水のルール

万が一火事が起きて消防車が来る時には、雨水タンクや溜め池は消火用の給水源にもなる。森林火災のリスクが高いエリアでは、少雨であっても飲用水や園芸用水として全て使い切ることなく、常に決められた量以上をタンクに貯水しておくことがルールだ。
給水業者の車両がやって来るのを見掛けると、どこかの家の雨水タンクの貯水量が少なくなってしまったのだと分かる。月々の水道料金がない雨水タンク方式は降雨がある時なら安上がりだが、タンクやポンプなどの設備、渇水時の給水などにまとまったコストが掛かるのも現実だ。
この辺りには雨季はないが、昨年は夏が始まる12月の直前、唐突に1週間ほど雨が降り続いた。乾ききっていた地面を嵐のような集中豪雨が瞬く間に水たまりに変え、各地で浸水被害や洪水が相次いだ。と思ったら、2週間後には熱波で気温が40度まで上がり火災リスクが高まるという、なんとも慌ただしい夏の始まりだった。そうは言っても溜め池やタンクの水位が回復したことには心から安堵したし、果樹は枯れず、家庭菜園も無事だった。
今季はどうなるか、気にはしつつも気に病まない程度に意識しておくのが良いだろう。オーストラリア東岸の今年の春は例年より多雨・高温の傾向が予想されているが、「例年」より雨が少々多い程度なら土はすぐに乾いてしまう。今のところ生きている果樹や野菜がこの先も無事だといい。
著者
七井マリ
フリーランスライター、エッセイスト。2013年よりオーストラリア在住