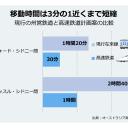対談 : 八尋恆存 (空手家・東京五輪豪州代表 ) X 作野善教(doq®代表)
日系のクロス・カルチャー·マーケティング会社doq®の創業者として数々のビジネス・シーンで活躍、現在は日豪プレスのチェア・パーソンも務める作野善教が、日豪関係のキー・パーソンとビジネスをテーマに対談を行う本企画。今回は、東京五輪、空手種目にオーストラリア代表として参戦した八尋恆存氏にご登場願った。
(監修・撮影:馬場一哉)

作野:八尋さんは日本のバック・グラウンドを持つオーストラリア人としてシドニーで育ってこられたわけですが、日本人のご両親と共に、どのような幼少期を過ごされたのでしょう。
八尋:幼少期のことで思い出すのは、「家で英語を話してはダメ」というルールがあったことです。食事や生活リズムも非常に日本的で、オーストラリアに暮らしていながら「家に帰ると日本」というような環境でした。外に出たら英語は勝手に覚えるだろうということで、家では小学校6年生くらいまで日本語のドリルをやっていました。文学全集なども読まされていたので、読むことは問題なくできるようになりました。父が日本語を教える学校を経営していたこともあって、日本語教育に関してはかなり厳しかったです。

作野:一歩家の外に出るとオーストラリア。家の中にいると日本。その辺りのカルチャー・ギャップをどのように感じておられましたか?
八尋:小さなころから当たり前の環境だったので、違和感はなかったです。あいさつや敬語の使い方など、かなり厳しく教え込まれましたが、今思えばこの環境には感謝しかないです。おかげで今でもしっかり日本語を話すことができ、実生活でも役立っていますから。

作野:その当時のシドニーは、今とはマルチカルチャーのバランスや度合い、日本に対する興味なども異なると思いますが、実際、違いを感じますか。
八尋:日本人の数自体が少なかったので、日本人の家族は珍しい存在ではあったかもしれません。ただ、少なくとも自分はそれで嫌な経験をしたことはなかったです。先代の日本人の方々が評判を高く保ってくれていたため、日本人に対して良い印象を持っている人が多かったのだと思います。実際に差別を受けたこともないですし、むしろ日本人だからということで優遇されることの方が多かったかもしれない。この点、先人たちに感謝すると共に、自分もそれに続かなければならないと思います。
作野:日本のルーツを持ちながらオーストラリア人として育った八尋さんにとって、日本という国はどのような存在でしたか。
八尋:憧れのような存在でした。当時は現在のようにソーシャル・ネットワークなどもなかったですし、祖母がビデオに撮って送ってくれたテレビ番組やお菓子などの荷物が日本から送られてくることを楽しみにしていました。また、小学校の時には短期ながら日本の学校に通わせてもらったことがあるのですが、非常に新鮮で楽しかったです。
作野:日本とオーストラリアの学校の違いを、どのように感じましたか?
八尋:今思えば学校には二国間の文化の違いがしっかり出ていたなと思います。学校の作り1つとっても、日本の場合は1つの建物の中で完結している印象ですが、オーストラリアの学校は作りがオープンで、またシステムも異なりますよね。日本の場合、教室は基本的に1つで先生が移動してやって来るのを生徒が待つ形ですが、オーストラリアでは生徒が移動します。また、学校内での勉強の時間に関しては日本の方が多かった気がします。一方でオーストラリアの学校は遊ぶことも重視します。そして、中でも日本の学校で非常に新鮮に感じたのは給食のシステムです。
作野:オーストラリアでは給食ではなく、ランチ・ボックスを持って行っていたと思いますが、八尋さんはどのようなものをお持ちになっていました?
八尋:リンゴとヌテラ・サンド、といったような感じでした。
作野:そこはローカルのご家庭と変わらないのですね。
八尋:ええ、おにぎりとなどを持って行くと「何食べてるの?」と注目されるような感じになるので、子どもながらに「みんなと同じが良い」と親に伝えたのかもしれないです。中国系やインド系の同級生もいましたが、なじみのない食べ物を持っていくとやはり注目されていたような覚えがあります。
作野:なるほど。実は私の知り合いで同じように海外で育った日本人の方がいるのですが、小さいころお弁当に入っていたおにぎりが恥ずかしくてごみ箱に捨てていたと言っていました。
八尋:それ、分かります。子どもながらにみんなと一緒が良いんですよね。今思えば、おいしいおにぎりの方が良いのですが(笑)
場所や環境で切り替わるアイデンティティー

作野:ご自身のアイデンティティーに関してはどのようにお考えですか。
八尋:場所や環境によって変わると感じています。オーストラリアにいる時は自分を日本人だと感じますが、日本を含めて海外にいる時はオージーだと自身を認識します。
作野:例えば日本にいる時、具体的にどのような点でオージーらしさを実感しますか。
八尋:そうですね、例えば行き当たりばったりで計画を変えてしまうなど、生活のリズム、ものの考え方が「Easy Going」になっていることに気付く時ですね。
作野:オーストラリア国内で日本人としての感覚で空手を続け、しかしオリンピックではオーストラリア代表として国を背負いました。その点に関してはいかがでした。

八尋:まず、オリンピックで空手種目採用が決定した時点で、「日本人として」この席は他のオージーには譲れないなという思いがありました。ただ、個人競技なので、オーストラリアという国を背負うという意識は当初はあまりありませんでした。ですが本番が近づくにつれ、オーストラリア・オリンピック・チームの一員として出場するのだという意識が大きくなりました。オーストラリア・オリンピック委員会の多くの方々にサポートして頂くなど周囲のビルドアップも大きかったですし、自分の代わりに行けなかった選手がいることを考えると、その選手たちの分もやらねばと思いました。
作野:期待、そしてプレッシャーも大きかったと思いますが、そのプレッシャーをどのようにマネージし、克服されましたか。
八尋:状況が悪くなればなるほど実力を出せるタイプなのでプレッシャーは嫌いではないんです。「やらなあかん」と気合いが入りやすくなるのでプレシャーは大きければ大きいほど良いと思っています。
作野:プレッシャーによって自分を鼓舞し、気持ちを盛り上げ、そしてモチベーションを高めることができるわけですね。
日豪のスタイルの違い

作野:空手を競技として見た場合、八尋さんにとって日本とオーストラリアの違いはどこにあると思いますか。
八尋:日本は部活として空手を始める人が多いため、子ども時代からの練習量が違いますし、強い選手は、勉強が免除され特待生として大学にも行けます。ただ、道半ばでドロップアウトする人が多いのも日本の特徴のような気がします。毎日何時間も練習を続ける生活を長きにわたって続けるうち、センスはありながらも途中で燃え尽き、大学卒業を機に引退する人が少なくありません。その意味では、オーストラリアの方が選手寿命は長いと思います。純粋に空手が好きで仕方がなくて、毎日道場に通っているというような人が多いからです。
作野:好きだから、長く楽しんでいられると。
八尋:ええ、ただ競技で大きな大会を目指すとなると、「楽しむ」の定義も変わってきますね。昔は好きだから道場に通っていても、競技における目標ができると勝つために練習に行くことになるので、純粋に空手を楽しむこととは意味合いが変わってきます。僕自身は、難局において自分をどう成長させられるかと試行錯誤すること自体を楽しんできました。ただ、自分を成長させるためには大変な練習量が必要です。人が練習していない時にいかに練習するか、それを肝に銘じる必要があります。
作野:なるほど。空手のスタイルの違いなどについてはどう思われますか。

八尋:今はグローバル化しているので、大きな違いはなくなりましたが、自分が若い頃は国によってスタイルの違いを感じました。特に日本は伝統を重んじた、あまり動かないスタイルの空手が特徴でした。そしてそれを崩すためにヨーロッパを始めとした多くの国が動きの多いダイナミックな空手を作り上げた結果、日本人がなかなか勝てなくなった。そしてスタイルを変えざるを得なくなったという歴史があります。
作野:ルーツでもある日本の空手が海外からの刺激で変わる、面白いですね。
八尋:進化しないで止まると負けてしまいますよね、何事も。
作野:空手は心技体ということで、心の部分も重要だと思いますが、その点において違いは感じまか。
八尋:日本人は勝ち方はもちろんのこと、負け方においてもこだわりを持っています。たとえ試合に勝ったとしても最後に逃げた上でのことであれば良しとされません。その昔、雑誌のインタビュー記事で「下がるよりは前に出て負けた方が良い」という主旨の発言を読んだことを覚えています。オーストラリアでは、スポーツなので勝てば良いという風潮がありますが、この点において、自分自身の価値観は日本人に近いと感じます。

セカンド・キャリア
作野:オリンピックで八尋さんが入った予選リーグは激戦区だったと伺っています。
八尋:上位2人が準決勝に上がれる5人総当たりのリーグ戦で、僕は勝つことができず予選敗退となってしまったのですが、優勝、準優勝の選手が共にいたリーグでした。ですが、空手界のレジェンドであるラファエル・アガエフ選手(アゼルバイジャン)始め、オリンピックの舞台で強い選手たちと相まみえることができたのは本当にうれしかったです。
作野:オリンピックを最後に、現役を引退されましたが、最初から決めていたのですか。
八尋:ええ。いろいろなスポーツを見ていると、フィジカル的にもメンタル的にも高い位置にいる時に現役を離れられる選手はやはり少ない。スポーツを引退する、あるいはスポーツに引退させられる。そこには大きな差があって、自分は前者でありたいと常々考えていました。
作野:引退させられるのではなくて、自ら選んで引退すると。
八尋:そうです。いろいろ考えた末、オリンピックで引退というのは最高の花道だなと思いました。
作野:競技者としての人生を終えたわけですが、セカンド・キャリアについてお話を伺わせて下さい。
八尋:実は10年ほど前から縁あって仲良くしている方からお声掛けを頂き、間もなくベトナムに移住し、これまでのキャリアとは全く異なる新たな仕事に就くことが決まっています。
作野:現役時代からの人とのご縁によって、別の国でのチャレンジの機会を得られたわけですね。全く異なる環境、更には国をまたいでの挑戦ですが不安はございませんか。
八尋:何事も最初はトントン拍子に進まないということはスポーツで嫌というほど学んできました。厳しいことは分かっていますので、まずはつまずくところからスタートし、負けながらも、こつこつとできることを積み重ねるのみです。それを繰り返すことが結果的には一番の近道だと知っているので、不安を感じることはないですね。
作野:アスリートからの転身はもちろん、キャリア・チェンジは誰にとっても大きなチャレンジですが、新たなキャリア構築に向けて八尋さんが重要だと感じることは何でしょう。
八尋:人とのつながりでしょう。とにかくいろいろな場所、場面に顔を出してつながりを作ることだと思います。また、アスリートを始め、1つの道をある程度極めるところまで進んだ人は成功の仕方、勝ち上がり方を知っているのでたとえ環境が変わっても必ず成功できると思います。ですから、チャンスが来たらあまり考えずに飛び込むことが重要だと思います。
作野:日本で生まれ、オーストラリアで育ち、豪州代表として国を背負い、これからベトナムでチャレンジをされる。八尋さんはこれから世界のどこで生きていきたいとお考えですか。
八尋:飛行機に乗って世界各地を遠征で回るような生活を続けてきたので、これからも世界を股に掛けて活躍していきたいと考えています。でも最後はオーストラリアが良いですね。もちろん日本も好きですし、いろいろな国を回ってきましたが、やはりオーストラリアに帰ってくるといつも、ああ空が高いな、いいなあここは、って思うんです。
作野:やはりオーストラリアが故郷なのですね。最後に、人生の転機を迎えられている方に、八尋さんからメッセージを頂けますか。
八尋:やらない後悔よりやった後悔の方が良いと思うので、もし悩んでいるのであれば何にでも飛び込んでみて下さい。仕事や学業で日本から来られている人はそれだけでも十分「挑戦」だとは思いますが、更に一歩踏み込んでオージーの環境、この地にどっぷり浸かって欲しいと思います。そこでできた縁を大切に、日本人らしさを生かしていけば必ず成功すると思います。勝負を掛ける準備だけはしておいて、チャンスがあれば飛び込む。それだけですね。
作野:本日はありがとうございました。

(3月9日、アーターモン、新極真空手・八尋道場で)