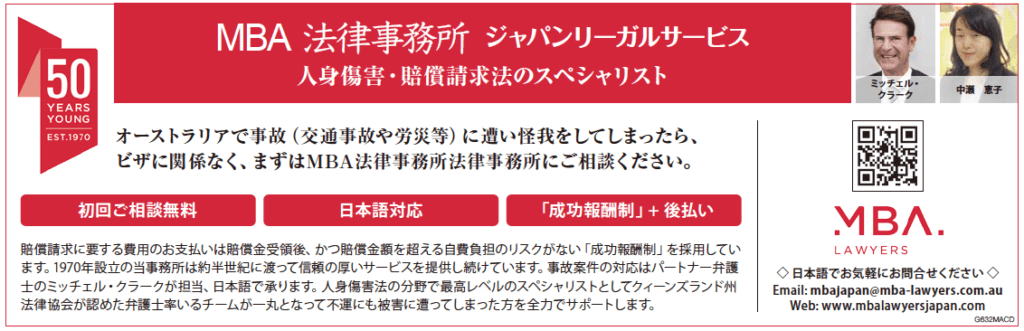第84回 裁判における言葉選びの重要性
公用語を母語としない人が裁判で証言する際、通訳・翻訳のクオリティーが大切なことは言うまでもありませんが、どんな言語であれ言葉選びは非常に重要です。言葉選びのちょっとしたミスが原因で、裁判に負けてしまうこともあるぐらいです。
先日QLD州で、拘留中の難民が法的主張 “ロスト・イン・トランスレーション” (※重要事項が翻訳で失われること)に準じて上訴した裁判に勝ち(QLD州判事が有罪判決を覆した)改めて
言葉の重要性が浮き彫りになりました。
被告のスリランカ難民は英語力に乏しく、訴訟内容が理解できない状況のもと治安判事裁判で有罪となり、懲役刑と拘留施設への送還が言い渡されていました。
3 0 件の詐欺罪に問われたスリランカ出身の被告は、2021年2月に行われた審問を経て懲役2 年の刑に処されました。被告は公正法(Justices Act)222項に準じ、被告の第1言語はタミル語であること、よって英語力が非常に乏しいことを理由にブリスベン地方裁判所に上訴しました。このケースは元もと検察が言及した29件の罪に対し、被告は28件の罪を、そして判事が17件の罪を扱った点が重要です。しかも、原告・被告のどちらからも妨訴抗弁(事実としては認めるものの、有効性や関連性がないため承認
できないという主張)はありませんでした。
被告は全ての容疑について、弁護士を通じて有罪であることを認めたものの、実はその内容をよ
く理解していなかったとして、22年4月29日、ブリスベン地方裁判所で無罪判決がでました。判事
は、被告に対するいくつもの容疑について、審問を経て、不当に有罪判決を受けた可能性があるこ
とに触れました。この不法行為によって、被告は懲役刑に処され、ブリッジング・ビザが取り消されるという深刻な状況でしたが、裁判所は、このスリランカ難民に対する有罪判決を無効にするとい
う判断を下しました(Selvaraja v Queensland Police Service [2022] QDC 94))。
言葉の意味は年々変化していきます。性的暴行の被害者は自らを“victim”(犠牲者)ではなく“survivor”(生存者、逆境に強い人)と称します。なぜなら、今日“victim”というワードには、
“coward”(弱虫)や“pretender”(偽善者)のように重荷を背負った不幸な人というイメージがあ
るからです。行為の対象者(何か悪いことをされた人)として使用されるワード “victim”は、まる
でその人が受け身であるかのような印象を与えます。興味深いことに、被害者が受けたダメージが
ぱっと見て判断できないような時(レントゲンや血液検査などでは分からない精神疾患など “隠れた傷害”)にも同じようなことが起きます。一方で、火傷被害者や事故で足を失ってしまった人のように、身体障害が明らかな場合、“victim” という言葉の含みに関する問題は起こりません。
当然のことながらオーストラリアの裁判所でも、英語を母語としない人たちとのコミュニケーションを含め、こうした言語問題が認識されつつあります。ガイドラインも幾つか出ていますが、既に司法行政で実践されていることもあります。
例えば、日本人が暴行事件に巻き込まれ、日本語で000通報したとします。その時の通話録音は日本語から英語に訳され、後の裁判で重要な証拠となります。プロが音声を翻訳する際、通常、電子ツールを使用して音声の質を上げるのですが、おおむね、1分間の音声の翻訳には1時間を要します。このように、裁判に関わる翻訳者のレベル、クオリティーが重要であることは言うまでもありません。裁判所業務を請け負った通訳・翻訳者は、原告、被告いずれにも協力してはいけないルールがあります。
過去、私がサポートした日本人のケースで、実際にあったことをお話ししましょう。相手弁護士が日本人の証人に、ある資料のある部分について尋ねた際、英訳された資料と原本である日本語資料のページ数(つまり、英語と日本語文章の長さ)の違いに全く気付かず、とんちんかんなページ数を参照し、判事の前で大きなへまをおかしてしまった(私ではなく、相手弁護士です!)ということがありました(日本人による賠償請求案件のベンチマークとなっている Yamaguchi v QBE [2016] QSC 151)。
日本語でも同じようなことがあるでしょう。例えば日本語初級者なら “ビル” と “ビール” を混同してしまうことがあるかもしれません。「猛暑日に、喉が渇いて冷たいビルを飲みながら運転していたら、事故を起こしてしまった」という証言を裁判官が聞いたらびっくりしてしまいますよね。
証人尋問、特に相手側に有利な証言をする人に質問する際「回答が分かっている質問、または、どんな回答でも構わない質問以外はしてはいけない」という鉄則があります。
イギリスで、耳をかみちぎられた人が相手を訴えた有名なケースがあります。
被告は 「I didn’t do it(やっていない)」と言いました。
重要証人に対する反対尋問の中で、被告の弁護士が「あなたは主尋問中に、私のクライアントが耳をかみちぎったのを見なかった、と証言しましたよね?」(主尋問中に明らかになった、自分のクライアントにとって有利な証言を繰り返してもらうのは、反対尋問の模範質問です)と尋ね、証人は「Yes Sir(はい)」と答えました。
通常ここで、被告の弁護士は反対尋問を終わらせますが、なぜかこの弁護士は、回答が分か
らない質問を続けてしまったのです。
Q: What did you see?(それで、あなたは何を見たのですか?)
A: I saw spit it out.(吐き出したのを見たんですよ)
このように、言葉の選択ミス1つで裁判結果が大きく変わることもあるのです。2カ国語が関係す
る裁判では、更にその重要性が高まるでしょう。

ミッチェル・クラーク
MBA法律事務所共同経営者。QUT法学部1989年卒。豪州弁護士として30年の経験を持つ。QLD州法律協会認定の賠償請求関連法スペシャリスト。豪州法に関する日本企業のリーガル・アドバイザーも務める。高等裁判所での勝訴経験があるなど、多くの日本人案件をサポート