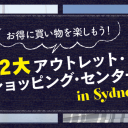坂井健二の
「がんばれ、オーストラリア映画!」

かつてグローバルなメガ・ヒット作品を数多く生み出したオーストラリア映画界。荒廃した近未来を描いたアクション映画『マッド・マックス』(1979年、ジョージ・ミラー監督、メル・ギブソン主演)や、辺境でワニと格闘するオージー男のニューヨーク珍道中を描いたコメディー映画『クロコダイル・ダンディー』(1986年、ピーター・フェイマン監督、ポール・ホーガン主演)など、オーストラリア独自のテイストを打ち出した作品が、他の英語圏のみならず日本を始め世界中で人気を集めた。ハリウッドを代表するスーパー・スターたちも、ギブソンに続いて、ニコール・キッドマン、ラッセル・クロウ、ケイト・ブランシェットら多数を輩出した。ところが、オーストラリア制作の映画に焦点を当てると、21世紀に入って次第に勢いが衰え、過去10年間に至っては全くと言っていいほどヒット作に恵まれていない。日豪プレス元発行人の在豪映画ジャーナリスト・坂井健二氏が、低迷期が続くオーストラリア映画界にエールを送る。
最近のオーストラリア映画から


不調が続くオーストラリア映画で、ある程度の結果を出した最近の映画は、『ブレス あの波の向こうへ(Breath)』と『黒衣のレディーズ』(Ladies in Black)の2本。『ブレス』は、TVシリーズ『メンタリスト』でスターになったサイモン・ベーカー主演で、脚本と監督もベーカーが手掛けました。正直言って退屈。70年代の年上の女性と初体験する少年のスイート・ビターな話だが、この類の映画でもっとましなのはいくらでもある。サーフィンを持ってきたのがみそだが、それだけで映画は救えない。好感度が高いナイス・ガイのベーカー初監督作品に、水を差したくはないのですが……。その監督ぶりは「一応映画にはなっていました」というところでしょうか。
『黒衣のレディース』は、ブルース・ベレスフォードが久しぶりにメガホンをとった映画。1959年のシドニーの大きな百貨店で働く女性たちのドラマをコメディー・タッチで描いたもの。黒衣ということで葬式へ行く女性を思い浮かべるかもしれませんが、この黒衣は百貨店のユニホームです。ベレスフォードはオーストラリアから国際的な監督になった一人。ジェシカ・タンディがオスカーをとった『ドライビングMissデイジー』が有名。もちろんベテラン監督の作品ですので、映画としては完成していますが、面白いかと聞かれると答えに窮します。
2作品ともベストセラー小説(国内で)の映画化で、共にノスタルジックなストーリーです。国内では、まずまずの結果を出したと見られています。オーストラリア映画のつらいところは、絶対的な国内人口が少ないので、国内で一応の成果くらいでは黒字にならないところですね。映画を商業的に成功させるためには、海外での成功(特にアメリカ)が、必須です。ベーカーの『ブレス』はすでにアメリカで封切られましたが、大惨敗。ベレスフォードの『黒衣のレディーズ』は、アメリカでの封切りさえ決まっていません。
映画は制作費の3倍の収益でトントンと言われています。簡単に言うと、例えば20ドルのチケットの半分が劇場へ、半分が製作者サイドへ行きます。実際にはそれに宣伝費が上乗せされるのです。
ベイカーの作品は、制作費が約700万ドルで総収益は400万ドル。ベレスフォードは、約1,100万ドルの制作費に対して、約1,100万ドルの収益(アメリカ公開は未定)を上げました。今後テレビ局へのセールスとDVD化での収益が望めますが、劇場で当たらなかった作品がそれで大きな稼ぎになるとは期待できません。
ということで、映画がビジネスである限り「儲けて官軍、損して賊軍」なら、上記の2作品が官軍になるのは不可能です。国内で一応の結果を残したと言われる作品でさえ、実情はこんなものなんですね。
オーストラリア映画の歴史
オーストラリア映画の第1号が、ハリウッドのそれより古いことを知って驚きますが、オーストラリア映画が世界中で認知されたのは、1970年以降。満を持したようにヒット作や名作が続出しました。
商業的に大成功したのは、何と言っても『マッド・マックス』。文芸作としては、『我が青春の輝き』『ピクニック・アット・ハンギング・ロック』、『ブレイカーモラント』、『ニュース・フロント』、『ストーム・ボーイ』、『誓い(ガリポリ)』など。そうそう、艶笑(えんしょう)コメディーの『アルビンパープル』シリーズもウケました。これは、日本人が観たらアホみたいな映画としか思えない代物ですが、特にオージーの男性には大ウケ。
80年に入り、『クロコダイル・ダンディー』というメガヒット作が世界中を席巻しました。続いて、カーク・ダグラスを迎えて作った『スノーウィー・マウンテンから来た男』や『ファーラップ』『思春期ブルース』、『ヤング・アインシュタイン』などが当たりました。
『思春期ブルース』は、私も少し関わりがあるんですね。これはサーファー・ギャル(古い?)2人が実体験を書いた本がべストセラーになり、映画化(べレスフォード監督)されたものですが、日本の映画雑誌「スクリーン」を出していた近代映画社に頼まれ版権を取って訳し、映画の封切りに合わせて発売しましたが(日本語のタイトルは『ハイスクール・グラフィティー 渚のレッスン』)、映画も本も不発に終わりました。
90年代には『マッド・マックス』のジョージ・ミラーが、今度は豚を主人公にしたコメディ『ベイブ』(1995年)を大ヒットさせました。この年はコメディが当たった年で、『プリシラ』や『ミュリエルの結婚』『ダンシング・ヒーロー』もヒット。ジェフリー・ラッシュがオスカーを取ったシリアス・ドラマ『シャイン』もこの年の作品です。そうそう、立ち退きをめぐるコメディー『ザ・キャッスル』もウケました。
2000年代に入り、徐々に陰り見せ始めたというか、スローダウンし始めるんですね。それでも『オーストラリア』『ムーラン・ルージュ』『ザ・サファイアーズ』『ケニー』などが健闘。ラッセル・クロウが初監督した『ザ・ウォーター・ディバイナー』も、一応ヒットと考えて良いのでは。
そしてここ10年は、合作はありますが純粋な意味でのオーストラリア映画の活躍というのが聞かれませんね。
オーストラリアには映画作りに関して、「10BA」という政策があります。簡単に言うと、映画産業奨励策で、70年代後半から起きたオーストラリア映画の大躍進を、政府が後押しするカタチで生まれたものです。映画に投資することで、税控除の恩恵が受けられるのです。確かにこのおかげで、しばらくは映画ラッシュになりました。
ただ、なんでも諸刃の剣だと思いますが、愚作が溢れたのも事実。なぜなら、仲介に銀行や会計事務所が入ることで応募条件に合致することが優先され、「この映画を作りたい!」という情熱から生まれた作品が少なかったのですね。10BAは現存していますが、投資家にとって、もう魅力のあるものではなくなっているのが現実ではないでしょうか。



世界へ羽ばたいた監督とスター
前述のべレスフォードやミラー以外にハリウッドに進出したのは、『ピクニック・アット・ハンギング・ロック』のピーター・ウェアー。『目撃者(ハリソン・フォード)』や『今を生きる(ロビン・ウィリアムス)』をヒットさせ、石田純一が主演したTVドラマのミニ・シリーズ『カウラ・ブレイクアウト』のフィリップ・ノイスは、『硝子の塔(シャロン・ストーン)』や『今そこにある危機(フォード)』が成功。『ジミー・ブラックスミスの歌』というアボリジニの悲劇を描いた文芸作で注目されたフレッド・スケピシは『愛しのロクサーヌ(スティーブ・マーティン)』、『ロシアハウス(ショーン・コネリー)』をヒットさせました。以上は全て、70年代に起きたオーストラリア映画興隆期の中心的な人たち。
それからずっと後に出てきたのは、『ダンシング・ヒーロー』のバズ・ラーマン。レオナルド・ディカプリオと気が合ったのか、『ロミオ+ジュリエット』、『華麗なるギャッツビー』のリメイクにディカプリオを使って当てました。作品的には前作(オリビア・ハッシー版とロバート・レッドフォード版)を超えてないと思いました。異色なのは、ホラー映画の人気シリーズ『ソウ』は、メルボルンの若者2人(ワンとワンネル)がデモ・テープをワーナー・ブラザースに送り、それが気に入られ、ハリウッドで映画監督としてデビューする夢を叶えたのですね。


スターでは、何と言ってもメル・ギブソンとジュディ・デービスがパイオニア。ギブソンは『マッド・マックス』が日本で大当たりし、スターとなった。このことを彼は知らなくて『スクリーン』の初取材で告げると、パッと顔を輝かせ見せた笑顔は今でもよく覚えています。
その後何度も取材をさせてもらいました。夏号の写真のために冬の寒空のビーチで、海パン1つで波打ち際を何度も走ってもらったのは、今では考えられない出来事です。友達になったなんて自惚(うぬぼ)れたことは言いませんが、パブでビールを飲みながらよく雑談しました。当時ギブソンはクロヌラ(シドニー南郊のビーチ・タウン)に2階建ての小さな家を買ってローンがあり、1児の父親で、日本でCMに出れないかと打診され、当時の編集長を通して動きました。映画からバイク関係でと思いホンダに持って行きましたが、結局まとまらなかったです。
彼はアメリカでスーパー・スターになった後、日本のビールのCMに出ました。それだけに、再婚した若いロシア美人とのDV騒動や、反ユダヤ人への差別発言でスキャンダルの嵐のど真ん中に居る時、願っていたことはただ1つ。どうか「ハリウッドの悲劇」にはならないで欲しいということでした。2016年に監督した『ハクソー・リッジ』が成功しカムバックした際は、胸をなでおろしました。
デービスはマイルズ・フランクリンの自伝『我が青春の輝き』で注目後、巨匠の故デービッド・リーンの大作『インドへの道』のヒロインに抜擢されたことが、世界のスターへのパスポートに。その後ウディ・アレンのお気に入りとなり、何度も彼の作品に出ました。
続いて、ニコール・キッドマン、ラッセル・クロウ、ガイ・ピアースが登場。キッドマンはトム・クルーズと離婚後、『めぐりあう時間たち』でオスカーをゲット。芸術的にはクルーズを抜きました。クロウも『グラディエーター』でオスカーを。最近は超肥満気味ですが。
ケイト・ブランシェットは、NIDA(国立演劇学校)を卒業後(ギブソンもデービスもここの卒業生)、数年後には英映画『エリザベス』に抜擢されて世界中に知られるようになり、あっという間に演技派トップ・スターの座を確保。オスカーはダブル受賞。インタビューの際、メルボルンのハイ・スクール時代のベスト・フレンドは、日本人だったと言っていました。
ナオミ・ワッツは、長い間B級女優の座に留まっていましたが、鬼才デービッド・リンチの『マルホランド・ドライブ』でびっくりするような演技を見せ、ハリウッド版『ザ・リング』が大ヒット。名実ともにA級スターへ。
ヒュー・ジャックマンは『Xマン』でビッグ・アクション・スターに。現在最も高い主演料を取るのはこの人かも。国内ではコメディアンからスタートして、ハリウッドでは2枚目俳優に転じたエリック・バナ。クリス・ヘムズワースは大ヒットシリーズ『マイティ・ソー』が続いている限り安泰。ローズ・バーンは清純派美人にしては、意外にもコメディー系でヒットが続きます。いわゆるイケメンからは程遠いが演技派で、監督としての才能もあるジョエル・エドガートン。
そして今一番の注目の的は、マーゴット・ロビー。セクシー系正統派美女で、ディカプリオの『ウルフ・オブ・ウォール・ストリート』の愛人役でハリウッド・デビューした後、着実にキャリアを築き、奇麗なだけではなく『アイ、トーニャ 史上最大のスキャンダル』でオスカーにノミネート。ヘムズワーズと共に長寿ソープ『ホーム&アウェイ』の出身。現在主演作が目白押し。



最後に忘れてならないのは、ラッシュとジャッキー・ウィバー。ラッシュが『シャイン』に主演したのは45歳の時。子役からスタートし国内ではよく知られたベテラン女優のジャッキーに至っては、メルボルンを舞台にした映画『アニマル・キングダム』でオスカーにノミネートされ国際的に大ブレイクとなったのだが、当時なんと63歳。2人が多くのオーストラリアの俳優たちに大きな希望を与えたのは間違いない。年齢は関係ない、チャンスは来るんだという希望を。
今後オーストラリア映画がどういう展開を見せるのか予測がつきません。起爆剤として、『クロコダイル・ダンディー』のようなオーストラリア・カラーが満載の、そして世界中に大アピールする映画の登場を待っています。

KENJIS MOVIE REVIEW
kenjismoviereview.com
筆者プロフィール
シドニー在住の映画ジャーナリスト。1977年に月刊日本語新聞「日豪プレス」を創立。2014年まで発行人を勤める。雑誌「スクリーン」シドニー通信員。これまでにオードリー・ヘップバーン、メル・ギブソン、ケイト・ブランシェット、ジャッキー・チェン、ブルック・シールズ、ジャクリーヌ・ビセット、マーク・ハミル、ルパート・イベレット、岸惠子、吉永小百合、美輪明宏、倍賞美津子、勝新太郎、樹木希林、八千草薫など、東西のトップ映画スターを数多くインタビュー。2018年には、映画批評ブログ『KENJIS MOVIE REVIEW』(kenjismoviereview.com)を立ち上げ、新旧の洋画・邦画のレビューに加えて芸能界や豪政界のスキャンダルなど幅広いジャンルの批評を展開している。