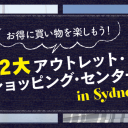オーストラリア各地で話題の日本映画を一挙上映!
第22回 日本映画祭
ジャパンファウンデーションが主催する毎年恒例の「日本映画祭(The Japanese Film Festival 2018)」が、キャンベラ、ブリスベンでの開催を終え、11月15日から25日にかけてシドニーで開催される。本特集では、お薦め作品の紹介と注目作『生きてるだけで、愛。』の関根光才監督のインタビューをお届けする。人気の日本映画を英語の字幕付きで観に出掛けよう。
特別インタビュー
『生きてるだけで、愛。』の関根光才監督
※『生きてるだけで、愛。』の作品紹介はこちらから。
数々の企業CMや有名アーティストのミュージック·ビデオ(MV)を手掛けるディレクター、またドキュメンタリーやショート・フィルムの監督として活躍している関根光才監督。同監督にとって、劇場長編映画デビュー作となる『生きてるだけで、愛。』が日本映画祭で上映される。また、11月24日に、メルボルンで映画上映後のQ&Aセッションを行うスペシャル·ゲストとして来豪するに当たり、監督·脚本を手掛ける上で心掛けたことや撮影時の様子など、同監督に話を伺った。
関根光才
プロフィル◎1976年生まれ、東京都出身。上智大学文学部哲学科卒業後、CM制作会社入社。2006年、カンヌ国際広告祭新人監督賞「Young Directors Award」でグランプリを獲得。また、安室奈美恵、AKB48、Mr.ChildrenらのMVや数々の企業CMを手掛け、広告映像ディレクターとして国際的な知名度を獲得し活動中
――今回、オーストラリアの日本映画祭で関根監督がメガホンを取った『生きてるだけで、愛。』が上映されますが、同作品を制作することになった経緯について聞かせてください。
原作は、本谷有希子さんの同名小説なのですが、彼女の書く文体は非常に独特で「人間味」を煮詰めてそのインクで文章を書いているような濃いものです。中でも、初期の作品である同作は、若いころの彼女の疾走感に満ちています。そのエネルギーに魅了されました。彼女の小説自体は、若いころの社会に対する恨み言や罵詈雑言を書き殴っていて、それがある種、キュートなコメディーになっている感じだったのですが、僕はそれを、映画化するに当たり、近代社会のシステムを破壊し、突き抜けようとする人間の生命力とか、狂おしい情念というものに転化させてみようと考えました。大人の人間劇の映画として描きたいと思い、そのアプローチがプロデューサーの甲斐さんの意見と一致し、映画化をオファーしたのです。

――映画化に当たり、監督·脚本を手掛ける上で心掛けたことはどのような点ですか。
脚本を書くに当たり、小説ではほぼ主人公のモノローグだけで構成されていたところを、映画として成立させるために、女性1人の視点で描かれていたところに加え男性の視点を入れました。回想が散りばめられていましたが、ほとんどそれらをそぎ落として現在のストーリーを膨らませて、「今」を生きる彼女と彼のストーリーに集約しています。また、インターネットやその他、現代的すぎたりニッチすぎたりする要素を排除して、声だけの登場ですが、「姉」という役を生み出し、できるだけシンプルなストーリーになるように変えています。
――関根監督にとって、同作が劇場長編映画デビュー作となりますが、撮影を進める中で苦労した点、工夫したことなどはありますか。
ひと言で映像と言ってもMVやCMの撮影の進め方と映画は大きく異なり、スタッフのやり方やモチベーションの置き所も大きく異なります。映像は1人で作れるものではなく、たくさんのキャストやスタッフが関わるので、自分が初監督の作品のために皆ができるだけ仕事がしやすい、その雰囲気作りには配慮しました。作品の内容が痛々しかったり、ネガティブな分、ずっと張り詰めるというよりは、ある種ゆるりとした空気から撮影を始めて、段々と皆が具体的に「こういう映画か」と体感できた時にクライマックスの張り詰めた空気を撮れるように、最初はあえて油断しているようにしたり、のほほんとしてみたりしていましたね。
――同作のヒロイン·寧子を演じた趣里さん、そして津奈木役を務めた菅田将暉さんら俳優陣の演技はいかがでしたか。監督が2人にそれぞれ求めたもの、それに対して返ってきたものは何でしたか。また、撮影時のエピソードなどがありましたら教えてください。
趣里さんは、役を演じるというより、役の中にある自分を「生きて」いたように思います。それが彼女の演技を非常にリアルに、身に迫るものにしたのだと思います。彼女自身の挫折や絶望、そしてそれを打ち破り、乗り越えようとする欲動を彼女はフィルムにぶつけようとしていた。それを感じていたので、僕は彼女に全幅の信頼を置いていました。
菅田将暉さんは、若いけれど非常に経験豊富で幅のある人。日本では知名度も非常に高いです。それでも彼にとって、理解不能なほど「冷めて」いて、物事との間に距離を置き、何に対しても受動的に見える人を演じるのはチャレンジだったのではないでしょうか。「受け」の演技ほど演じ辛いからです。それを彼は見事に、自分の中で完成された演技プランと共にやってのけたと思います。
――同作で、監督にとって特にお気に入りのシーンなどはありますか。
いろいろありますが、シャワーを浴びるシーンは気に入っていますね。濡れるシーンのため、一発勝負ですが、その一発で見事な寧子の狂気と美しさが撮れたと思っています。また何と言ってもラストの趣里さんの表情はものすごいパワフルで美しいシーンだと思っています。それは撮影の中盤に撮りましたが、そのシーンが撮れたことでその後の撮影の指標ができました。
――来豪されるのは初めてですか?また、来豪されるに当たって楽しみにしていることはありますか。
何度か撮影で来ていますが、シドニーばかりだったので、メルボルンなど他の都市は始めてです。機会があれば自然の風景に触れたり、先住民族の文化に触れたりしたいですね、そこまでの時間はないかもしれませんが。
――今後挑戦していきたいと考えていることはありますか。監督としてはもちろん、プライベートでもあれば教えてください。
映画を監督するのは長年の目標でしたが、同作と同時期に公開した長編ドキュメンタリー映画『太陽の塔』と合わせて2つの作品を今年公開することができました。しかしまだ、やっとスタート·ラインに立ったという気分なので、これからどんどん長編に挑んでいきたいですね。監督という仕事は、仕事とプライベートの境目があいまいなので、それが当面のチャレンジになると思います。
――最後に、関根監督の来豪を楽しみにしているオーストラリアのファンの方に向けてメッセージをお願いします。
僕はまだ長編の世界では知られていないので、ファンという人はいないと思いますが、この映画は日本のとあるおかしな人間の姿を映し出しているようで、実はどこの場所でも共通して言える、人間の普遍的なテーマを扱っています。人間が人間と深くつながり合いたいという欲求が、SNSなどが氾濫する中でそういったうわべのものより、より本質的なものを更に求めるようになった時代で、同作が伝えようとしているメッセージがオーストラリアの皆さんにも届くことを願っています。